株式会社ベストは、山形県鶴岡市に本社を構え、給食受託、介護食、配食サービスを提供している企業です。彼らの企業理念は、「健康でありたい」「健康であってほしい」という想いを“食”を通じてつなげ、支え続けることです。社会の高齢化が進む中で、日々の食の提供を通じて人々の生活を支える、社会にとって不可欠な役割を担っています。今回は、“食”を通じて地域の健康を支え続ける株式会社ベスト様の取り組みと、その根底にある想い、そしてこれからの展望について、代表の方にじっくりとお話をお伺いしました。
<聞き手=石嵜渉(学生団体GOAT編集部)>
【野澤様の今までの経緯・背景】
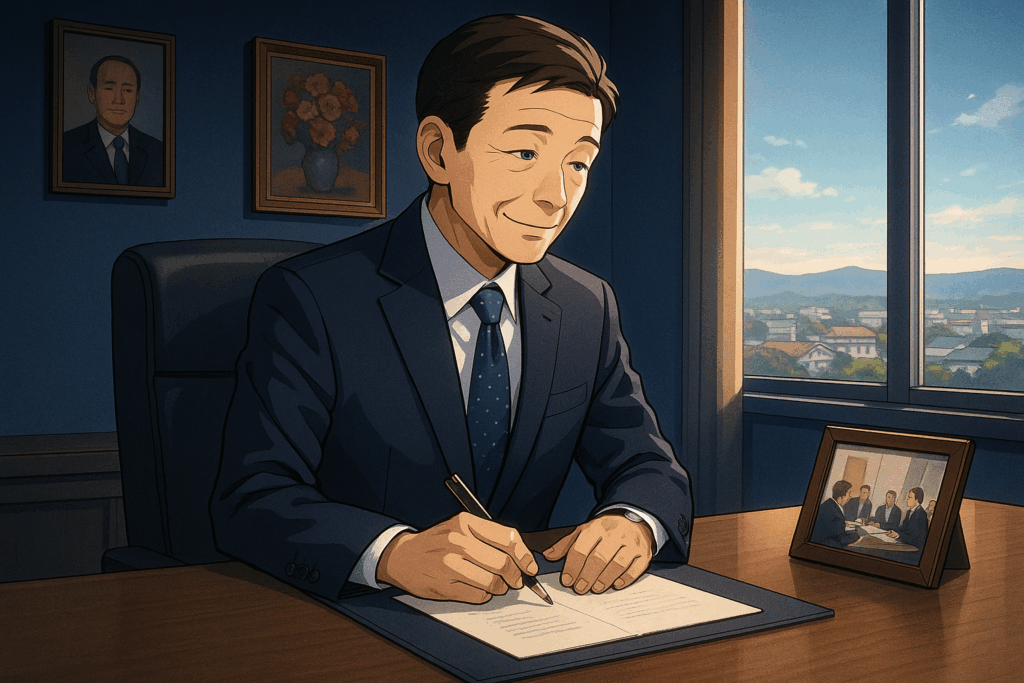
株式会社ベストは、現会長である斎藤氏によって創業され、今年で40年の節目を迎える歴史ある企業です。私は約3年前、親会社である富士産業株式会社から代表取締役として、ベストの社長に就任いたしました。富士産業がベストの事業を承継したのは、当時、ベストに後継者が不在であったことが背景にあります。
私の社長就任は、当時の状況から自然な流れで決まりました。富士産業で取締役を務めていた私は、ベストの株式譲渡に関する議題が取締役会で議論された際、適任者が他に見当たらないと感じており、最終的に社長からの依頼を受け、その役割を引き受けることになったのです。
富士産業では長年経営に携わってきましたので、ベストの経営もこれまでの経験の延長線上にあります。経営者として、創業者が経験されたような苦労とは異なるかもしれませんが、「人とお金」という事業の根幹に関わる課題には常に直面しています。特に人材の確保は、今日の事業継続において最も重要な要素であると認識しており、この課題に日々向き合っています。
取材担当者(石嵜)の感想
野澤社長が自ら立候補されたのではなく、周囲の状況や期待から社長に就任されたという経緯は非常に興味深く、自然な流れでの事業承継を担われていることが伺えます。元々親会社で経営に携わられていたというご経験も、今の立場に活かされているのだと感じました。
創業者の苦労とは異なるものの、「人とお金」という経営の根本的な課題に真摯に向き合われている姿勢に、経営者としての強い責任感と覚悟を感じました。

【株式会社ベストの事業・業界について】
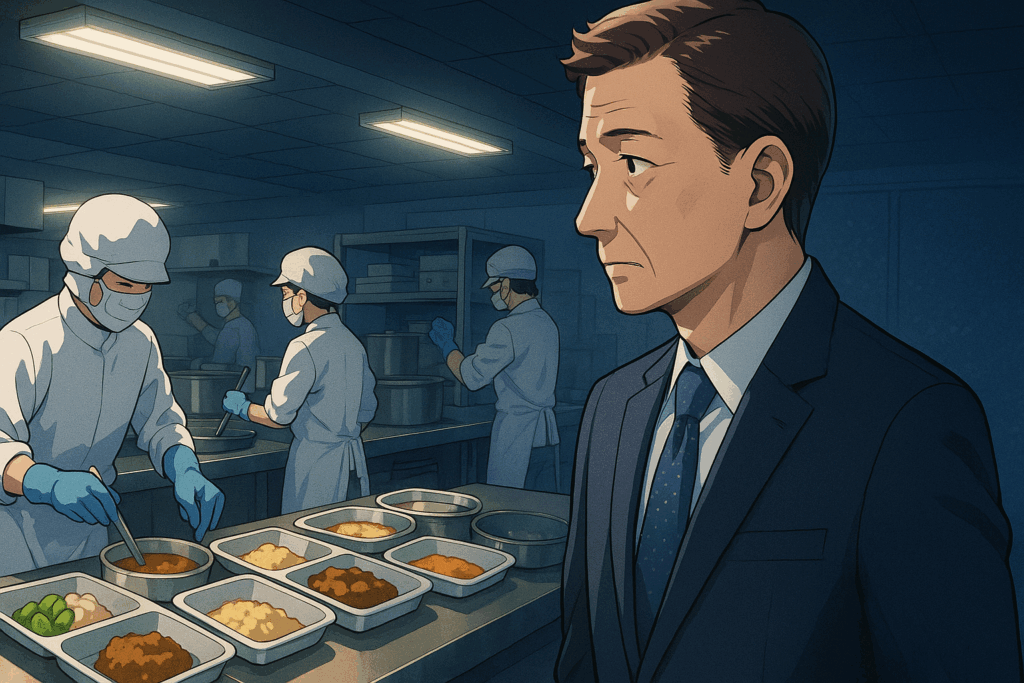
私たちが提供する給食の委託事業や介護・在宅での食事提供は、毎日異なる献立を作成し、お客様一人ひとりに合わせた食事を提供する必要がある点で、非常に専門性の高い分野です。これは、セントラルキッチン方式で均一な味を提供する外食産業とは一線を画します。この事業の根幹を支えるのは「人」であり、私たちの事業に共感し、食事を通じてお客様に寄り添う思いを共有できる人材こそが最も重要であると考えています。
現在、多くの業界が人手不足に直面していますが、私たちの業界も例外ではありません特に新卒採用は困難を極め、以前と比較して採用数は大きく減少しています。このため、技能実習生や特定技能の外国人材の採用も積極的に行っていますが、それでもなお人手不足は解消されておらず、深刻な課題として認識しています。この給食受託業界は、現在「混沌としている」と表現できます。特に、病院や介護施設に対して「3食異なる食事を提供し続ける」という点が大きな課題です。
多様な企業が解決策を模索し、技術や手法を開発していますが、業界全体として統一された解決策や方向性が定まっていません。これは、診療報酬や介護報酬といった国の制度による価格統制下で事業を行っておりますが、現場ごとの細やかなニーズ(患者様の病状、利用者の背景、地域性など)に対応し続けることが非常に困難になっているためです。さらに、社会保障費がほとんど上昇していない一方で、食材費や人件費は高騰を続けており、国の定めた報酬ではコストを賄いきれない現状があります。
献立作成は、特に労力を要する作業の一つです。病院では、通常の食事に加えて、糖尿病食、減塩食、腎臓病食など、患者様の病状に応じた多様な治療食を同時に提供する必要があります。介護施設では、要介護度の高い利用者が増えるに伴い、刻み食、極刻み食、ミキサー食、ペースト食、ソフト食など、様々な形態の食事を作り分ける必要があり、ここにも膨大な手間と人手がかかっています。この業界は、デジタルの導入が難しいという特性も持ち合わせています。
AIによる献立作成は技術的に可能かもしれませんが、各施設が設定する基準や、病院の管理栄養士や院長など、複数の決裁者の主観が大きく影響するため、継続的な献立の承認を得ることが容易ではありません。AIはまだ完璧ではなく、味を含めた質の高い献立を継続的に提供できるレベルには達しておらず、データも不足しているのが現状です。厨房内でデジタル化できるのは、中心温度の記録などごく一部に限定されます。
地方における人手不足は特に深刻で、私が拠点とする山形県鶴岡市では、生産労働人口が全国平均の約2倍の速さで減少しています。これにより、事業としては成り立っているにも関わらず、人手不足が原因で事業継続を断念せざるを得ない「人手不足倒産」のような現象も現実に起こっています。採用活動においては、ハローワークからの応募が最も多く、その他に紹介や地元の媒体を活用しています。
こうした状況の中で、高齢者に不足しがちなタンパク質補給のため、納豆菌を用いたタンパク質生成技術を持つスタートアップ企業と、介護食への応用を目指した共同開発を進めています。特に高齢者施設では、タンパク質の強化が求められており、肉や魚、牛乳などが十分に摂取できない高齢者のために、タンパク質パウダーなどの商品も取り扱っています。タンパク質は筋肉量の維持だけでなく、高齢者が日常生活を健やかに送る上で極めて重要な栄養素です。
取材担当(石嵜)の感想
この業界の課題が想像以上に複雑で多岐にわたることに驚きました。特に、国の価格統制下での事業運営、日々の献立作成の難しさ、そして多様なニーズへの対応は、まさに「混沌」という言葉がぴったりだと感じます。人手不足が深刻化する中で、AIやデジタル技術の導入が難しいという現状も、現場のリアルな課題として深く理解できました。
タンパク質補給という高齢者の健康に直結する課題に対し、
新しい技術を取り入れて共同開発を進める姿勢は、まさに業界が直面する困難を乗り越えようとするチャレンジ精神の表れだと感じました。

【株式会社ベストの今後の展望】
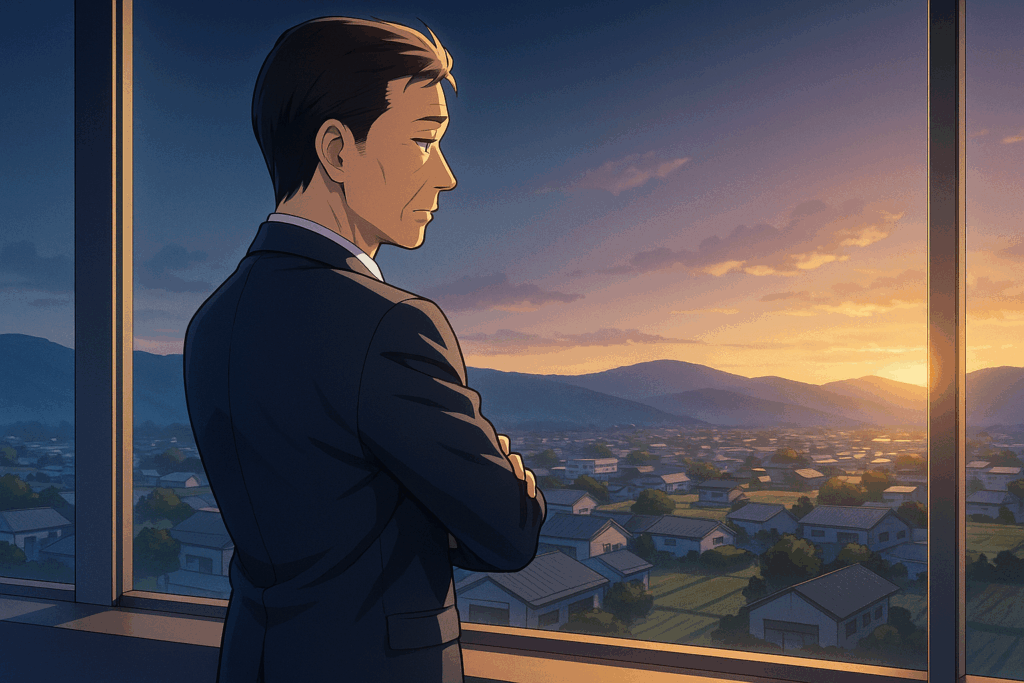
私たちは、「3食毎日提供し続ける」という、想像以上に大変なこの仕事に今後も挑戦し続けたいと考えています。デジタル化が困難で、常に喫食者の目の前まで食事を届けなければならないこの事業において、人手不足や人口減少が進行する中で、どのように提供を継続していくかが最大の課題です。この解決策の一つとして、グループ会社と協力し、さまざまな商品の開発を進めています。これらが市場にどこまで受け入れられるかを検証しながら、業界全体の大きな流れを創り出す、あるいはその流れに乗っていくことを目指しています。
現状のままでは、特に地方の福祉施設において、食事の提供が困難になり、止まってしまう事態が起こり得ると危惧しています。2年前に広島で給食業者が倒産し、学校給食が出なくなった事例がありましたが、これと同様に、費用や人手不足が原因で「明日から給食が出ません」という事態が起こる可能性は十分にあります。特に幼稚園や保育園の給食は、施設ごとの単位が小さく、提供にかかるエネルギーが大きいため、地方から崩壊するリスクが高いと危惧しています。大手の給食会社は、採算が合わない地方の事業から撤退する傾向にあり、地元の会社がその担い手となっています。
しかし、私たち地元企業も人手確保には苦慮しており、現状の方法で食事提供を継続できるかは非常に厳しい問題です。来年以降、お客様に提供方法の変更を理解してもらい、それに対応していくことが今後の大きな分岐点となるでしょう。人口が減少し続ける中で、従来の提供方法の維持は困難になりつつあります。
学校給食や幼稚園・保育園も同様で、かつては人気の高かった求人ですが、今では働き手が見つからない状況です。アレルギー食への対応の厳格化や食中毒事故の発生も背景にありますが、人口減少の影響から夏休み等の長期の休みや働きやすい労働時間帯である職場ですら人が集まらない状況です。このままでは、幼稚園や保育園では親御さんが弁当を持参する昔の形に戻る可能性すらあります。
しかし、これらの厳しい課題は同時に大きなビジネスチャンスでもあります。デジタル化が難しく、体力的に大変な、いわゆる「3K」の職場と見られがちですが、ここにこそ変革と解決の大きなビジネスが眠っていると確信しています。この問題に真摯に取り組むことができなければ、将来的に私たちは食事が手元に届かないという、非常に現実的な問題に直面するかもしれません。
取材担当(石嵜)の感想
野澤社長が語る「3食提供し続けることの難しさ」と、それによって地方で給食がストップする可能性は、非常に衝撃的な現実でした。特に、幼稚園や保育園で給食が提供できなくなるという話は、未来を担う子供たちに直結する問題であり、社会全体で目を向けるべき喫緊の課題だと強く感じました。
厳しい現状の中にビジネスチャンスを見出し、冷凍食品や提供方法などの新しいアプローチで挑戦しようとする姿勢に、未来への強い責任感と熱意を感じました。この業界が直面している「混沌」を乗り越えることが、今後の日本社会にとって不可欠であると再認識しました。

【野澤様から学生へのメッセージ】
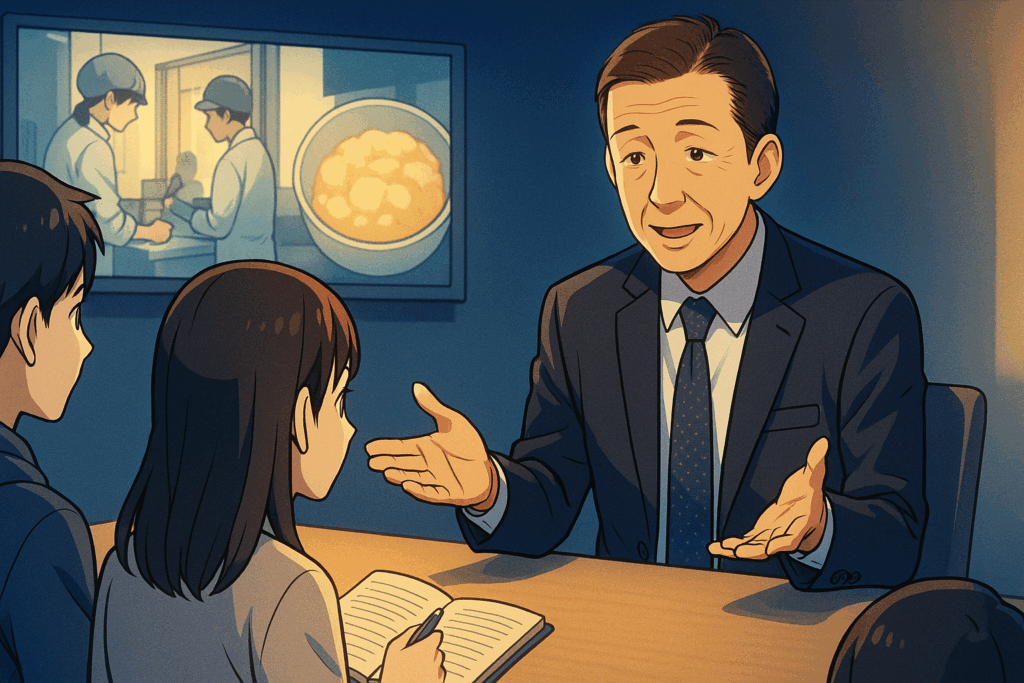
若者の皆さんには、ぜひ様々なことにチャレンジし、たくさんの失敗を経験してほしいと願っています。実際にやってみなければ分からないことばかりですし、学生のうちなら失敗しても大きなリスクはありません。私たちの話を聞かなければ、この業界の現状や課題を知る機会はなかったかもしれません。
AIに聞いても、表面的な情報は得られるかもしれませんが、現場の「現実」やそこに潜む真の「問題・課題」は決して教えてくれません。ビジネスは「ギャップ」、つまり課題や問題の大きさが、そのままチャンスの大きさに直結します。そのギャップがどこにどのように存在するかは、自分の足を使って現場に行き、目で見て、現場の人に話を聞かなければ分からないものです。
まさに「百聞は一見に如かず」です。AIに頼りすぎるのではなく、自ら行動し、リアルな情報に触れることを強くお勧めします。特に、高齢者介護の分野は、現在の50歳代が介護を受けるようになるまで30年以上の期間、大きなビジネスが残っています。働き手がさらに少なくなる中で、どうやって食事を提供し続けるかという問いに対する明確な答えはまだ見つかっていません。
この「混沌」とした状況の中にこそ、大きなビジネスチャンスが眠っていると確信しています。デジタルで解決しにくい、いわゆる3Kの職場ではありますが、そこには社会を支える上で不可欠な、そして非常に大きな価値を創造できる可能性が秘められているのです。この問題に真摯に取り組むことができなければ、将来的に私たちは食事が手元に届かないという、非常に現実的な問題に直面するかもしれません。
取材担当者(石嵜)の感想
野澤社長の「とにかく現場へ足を運び、人の話を聞くこと」というメッセージは、現代を生きる私たち学生にとって非常に重い言葉でした。AIが普及する中で、つい情報収集をデジタルに頼りがちですが、現場でしか知り得ない「現実のギャップ」こそがビジネスチャンスの源泉であるというお話は、私の今後の行動指針を大きく変えるものだと感じました。
特に、高齢者介護業界が抱える課題の深さと、 それが同時に大きなビジネスチャンスでもあるという指摘は、将来のキャリアを考える上で新たな視点を与えてくれました。失敗を恐れずに挑戦すること、そして自分の目で見て肌で感じる経験の重要性を改めて認識しました。










