ケアゲート株式会社は、地域社会に密着し、高齢者やそのご家族の「いつまでも現役」を実現することを目指しています。
住み慣れた地域で最期まで安心して自分らしく生きられるよう、居宅介護支援、訪問看護、訪問介護、デイサービス、福祉用具レンタル販売、グループホーム、保育園、そして介護医療系人材派遣や警備事業など、多岐にわたるサービスを提供しています。特に在宅での医療・介護サービスに力を入れ、地域の医療機関とも連携しながら、お客様の在宅復帰や生活をサポートしています。
今回は、地域に根ざした多角的なサービス展開の背景、そして今後のビジョンについて、代表取締役社長・田邊様にじっくりとお話をお伺いしました。
<聞き手=丸山素輝(学生団体GOAT編集部)>
【田邊様のこれまでの経緯・背景】
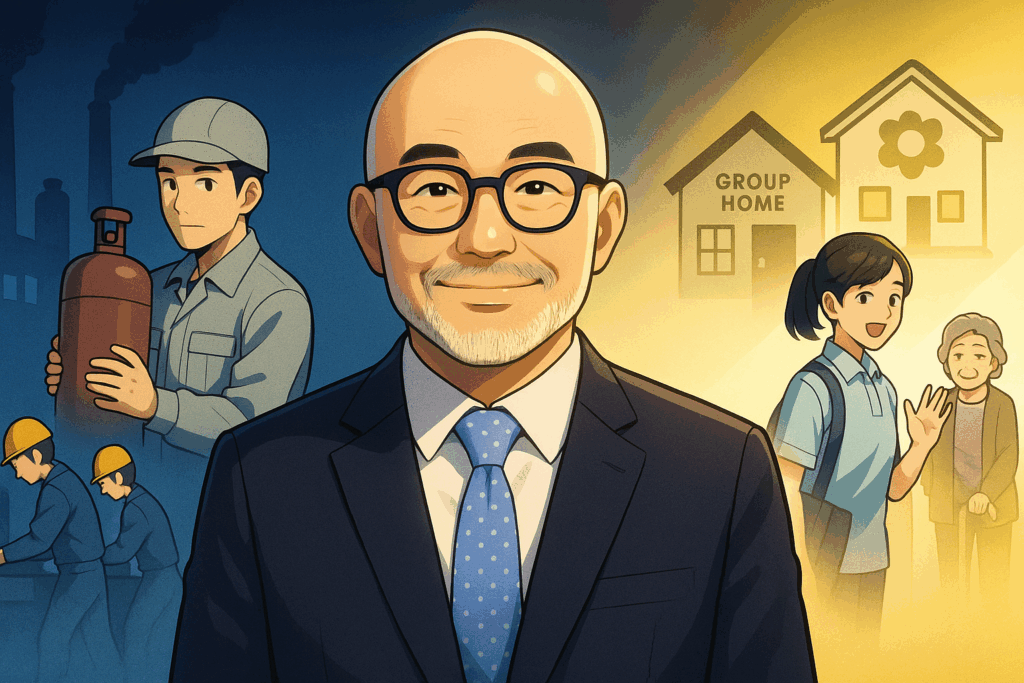
私は元々、ガスの会社を経営していました。工場にガスを販売する事業で、例えば酸素や窒素などを扱っていました。コンビニで売られている菓子パンが膨らんでいるのは窒素が入っているからで、酸化防止のためです。
当時は製造業のお客様が多かったのですが、より事業を伸ばすには何か他のことをやらなければと考え、多角化を模索しました。製造業と取引がある仕事でないと難しいだろうと考え、一生懸命探しましたが、何も見つかりませんでした。
そこで考え抜いた末に始めたのが、製造業への人材派遣でした。当時は人材派遣が非常に流行しており、例えば工場の流れ作業などにたくさんの派遣社員が入っていました。「ハケンの品格」というドラマがあったように、派遣が最も盛んな時代だったと思います。
製造業向けの人材派遣事業は比較的うまくいっていたのですが、リーマンショックが発生し、派遣切りが社会問題となりました。その影響で、製造業向け派遣の事業はあまりうまくいかなくなってしまいました。
これはまずい、何か他のことをやらなければならないと考えた時、福祉の派遣、つまり看護師や介護師の派遣を始めようと思いつきました。これが業態転換のきっかけです。人材派遣を経験する中で、介護保険を使った仕事、本当の介護の仕事をやりたいという気持ちが強まり、ケアゲートの介護事業を始めました。
現在の当社の事業の柱は、在宅医療介護の仕事と福祉系の人材派遣です。当時は介護について何も知りませんでした。元々知識があったわけでもなく、学生の頃には介護の仕事をするとは全く思っていませんでした。銀行に勤めていた頃も、まだ介護はそこまで世の中でブームになっていませんでした。
介護事業を始めるにあたり、中野区にあった小さな訪問介護の会社を買収しました。人材派遣事業を行っていた会社で、その訪問介護事業を買収したのがケアゲートの介護事業の始まりです。たまたま譲渡された小さな会社が中野区にあり、拠点となりました。
それから徐々に色々なところに支店を出すようになりました。しかし、在宅介護サービスは地域に密着することが重要で、例えば中野区の次にいきなり大阪に支店を出すとうまくいきません。なぜなら、人材採用と教育が非常に重要であり、地域の特性が大きいからです。そのため、中野区を本部として、近くの新宿など、人が共有しやすい地域に拠点を作っていきました。これが事業を広げていった経緯です。
取材担当者(丸山)の感想
田邊社長がガス事業から人材派遣、そして現在の介護・福祉事業へと至った経緯をお聞きしました。製造業の状況変化に対応するために多角化を模索し、リーマンショックを機に福祉分野へ転換されたというお話は、時代の変化を捉え事業を変化させていく経営のダイナミズムを感じさせました。
特に、介護については全くの未経験からスタートし、買収によって参入されたという点が印象的でした。

【田邊様が大切にしていること】
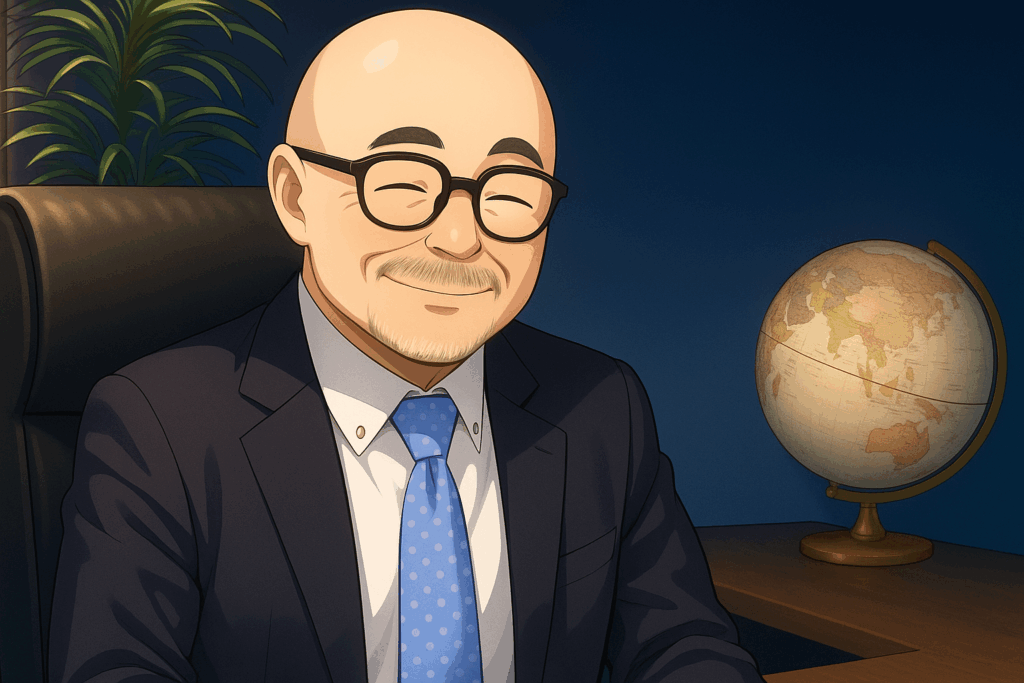
経営者という仕事は、人にもよりますが、それほど儲かる仕事ではないと私は思っています。事業、特に実業をやるということは、それほど簡単に儲けられることではありません。例えば土地を転がすような投資であれば大きなお金が入ってくるかもしれませんが、実業は人を使って商品やサービスを提供することで収益を得ていくものです。
金儲けだけを目的として事業を始めると、おそらく続きません。やはり「志」が大切だと考えます。例えば、従業員をたくさん雇用して彼らを幸せにしようとか、介護事業であれば、お客様を幸せにしよう、本当に困っている人を助けたいという強い思い、志を持っていないと、特に介護のような利益率が決まっている事業を続けるのは難しいでしょう。目的がなければできない仕事です。
最近はM&Aが流行していますが、もちろん後継者不在で事業を譲渡せざるを得ないケースもあります。しかし、会社が少し儲かったから売ってしまおうと考える人もいるのは事実です。個人的にはそのような考えは好きではありません。現状後継者はいませんが、75歳まで事業を続けようと思っています。
しかし、そこまで毎日、毎年続けるためには、従業員やお客様を幸せにしようという信念がなければできないと考えています。
そして、経営者としてその仕事自体が面白いと思えるかどうかも重要です。私が一番初めに小さな会社を買収した時、介護の仕事はあまり利益が出ないし、従業員も辞めてしまうし、人間関係も複雑で、「やるんじゃなかった」と思った時期がありました。しかし、事業を続けていくうちに、優秀な人財と出会えたり、お客様が喜んでくれる姿を見たりすると、「やっていて良かったな」とだんだん思えるようになってきたのです。
取材担当者(丸山)の感想
経営者として大切にされていることが「志」であり、従業員やお客様の幸せを追求することだというお話は、単に利益を追求するだけではない、実業家としての深い理念を感じました。
特に、介護事業を始めた当初は大変さも感じていたが、お客様や人材との出会いを通して面白さを見出していったというお話は、仕事のやりがいの重要性を示唆しており、学ぶべき点が多いと感じました。

【ケアゲート株式会社の事業・業界について】
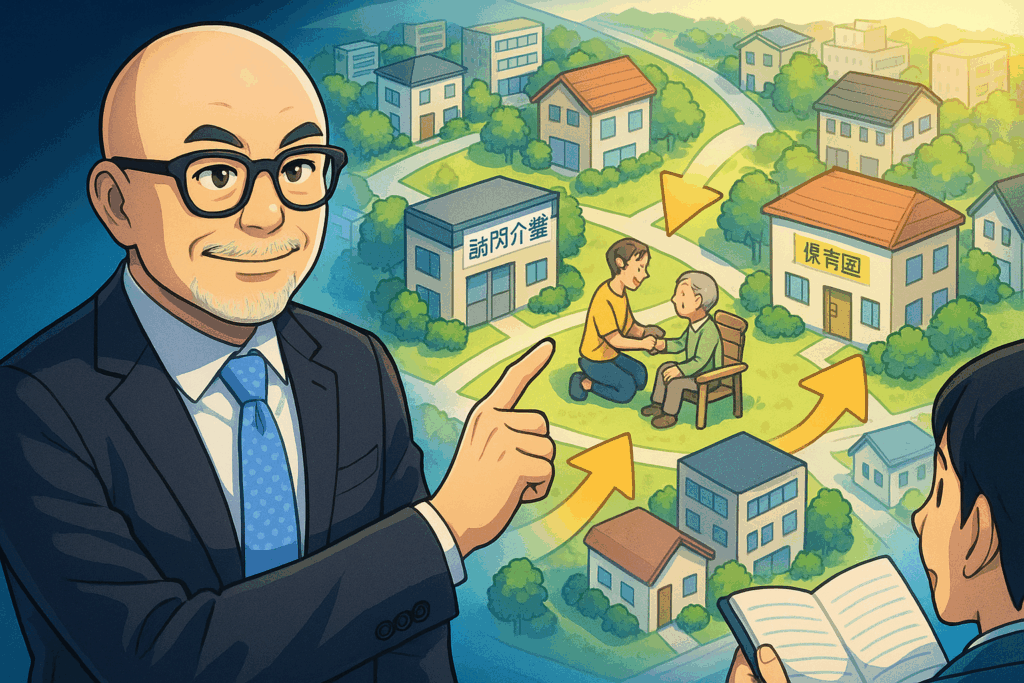
当社の事業は、主に介護・福祉・看護のサービス提供と介護・福祉人材派遣の二本柱です。施設の中でサービスをするのではなく、看護師や介護士がお客様の自宅に訪問してサービスを提供する、在宅看護・介護が中心です。法的には人材派遣とは異なりますが、全体としては人を介したサービス、人材サービスと言えます。
日本では、国の制度として、施設に通うのではなく、ご利用者様が住み慣れた自宅で介護や看護のサービスを受けられるようにしていこうという流れがあります。国は病院の数を減らしており、将来的に介護が必要になる方を考えると、施設だけでは受けきれません。
また、国は地域包括ケアシステムという、自宅で介護を受け、最期まで自宅で見送れるようなシステムを目指していることが見受けられます。これはオランダやヨーロッパから取り入れた制度ですが、向こうの国は家が広いのに比べて、日本の住宅事情は異なります。しかし、そうは言っても、今後は在宅介護・看護がさらに重要になり、マーケットとしてもまだまだ成長産業であると考えています。
高齢化が進み、ご利用者様の世代が増える中で、産業としては間違いなく広がっていきますが、働く側の「人財」が圧倒的に足りていません。今でも全く足りていない状況です。人を募集することもそうですが、採用した人財を技術的にも人間的にもきちんと教育していくことが非常に重要です。介護の現場では、残念ながらご利用者様のお金が盗まれるといったニュースも耳にします。
この人材不足に対応するため、経験者だけでなく、未経験や新卒の日本人財にも介護の仕事に挑戦してほしいと考えています。同時に、海外からの人材を積極的に受け入れていく必要があります。現在、ベトナム、スリランカ、カンボジア、ミャンマーなどから来ている従業員がいますが、彼らは勤勉に働く優秀な方が多いです。彼らはそれなりの志を持って日本に来ているからです。一方で、日本人の中途採用では、あまり質の良くない人に出会うことが多いという現実もあります。
当社の強みについてですが、採用力で言えば当社より力のある会社はあります。しかし、在宅介護の仕事は、大手も参入していますが、施設の運営を主体として訪問サービスを行うパターンが多く、在宅中心で事業展開しているのは中小企業が多いのが現状です。
私はこの仕事は中小企業がやるべき仕事だと考えています。強みを作るには、地域にどれだけ根付くか。役所や政治との連携も含めて、地域に密着していくことが重要だと考えてます。
もう一つの強みは、社員の定着化です。当社の定着率は高まっています。社員を定着させるためには、共通の価値観を作ることが不可欠です。当社にはフィロソフィーを記載した手帳があり、毎朝唱和するなどして価値観の共有を図っています。
また、良いリーダーシップを持った人間を育てていくことも重要です。これらの取り組みがある程度できていることが、当社の強みではないかと考えています。お金を使ってどんどん採用しても、すぐに辞めてしまっては意味がありません。
在宅介護は施設のような形のあるものではありません。人が働き、人に仕事をしてもらっています。人が相手の仕事だからこそ、マネジメント、良いチームワーク、良い会社の文化作りが非常に大切になります。価値観に共感してくれる人が残り、そうでない人は去っていく、というサイクルがある程度回っています。
ラーメン屋でも、箱だけ揃っていても、良いリーダーシップを取れる人間がいないと繁盛しません。人を育て、共感してもらい、共に成長していくことをやり続けることが、事業の継続には不可欠であり、それができていることが当社の強みだと感じています。
過去、私は急成長を目指して都内にどんどん事業所を出し、人材を大量に採用した時期がありました。しかし、結果として従業員との関係が悪くなったり、多くの事業所を閉鎖することになりました。その原因を考えた時、マネジメントがしっかりしていなかったこと、私と価値観を共有できる人財が不足していたことに気づきました。
そのため、時間はかかりますが、今は人をじっくり育てながら、堅実に事業を拡大していく方針です。急成長している同業他社もありますが、私はそのようなやり方は向いていないと考えています。基盤をしっかり固め、人材の教育を丁寧に行うことが、長期的な強みにつながると信じています。
取材担当者(丸山)の感想
日本の高齢化社会が進む中で、在宅介護・看護サービスの需要が高まっていること、そしてそれに対する人財不足が深刻な課題となっている状況を理解できました。
外国人財の活用や、その人財の教育・定着に力を入れている点、そして地域密着と共通の価値観作りが会社の強みであるというお話は、介護業界特有の難しさや、それを乗り越えるための経営戦略を知る上で非常に学びになりました。過去の急拡大での失敗から学び、堅実な経営を目指されている姿勢にも感銘を受けました。

【ケアゲート株式会社の今後の展望】
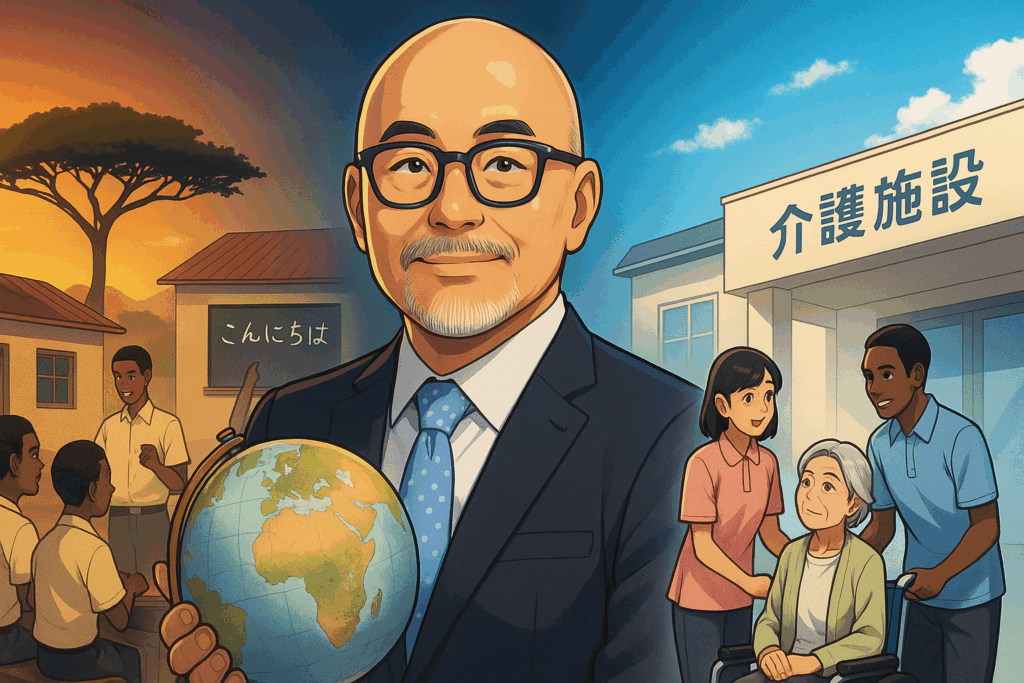
今後の展望としては、現場、特に介護の現場での深刻な人財不足に強い危機感を持っています。在宅サービスは人が命ですから、人財確保は最重要課題です。もちろん採用活動は行いますが、採用したいと言っているだけでは実現しません。
実行するためには、未経験者や新卒を含む日本人にこの業界に挑戦してほしいと働きかけると共に、海外からも多くの人に日本に来て、介護の現場を支えてほしいと考えています。
かつては、外国人を安く雇用できると考えている人もいましたが、今は全く異なります。日本人と同等な待遇、同等な評価をしていかなければ、海外から来てくれた人も満足せず、会社に定着しません。当社では、日本人と同じような待遇、同じような評価を行うようにしています。
会社の規模をただ拡大するのではなく、介護業界のために、高齢化社会のために、質の高い良い人財を育成し、輩出していくことが、私たちがやるべきことだと考えています。高齢化社会において良い人財は不可欠であり、人財の育成・教育は日本社会のためにもなります。この介護問題に対して、一人一人が関心を持つべきだと思います。
また、日本の介護保険制度についても、変えていかなければならないと考えています。現状では介護保険制度はだんだん削減されていく傾向にあります。介護業界も、政治に働きかけていかなければならない部分があります。介護職員の待遇改善なども必要だと考えています。
さらに、人財確保の一環として、ケニアに職業学校と日本語学校を作る構想を進めています。そこで介護人財を育成し、日本に来てもらうことを目指しています。アフリカ諸国は今、経済が発展しており、人口も増えて若い人が多いですが、一方で就職難という現実があります。
東アフリカの人々は英語圏に行くことが多いですが、日本を知ってもらい、日本で活躍してもらいたいと考えています。現在、ミャンマーやベトナムなどとは日本との間で労働協定があり、現地の試験を経て日本に来やすい制度が確立されていますが、アフリカ諸国とはまだそれがありません。
そのため、日本で働くには一度日本で試験を受け、帰国してビザを取得する必要があり、時間やコストがかかります。この制度を変えていくために、様々なロビー活動を行っています。
取材担当者(丸山)の感想
高齢化社会における介護人財不足という喫緊の課題に対し、日本人財の育成と並行して、海外からの人財確保を重要な柱とされていることがよく分かりました。特に、アフリカ・ケニアでの学校設立構想や、労働協定に関するロビー活動など、グローバルな視点と行動力には目を見張るものがありました。
外国人財を対等に評価するという考え方や、介護保険制度や待遇改善への問題意識も、業界全体をより良くしていこうという強い意志を感じさせるものでした。会社の規模拡大だけでなく、社会全体への貢献を目指すビジョンは非常に素晴らしいと思いました。

【学生へのメッセージ】
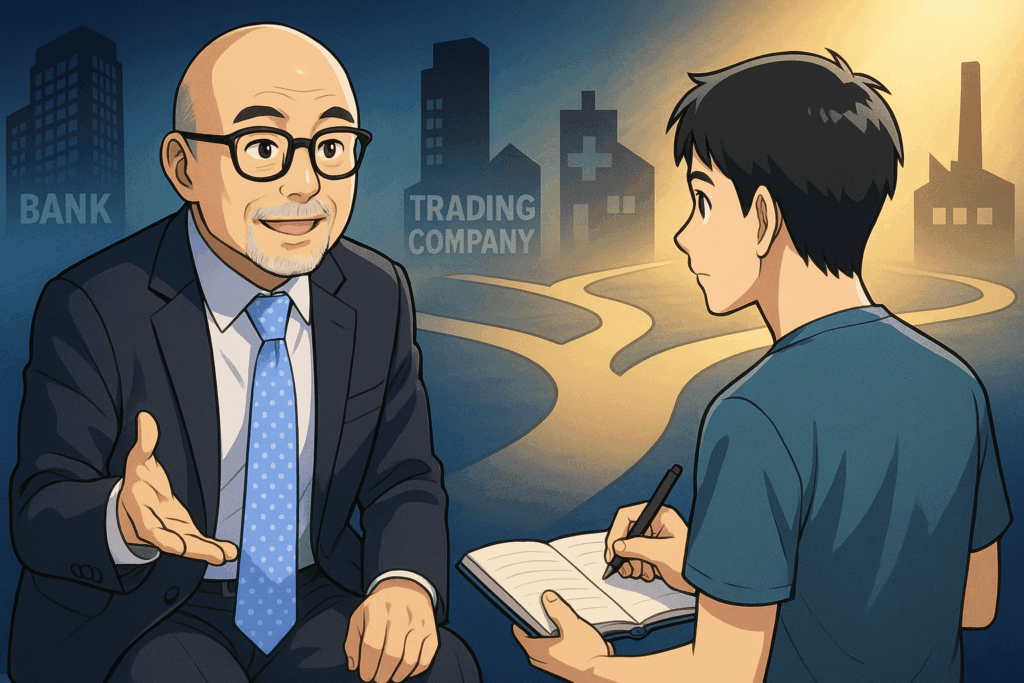
学生の皆さんには、ぜひ自分の興味のあることをアルバイトやインターンなどで体験してみることをお勧めします。そうすることで、自分が何に向いているのか、どんな仕事が自分に合っているのかを見つけることができると思います。多くの学生は、自分の適性を深く考えずに、銀行や商社といった有名企業に惹かれて就職活動をする傾向があるかもしれません。
しかし、それだけでは不十分だと思います。自分に向いている仕事は必ずあると思いますし、仕事はやはり楽しくないと続けられません。もちろん、お金も重要ですが、仕事の楽しさも同じくらい大切です。仕事には苦しいこともたくさんあります。
お客様に怒られたり、時には騙されたりすることもあるかもしれません。しかし、そういった経験も学びになり、結果として面白さにつながることもあります。
仕事は苦しいことばかりだからこそ、本当に自分が「これなら死んでもいい」と思えるくらいの仕事を見つけてほしいと考えています。そのためには、学生のうちに様々なことを経験しておくことが大切なのではないでしょうか。
私自身、大企業での勤務経験がありますが、大企業では必ずしも自分の好きな仕事ができるとは限りません。大企業は組織が大きく分業が進んでいるからです。例えば人材派遣の仕事でも、募集担当、営業担当、請求担当など細かく分かれています。
一方で、中小企業は人数が少ないため、一人の人が様々な役割をこなし、幅広い責任を持って仕事をしていかなければなりません。逆に言えば、中小企業の方が、向き不向きはありますが、自分が何に合っているのか、本当にやりたいことを見つけやすい環境にあると言えます。
取材担当(丸山)感想
学生に対して、自分の興味を追求し、多くの経験を積むことの重要性を強く語られていました。特に、大企業志向に偏らず、中小企業での多様な経験が自己理解を深めるのに役立つという視点は、就職活動を控えた学生にとって新たな気づきとなる深いアドバイスだと感じました。
「これなら死んでもいいと思える仕事を見つけてほしい」という言葉は、仕事への真摯な姿勢を示すものであり、心に響きました。










