大島グループは驚くほど多様な異業種の集まりであり、その多くがサービス業です。創業者から経営を引き継ぐ形でグループに参入した事業が多く、事業参入の判断基準は「その事業が地元に必要か」という一点にあり、特定の業種にこだわらないのは、特定の業種だけでは地域を元気にできないと考えているからです。引き継いだ事業を残していくためには変化が必要であり、それをどう変えていくか、アイデアを出し合っています。グループ各社には独立採算を求め、資金の融通は認めていません。
これは、一つの事業の破綻がグループ全体の連鎖倒産に繋がる事態を避けるためです。一方で、事業以外の部分では横の連携があり、幹部レベルの情報交換や社員間の交流イベントなどを実施しています。
グループ名に込めた思いとしては、「みんなでいきる」という言葉や、「地域の応援団」という新聞のキャッチフレーズがあり、地域とともに生き、応援団であり、応援される存在でありたいと考えています。事業展開のマーケットは地元が中心であり、ほとんどが地元での事業です。今回は、地域に必要とされる事業を見極め、多様な分野で挑戦を続ける大島グループの代表・大島誠様に、事業承継の哲学と変化を恐れない経営姿勢についてお話をお伺いしました。
<聞き手=丸山素輝(学生団体GOAT編集部)>
【大島様の今までの経緯・背景】
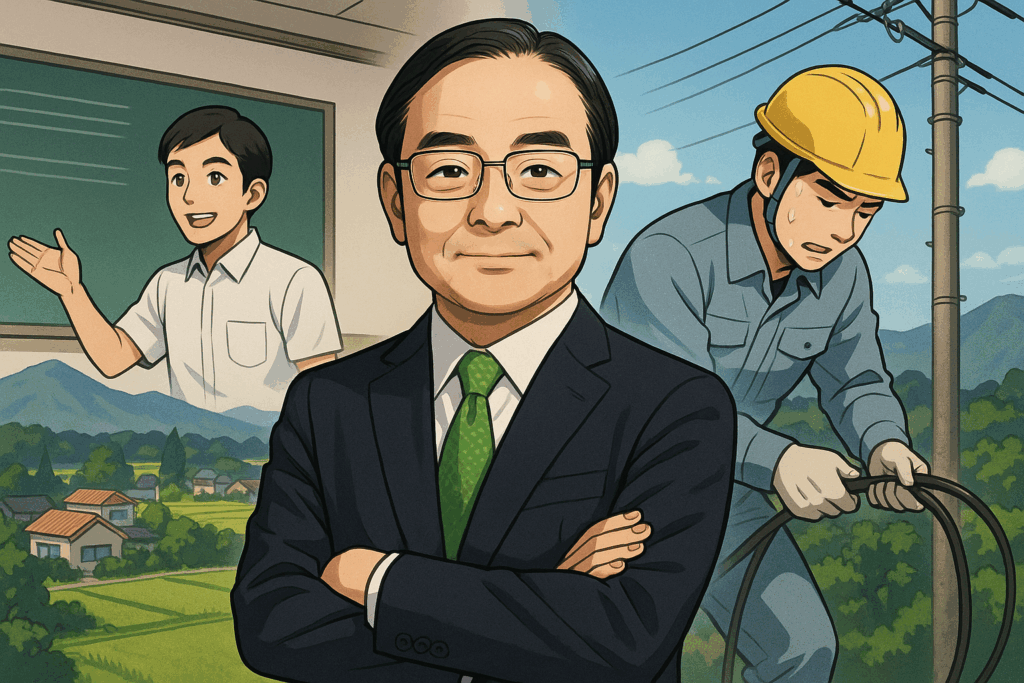
大学を卒業後、私は新潟県の中学校で教員をしていました。妻の実家が家業を営んでおり、結婚を機に学校を辞め、義父の家業に入ったのが今の仕事に就いたきっかけです。当時、義父は上越ケーブルビジョンを立ち上げた頃でした。
教員を辞めて家業に入ってから、約7年間はずっと現場でケーブルテレビの外線工事を担当していました。現場担当として、会社の一員として働いていました。社長になったのは35歳頃だったと思います。当時の大島グループは3社程度で、家族経営のような雰囲気でした。
その後、様々なきっかけがあり、他の会社の経営を引き受けたり、必要だと感じた会社を自ら立ち上げたりしていくうちに、今のグループの形になってきました。40歳頃からは、グループ全体のバランスを見ながらリーダーシップを取るようになりました。30代後半での社長就任は、オーナー企業の場合は特別早いとは言えないと考えています。|
取材担当者(丸山)の感想
中学校教員という安定した職業から、畑違いのケーブルテレビの外線工事という現場業務への転身は、キャリアを大きく変える勇気が必要だと感じました。
約7年間も現場で汗を流されたという経験は、今の経営にも活きているのだろうと想像します。家業を継ぐという選択肢の中で、現場から経営者へとステップアップされていった経緯は、様々な働き方を考える上で勉強になりました。

【大島グループの事業・業界について】
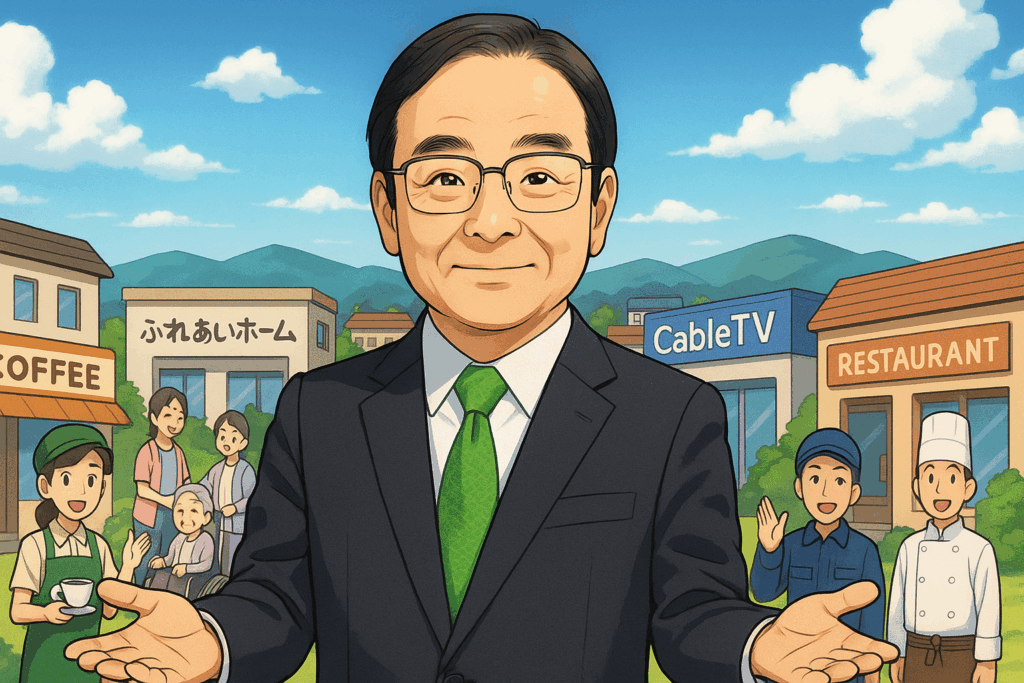
大島グループは驚くほど多様な異業種の集まりであり、その多くがサービス業です。創業者から経営を引き継ぐ形でグループに参入した事業が多く、事業参入を判断するポイントは「その事業が地元に必要か」という点です。
特定の業種にこだわらないのは、特定の業種だけでは地域が元気にならないと考えているからです。引き継いだ事業を残していくためには、時代に合わせて変わらなければならず、引き継いだものを先々へつないでいくために今どう変えるか、そこにアイデアを出し合っています。
グループ各社には独立採算を求めており、各社間での資金の融通は認めていません。これは、一つの事業が行き詰まることでグループ全体が連鎖倒産する事態を避けるためです。
一方、事業以外の部分での横の連携は重視しており、月に一度、各社の責任者が集まる「企業活力研究会」を開催し、情報交換や成績確認、全体に共通する話を行っています。また、社員やパート同士が交流できるイベントなども実施しています。
グループ全体のスローガンとも言える思いとして、グループ内の社会福祉法人名「みんなでいきる」や、地域の新聞紙「上越タイムス」のキャッチフレーズ「地域の応援団」があります。
私たちグループ自体が地域とともに「みんなでいきる」存在であり、「地域の応援団」でもあり、また地域からも応援される存在でありたいと考えています。マーケットは地元が中心であり、ほとんどが地元での事業です。
取材担当者(丸山)の感想
驚くほど多様な事業を展開されている中で、地域に必要かという独自の基準で事業を判断し、単なる営利目的だけでなく地域貢献を本業そのものと捉えている点が印象的でした。
各社の独立採算とグループ内の連携を両立されている体制も、多様な事業を運営する上での強みだと感じました。

【大島グループの今後の展望】
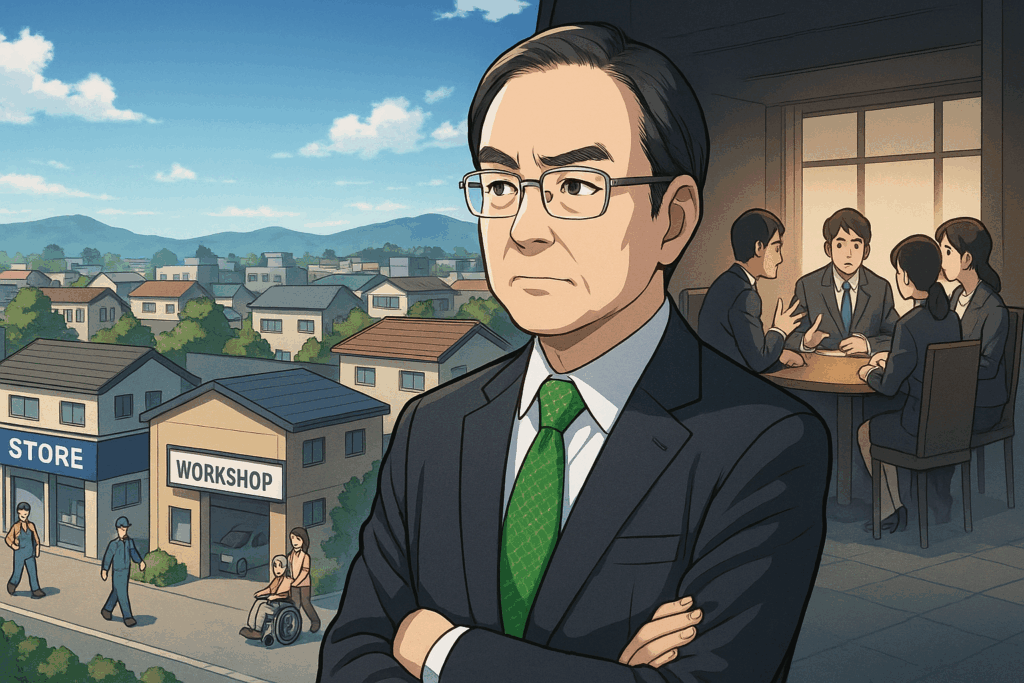
今後の企業の存続や拡大について、正解を持っている経営者はいないと考えます。特に地方においてはマーケットが小さく、さらに人口減少によってマーケットはどんどん小さくなっています。これは地方で事業を行う上で認識しておくべき現実です。
一方で、同じ職種でも後継者がいなくなり廃業する企業が多いという現状もあります。例えば自動車整備業など、どんどん廃業が進んでいます。そうすると、生き残っている企業にとっては、マーケットは小さくなっても業者の数が半分になれば、相対的にマーケットが2倍になったのと同じことになります。
この効果がいつまでも続くとは思いませんが、今後5年、10年程度の間であれば、地元マーケットの縮小の中でも生き残っていく一つの要因になるでしょう。
また、料亭のような事業では、地元マーケットだけでは事業継続が難しくなってきています。他の地域でも同様に料亭が減っているからといって、自分の料亭に来るわけではありません。そのため、地元だけではなく、外からお客様をどのように誘客するかが大きな課題となります。
オンラインでの情報拡散は皆が行っており、それだけで勝ち残れる時代は終わりつつあります。オンラインはきっかけにはなりますが、その後の口コミへと広がっていかないと効果は限定的だと感じてます。旅行会社へのアプローチなど様々な取り組みを行っています
が、集客に繋がるものは少ないと感じます。
そのため、地元のお客様に加え、飲食以外の売上を作ることも非常に重要だと考えています。例えばふるさと納税を活用して冷凍食品を開発したり、それがきっかけで実際に地域に足を運んでもらえるような関係を作ったりする、といったことの繰り返しです。何か一つの方法でうまくいく時代ではなく、様々な施策を同時に多方向に打っていく必要があります。
これからの経済の世界で生き延びていく鍵は、場所、つまり土地そのものにあると考えます。どれだけその土地らしい「らしさ」を発信できるかにかかっています。新幹線の駅ができて、どこの駅に降りても景色が一緒では意味がありません。その土地らしいものをどう表現できるかが非常に重要だと考えてます。
物理的な景観だけでなく、文化、歴史、人、食べ物など、様々な切り口でその土地の「らしさ」を出すことが大事です。違いを出すというよりは、「らしさ」を出すという表現の方が適切ですね。規模ではなく、いかに「らしさ」を魅力的に表現できるかにかかっていると感じます。
現在の日本は東京一極集中が進んでおり、経済論理的には効率が良いかもしれませんが、国のあり方としては非常に脆弱な形になっていると考えます。便利さや給料が良いという理由で東京に集中しますが、個人の便利さと国の将来の思考軸は全く異なると思います。自分の行動がこの国の未来にどのような影響を与えるのかを考えながら、仕事や働く場所を選ぶべきではないでしょうか。
上越市出身者として、上越らしさが表現できる会社でありたいと思っています。そして、日本中の地方都市でも、そういった「らしさ」を求めていく企業がどんどん表に出てきて、そこに地元出身者や地元以外の人たちが働けるようになっていったら良いなと考えています。
取材担当者(丸山)の感想
地方で事業を継続・発展させることの難しさと、それに立ち向かうための多角的な戦略について具体的に知ることができました。特に、マーケット縮小という現実の中で、競合の減少や「他がやらない分野」への着目、そして最も重要視されている「土地のらしさ」の発信という考え方は、地方で事業をするということを考える上で非常に学びになりました。
東京一極集中に対する危機感と、自分の行動が国の未来に与える影響を考えて働くことの重要性についての言葉は、まさに今、キャリアを考え始めている学生が心に留めるべきメッセージだと感じました。

【大島様から学生へのメッセージ】
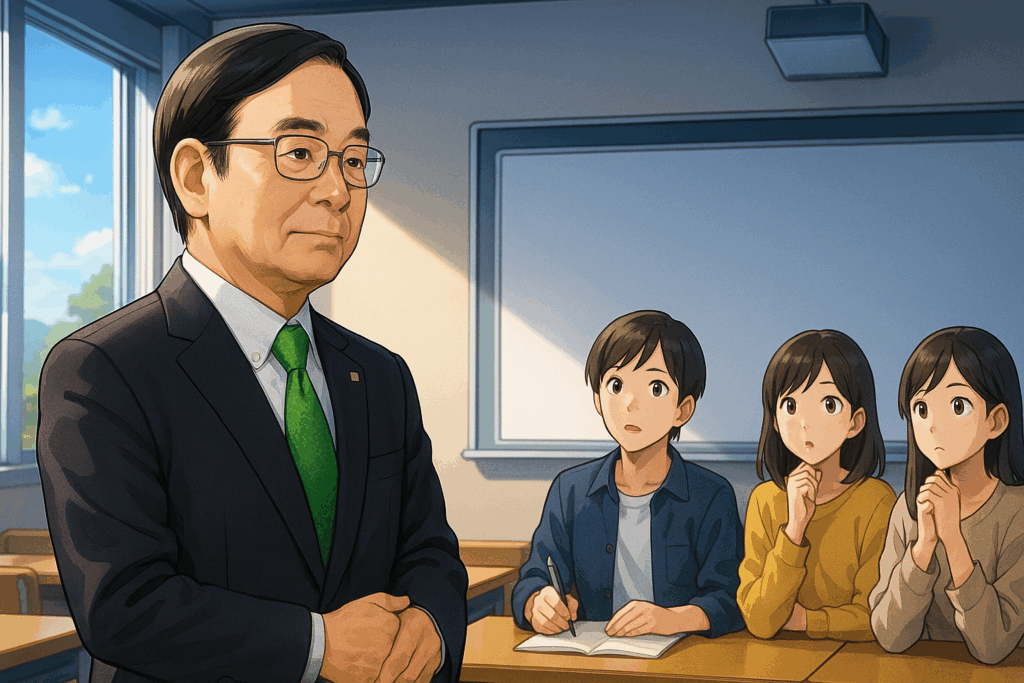
学生のうちにやっておいた方が良いこととしては、まず「勉強」をきちんと行うことが重要です。私たちは学生時代にあまり一生懸命勉強しなかった面がありますが、今の世の中で求められているビジネスは、専門性に裏打ちされた事業だと感じています。
法律のギリギリを攻めるような際どいビジネスは危険であり、お金を持つことがステータスとなるようなスタイルを目指すのでないならば、専門性は不可欠です。
大学で学んでいるのであれば、その学びが将来自分がイメージする事業に繋がっていくようなことではないと、大学での4年間は非常にもったいない時間になってしまいます。しっかりと専門知識や学びを深めることが、そこでしか勝負できない強みとなります。
また、「海外」も見た方が良いと思います。これからの時代、物事を動かすスケールは地球規模になるでしょう。世界中を回る必要はありませんが、海外という日本と違う環境に身を置いてみることは非常に大事な経験になるでしょう。
地方創生に貢献したいという学生も多いと聞きますが、「地方創生」という言葉を安易に使うべきではないと感じます。それは東京からの見方であるという面もあります。地方創生に貢献するためには、やはり「専門性」が不可欠です。
大学や専門学校で何を勉強し、何を身につけてきたかが重要になります。何の強みもないまま田舎に帰ってきても、単なる消費者として戻ってくるだけで、地域は困るでしょう。何か価値を生んでいくためには、地域が必要としている知識、技術、人脈、情報発信力などを身につける必要があります。
今、自分がいる場所で一生懸命生きることが大切です。例えば大阪にいるならば、まず大阪の良さを深く理解することです。それが地元に帰った時に、地元との違いや地元の良さを認識する力になります。
東京にいるなら東京で一生懸命生きることです。一生懸命生きる中で見えてくるものがたくさんあります。地元に帰ってきてくれるのは人口減少の中では嬉しいことですが、もし地方創生という切り口で戻ってくるのであれば、もっと覚悟を持って、今いる場所で結果を出すことを考えるべきです。今いる場所でできないことは、地元に帰ってもできません。
取材担当者(丸山)の感想
学生にとって耳の痛い厳しい現実も含めて、非常に率直で実践的なアドバイスをいただけたと感じています。特に「専門性の重要性」と「今いる場所で一生懸命生きること」というメッセージは、これから社会に出る上で、どこで働くか、どのように働くかを考える上で非常に重要だと感じました。
地方創生に対する鋭いご指摘も、言葉の表面だけでなくその本質を考えるきっかけとなりました。私自身も、今いる大阪で何を学び身につけられるのか、改めて考える必要があると気付かされました。










