アクト・玄々堂グループは、生活産業(製造、農業、物流)、医療健康(病院、健診センター)、福祉介護(介護施設)の3つの主軸事業を中心に多角的な経営を行うグループ企業です。大分県宇佐市に本社を置き、グループ全体で20社を経営しており、従業員数は1212名(2024年4月1日現在)。年商は116億円(2024年度現在)です。創業は1984年(有限会社花岡産業設立)で、2016年10月に株式会社アクト・玄々堂ホールディングスが設立されました。今回は、地域密着型で多角的な事業を展開する背景や、100年企業を目指す中で描く未来像について、代表取締役社長・西山様にじっくりとお話をお伺いしました。
<聞き手=丸山素輝(学生団体GOAT編集部)>
【西山様の今までの経緯・背景】
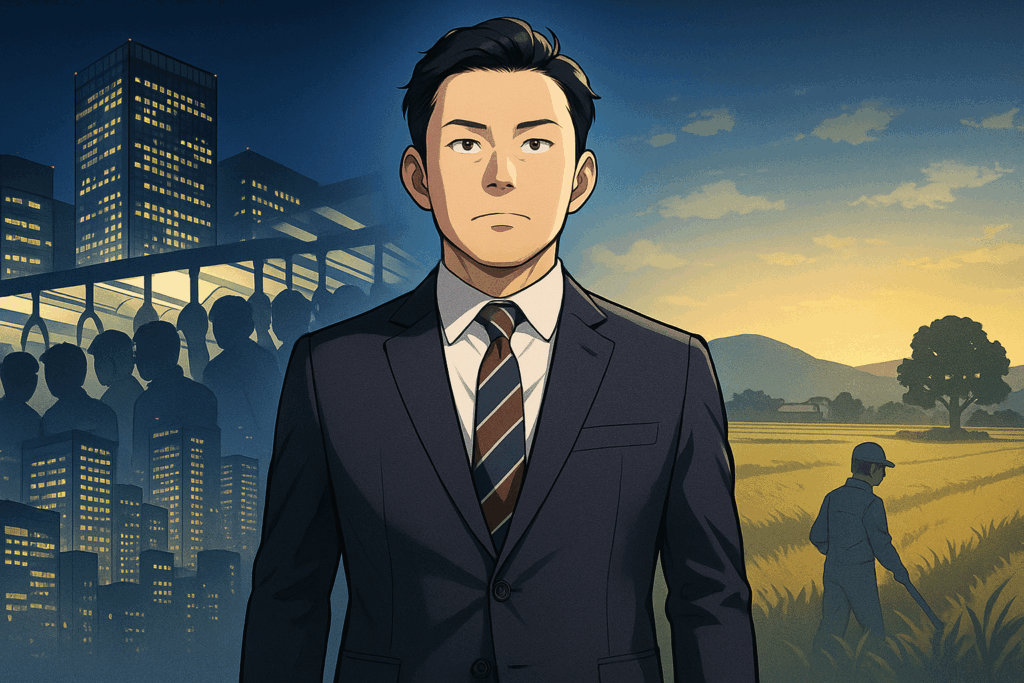
大学卒業後、すぐに大手上場企業に入社しました。前職では約6~7年間、営業を担当しました。元々、自分自身で起業したいという考えを持っていました。
大手企業に在籍している時に、現在の妻と結婚しました。その中で、妻の父がこの宇佐市、大分県内で事業を行っているという話を聞きました。義父から、今の会社を手伝ってほしいと言われたことが、入社するきっかけとなりました。
自分の起業したいという思いと、義父から手伝ってほしいという話がマッチしたため、それであればということで、大分の方に移住しました。こちらに来たのは、27歳か28歳ぐらいの時でした。当初はホールディングスとして取締役として入り、子会社の社長のような形で事業を任せてもらうことになりました。そこから3~4年後の31歳の時に、ホールディングス全体の社長に就任したという経緯です。
取材担当者(丸山)の感想
大学卒業後、一旦は東京の大手企業に就職された西山社長が、起業という目標を持ちながらも、ご家族とのご縁をきっかけに地元の事業承継を決断された経緯が印象的でした。それまでとは異なる環境に飛び込むこと、そして若くしてグループ全体の代表という重責を担うことには、想像以上の困難があったかと思います。
しかし、その決断力と、任された事業で経験を積み、最終的に代表に就任されたというお話からは、目標に向かって着実にステップを踏んでいく姿勢と、新しい環境での挑戦を恐れない強い意志を感じました。自身の人生をどう生きるのか、働く場所や業界の選択肢が多様にある現代において、決断の背景にある思いを聞くことは、自分自身のキャリアを考える上で多くの示唆を与えてくれると感じました。

【株式会社アクト・玄々堂ホールディングスの事業・業界について】
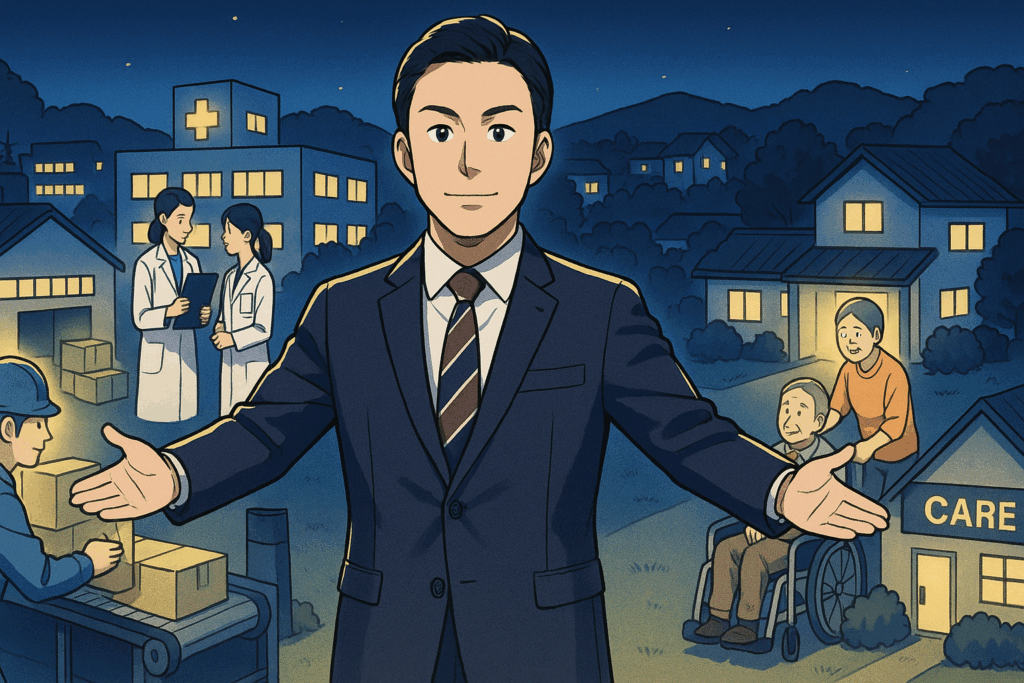
アクト・玄々堂グループは、主に生活産業、医療、介護の3つの柱で事業を展開しています。生活産業はいわゆる物づくりの産業で、医療は病院、そして3つ目が介護です。この3つが事業の大きな柱となっています。グループ全体では20社を経営しており、介護関連の施設は有料老人ホーム・特別養護老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅をはじめとした13の事業所を運営しております。
経営体制としては、基本的に各事業会社に責任者や社長がいます。彼らとコミュニケーションを取りながら、経営上の課題を抽出し、改善に向けて協議を進めていくという形で関わっています。現場に深く関わるというよりは、全体的な経営に携わっていると言えます。
経営における課題はたくさんありますが、その中でも最も大きな問題は「人」です。大分県、特に宇佐市のような地域では、人口が少なく、優秀な人材を集めることが難しいという現状があります。別府市や大分市にはまだ多くの人がいますが、それでも人手不足と言われており、宇佐市ではさらに状況が厳しいと言えます。グループ全体で1000名以上の従業員がいますが、やはり人材の確保は大きな課題です。新卒採用については、医療分野では数名採用することがありますが、介護や生活産業では毎年決まった人数を採用するということは行っていません。補充が必要な時に募集するという形です。
アクト・玄々堂グループの強みは、この事業の多角性にあると考えています。子会社ごとに強みはありますが、グループ全体で見ると、事業が非常に多岐にわたっています。例えば、コロナ禍のように医療や介護分野で入院患者や入居者が減少し、厳しい時期があったとしても、物づくりや農業の事業は一定の需要が確保できていました。このように、良い時もあれば厳しい時もある中で、両側面がしっかりあることで、グループ全体としては経営が安定し、どのような不況や好況の時代でもうまく乗り切ることができるのが強みです。これは、リスク分散ができていることにつながると言えます。
取材担当者(丸山)の感想
多角的な事業展開がグループ全体の安定経営につながっているというお話は、企業の強みを考える上で非常に勉強になりました。特に、リスク分散の重要性を実際のコロナ禍での経験と結びつけて説明していただいたことで、その効果を具体的に理解することができました。
一方で、地域に根差しているからこその人材不足という課題があることを率直に話してくださり、事業規模が大きいからこそ抱える問題があるのだと認識しました。地域創生に関心のある私にとって、地方企業がどのように人材を確保し、成長を目指していくのかという点は、今後の学びの大きなテーマになると感じています。

【西山様から学生へのメッセージ】
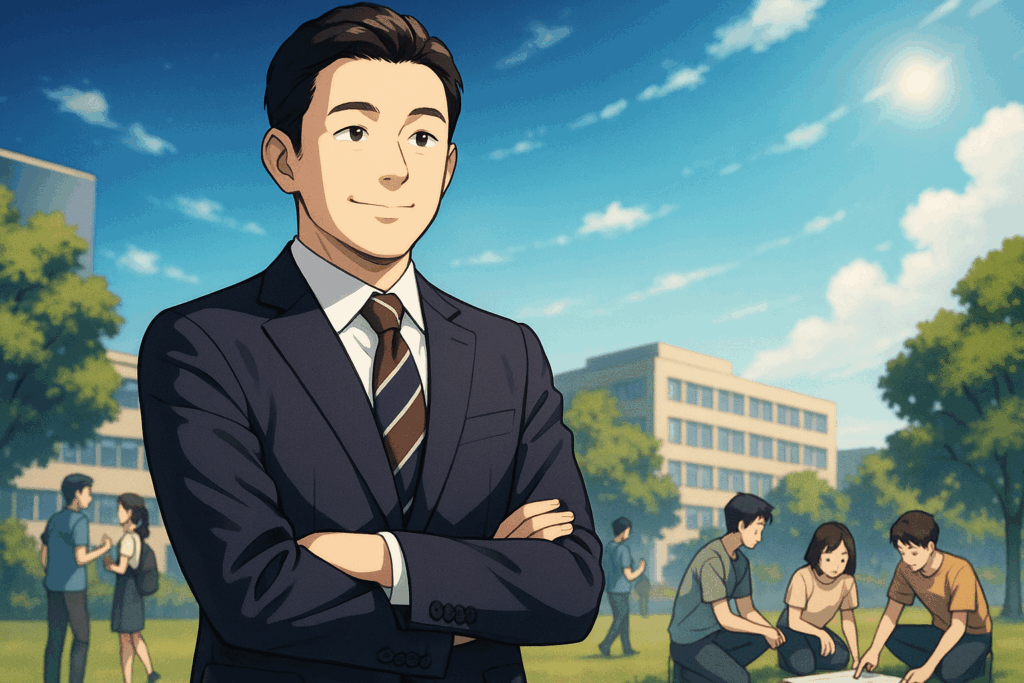
学生のうちにやっておいた方がいいこととしては、社会の疑似体験のようなことを一つ何かやっておくと非常に良いと考えています。例えば、リーダーシップを取ることが一つ挙げられます。
社会に出てから、仕事に必要な知識やスキルを勉強して学ぶことは、会社に入った後でもいくらでも努力すれば追いつくことができます。先輩や上司と同じレベルになるのも、慣れればすぐです。しかし、人とのコミュニケーションや、組織を率いるといった対外的なコミュニケーションの経験は、実社会においてはなかなかチャンスが得られにくいものです。
そのため、学生時代に、皆さんが所属しているような組織の中で、人をまとめて何かプロジェクトを進めてみるなど、そのような経験を積むことが重要だと考えます。そうすることで、社会に出た時に即戦力として活躍できる力が身につくのではないかと思います。
取材担当者(丸山)の感想
学生時代に身につけるべき力について、勉強や専門知識だけでなく、人間関係や組織を動かす経験の重要性を強調されている点が心に響きました。大学で学ぶこと、サークル活動やプロジェクトで経験を積むこと、それぞれの意味や価値を改めて認識しました。
特に、実社会で得にくい「組織を率いる経験」を学生のうちに意識的に行うべきだというアドバイスは、具体的な行動指針として非常に参考になります。私自身も、所属している団体で様々な活動に取り組んでいますが、今回のメッセージを聞いて、単に活動するだけでなく、そこからどのような学びを得られるかをより深く考える必要があると感じました。将来起業を目指す仲間が多い中で、このメッセージを共有し、皆で実践していきたいと思います。

【株式会社アクト・玄々堂ホールディングスの今後の展望】
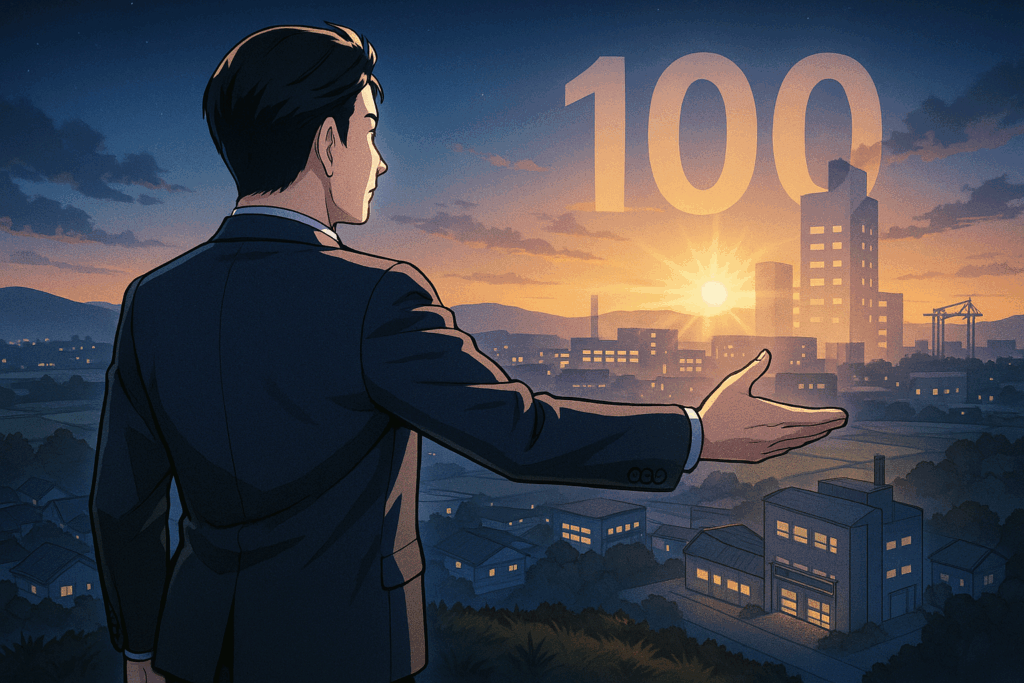
直近の目標としては、現在の年商115億円から200億円を目指して事業を進めています。企業として、やはり「人」の問題が大きな課題であるため、魅力ある会社にして、人が集まる会社にしていくことが、直近の大きな目標と言えます。
売上200億円を達成するためには、現状の1200名程度の従業員数から、単純計算では倍の2000名程度が必要になると考えています。医療や介護、物づくりといった事業は、人があって初めて成り立つ事業だからです。しかし、85億円といった大きな売上をゼロから作り出すのは非常に困難です。
そのため、今後はM&Aも含めて事業拡大を進めていく中で、目標を達成していきたいと考えています。私たちがやっている事業は生活に根差しているものであり、IT関連や人材系のように急激に伸びる性質のものではありません。やはりコツコツと積み重ねていかないと、成長は難しいと感じています。
100年企業を目指すというのは、企業として地盤を安定させ、人も物も持続的に回るような仕組みを作るということがベースになります。その仕組みを作りながら、200億円という目標、そして100年企業 を掲げて事業を進めていきたいと考えています。事業内容は今後も現在の主軸である医療や介護、物づくりを続けていくことになると思いますが、これらの事業は法律に定められている部分も多く、大きく新しいことをするのは難しい側面もあります。
しかし、関連する事業や、医療法人ではできないような新たな事業、物づくり分野での良い機会があれば、工場取得なども含めて積極的に取り組んでいきたいと考えています。ゼロから何かを始めるというよりは、既存事業とのシナジー効果が高いものを展開していくことが、200億円達成にもつながると考えています。今後は大分県だけでなく、西日本エリアでも事業を展開できる場所を探し、アグレッシブに進めていきたいと考えています。
取材担当者(丸山)の感想
200億円という目標設定や、それを達成するためのM&Aといった具体的な戦略を聞くことができ、非常に刺激を受けました。目標達成のために必要な「人」の課題を明確に認識されている点、そしてそれを解決するために魅力ある会社を目指すという考えに共感しました。
また、派手な急成長ではなく、生活に根差した事業だからこそコツコツと地道に取り組むことの重要性、そして100年企業という長期的な視点で地盤を固めることを重視されている点は、これから自分のキャリアを築いていく上で参考にすべき考え方だと感じました。今後の事業展開や、西日本エリアへの拡大という展望を聞き、地域に根差しつつも常に挑戦し続ける姿勢が伝わってきて、今後のアクト・玄々堂グループの発展がますます楽しみになりました。










