株式会社まるよし様は、1961年(昭和36年)に三重県松阪市で創業した松阪牛専門の精肉店とレストランです。世界に誇るブランド牛である松阪牛を「高値の花」にせず、誰もが楽しめる身近な存在にすることを目指してきました。自社牧場での一貫した肥育から精肉・レストラン運営までを手掛け、お客様に最高の松阪牛を提供し続ける企業として、日々努力を重ねています。本記事では、若くして社長に就任した私、亀田へのインタビューを通じ、その経営哲学と業界への挑戦、そして若手への期待をお話しします。今回は、松阪牛の伝統を守りながらも新しい挑戦を続ける背景、そして未来を担う世代への思いについて、代表取締役社長・亀田様にじっくりとお話を伺いました。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【社長就任までの道のり】
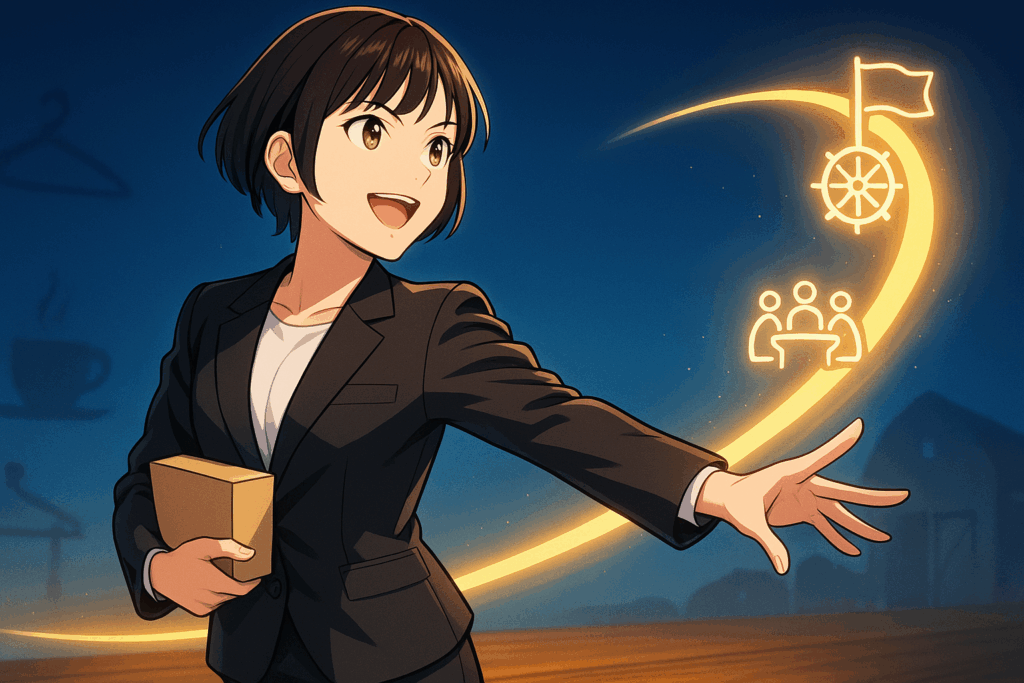
私は去年の10月に松阪まるよしの代表取締役社長に就任しました。入社時は社員として主に品質管理と商品開発、自社商品のパッケージデザインやレシピ開発、そしてパッケージングなどの業務を担当していました。以降は役員として2年間務め、現在に至ります。弊社は元々私の実家が経営する会社で、現会長である父からの世代交代という形で家業に戻り、約7年前に入社しました。
~代表取締役就任までの流れ~
2018年に入社し品質管理と商品開発
2021年に常務取締役に就任
2024年10月に代表取締役社長に就任
弊社に入社する前は、県外で様々な仕事をしていました。具体的には、カフェの社員としてお客様への接客や店舗運営に携わった経験があります。その後はアパレル業界に転身し、新規店舗の立ち上げや異動に伴うオープニングスタッフの準備なども担当しました。これらの異業種での経験は、私にとって非常に貴重な財産となり、現在の経営においても多大な影響を与えています。お客様が何を求めているのかという顧客視点、チームをまとめ上げるリーダーシップ、そして新しいプロジェクトを円滑に進めるための実践的なスキルは、これらの経験を通して培われたと強く感じています。
私のこのようなキャリアパスは、一見すると現在の仕事とは関連性が薄いように見えるかもしれません。しかし、多様な業界で得た経験は、伝統ある企業において新しい価値を創造する上で、固定観念に囚われない柔軟な視点をもたらしてくれると信じています。様々な背景を持つことで、変化の激しい現代において、より多角的なアプローチで経営を推進できると私は考えています。
取材担当者(高橋)の感想
異業種での経験を経て家業を継ぎ、リーダーシップを発揮されている亀田社長の姿に感銘を受けました。幅広いバックグラウンドを持つことで、従来のやり方に囚われない柔軟な発想が生まれることを実感しました。自身のキャリアを考える上で、多様な挑戦の重要性を改めて感じさせてくれるお話です 。

【会社を変革するリーダーシップ】
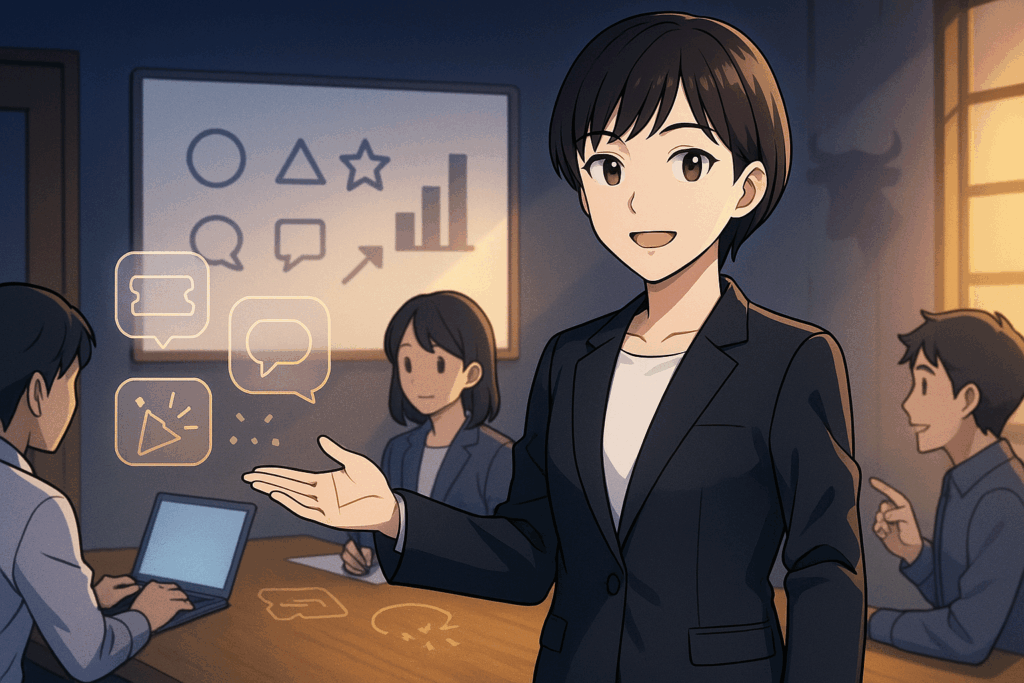
社長に就任してから、私が特に注力しているのは、松阪牛に対する「高い」というイメージを払拭し、より多くのお客様に気軽に味わってもらえるようにすることです。弊社の元来の経営理念である「名産松阪牛を高嶺の花にせず、美味しく良いものを少しでもお値打ちに」という精神を改めて深く認識し、お客様目線での取り組みを強化しています。例えば、会社の魅力や雰囲気を伝えるための情報発信を積極的に行い、クーポン発行やイベント企画を通じてお客様との接点を拡大する努力を続けています。
この変革の根底には、私一人の力ではなく、従業員全員が同じ目標を共有し、協力し合う「チームワーク」が不可欠だと私は考えています。新しい企画や商品開発を進める際には、本部の企画担当者だけでなく、現場の従業員も主体的に議論に参加してもらっています。頻繁に会議を開き、お客様のニーズに応じた魅力的な提案を皆で生み出すことを重視しています。
具体的な企画推進においては、「誰が」「いつ」「なぜ」「誰に向けて」行うのかを徹底的に話し合い、全員が納得した上で行動に移ることを徹底しています。私は日頃から会社の将来像を社員と共有し、対話を通じて社員が自ら考え、主体的に行動できるような組織文化を醸成するよう努めています。松阪まるよしは、単に伝統を守るだけでなく、柔軟な発想と強いリーダーシップ、そして従業員との密な連携によって、時代に合わせた進化を続けていくことが重要だと私は考えています。
取材担当者(高橋)の感想
松阪牛の「高級」イメージを「身近」に変えようとする亀田社長の顧客志向の姿勢に感銘を受けました 。特に、従業員の主体的な企画参加を促し、対話を通じて全員が納得するまで方針を練り上げるリーダーシップは、現代の企業が成長し続ける上で不可欠な要素だと感じます 。学生が企業を選ぶ際、このような「全員参加型」の組織文化があるかを重視するべきだと改めて学びました 。

【業界の現状と未来への挑戦】
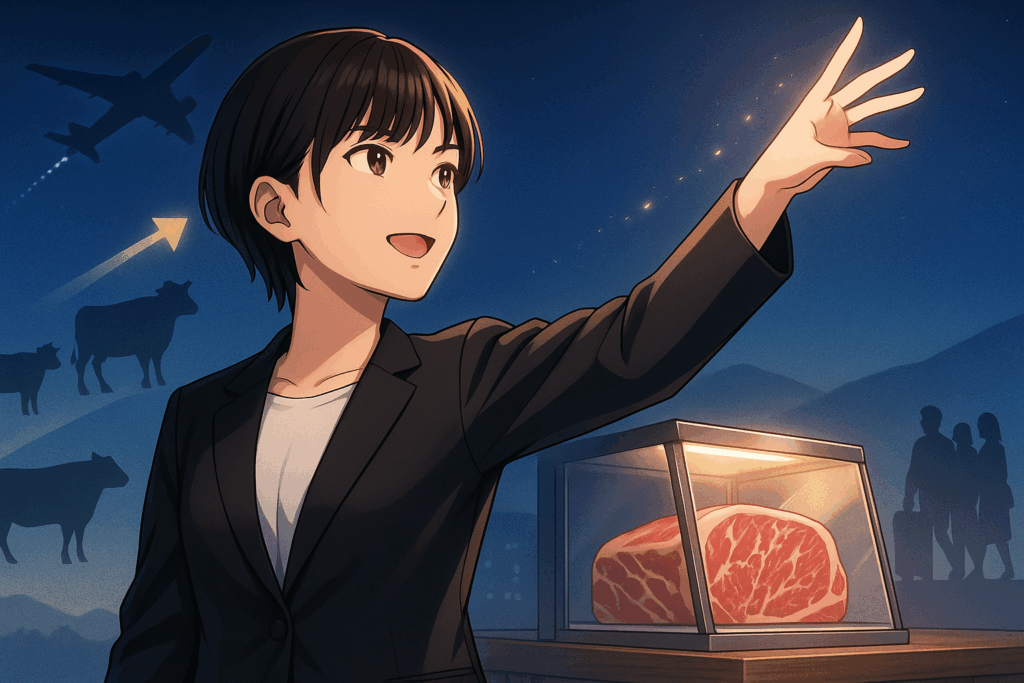
食肉業界、特に牛肉業界は現在、多くの課題に直面しています。原材料費の高騰は継続しており、お客様の節約志向も強まっています。さらに、子牛の頭数減少、価格高騰という構造的な問題も抱えています。政府は和牛の輸出促進のために早期出荷を推奨していますが、私はこれが和牛本来の「質」を損ないかねないと懸念しています。短期で出荷されることで、肉の味が大雑把になったり、肉質が硬くなったりする可能性があります。
松阪まるよしでは、単に利益を追求するだけでなく、松阪牛の品質維持を最優先しています。最高の肉質とは何かを常に追求し、BMS(脂肪交雑基準)で8番から10番という、最もバランスが良く美味しいとされるランクを目指しています。そのために、牧場のメンバーと密に連携を取りながら、30ヶ月から33ヶ月という長期肥育にこだわり、一頭一頭丁寧に育て上げています。これは、短期出荷を推奨する国の方向性とは異なるかもしれませんが、私たちが守りたい松阪牛の真の価値だと信じています。
このような厳しい市場環境の中、私たちは未来に向けた挑戦を続けています。現在、海外への取り組みを模索している段階です。さらに、地元三重県の経済発展にも貢献したいという強い思いがあります。三重県は全国的に見てもインバウンド誘致が遅れている現状があると認識しています。そこで、私たちは海外の旅行代理店を招いたファムトリップなどを実施し、松阪牛の魅力だけでなく、三重県の豊かな観光資源を世界に発信しています。最終的には、海外のお客様に直接松阪の地を訪れてもらい、地域全体の経済発展に繋げたいと考えています。私たちが地域に根差した企業として、自社の利益だけでなく、地域の活性化にも貢献することが重要だと強く感じています。
取材担当者(高橋)の感想
食肉業界の課題、特に品質と効率性のジレンマは深く考えさせられるものでした 。国の方針とは一線を画してでも品質を追求する松阪まるよし様の姿勢は、真のブランド価値を守るための強い信念を感じさせます 。また、地域貢献としてインバウンド誘致に取り組む広範な視点も印象的で、学生が仕事選びで社会貢献性を考える重要性を学びました 。

【20代へのメッセージとキャリア形成】
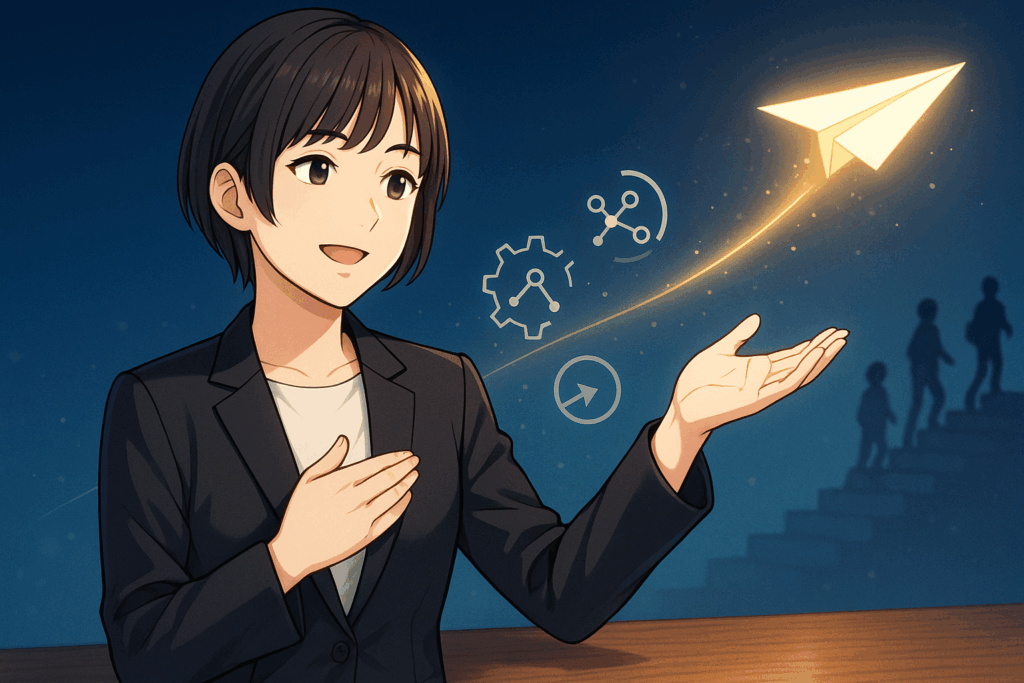
20代の若い皆さんには、まず自身の「得意なこと」を徹底的に伸ばしてほしいと強く思っています。入社時に希望する部署で専門性を磨き、その分野で誰にも負けないスキルを身につけることが、皆さん自身の「存在価値」を高め、会社にとって不可欠な人材になるために重要だと私は考えています。得意分野を極めることで、自分にしかできない仕事、自分だからこそ任せてもらえる仕事が必ず出てきます。
しかし、一つの分野に留まるだけでなく、他部署との連携を通じて視野を広げる「横串」の視点も、同時に不可欠です。例えば、商品開発の担当者が精肉業務やレストラン運営にも関わることで、お客様の視点から新たな発想や解決策が生まれることがあります。会社は一人ひとりのプロフェッショナルが集まったチームです。部署の垣根を越えて協力し、皆で楽しく仕事をしていくことが、個人の成長に繋がり、ひいては会社全体の発展に繋がると私は考えています。
さらに、若い皆さんには「言われたことだけをやる」のではなく、「自分で考えて動く」主体性を強く求めています。新しいことに挑戦する際、失敗を恐れる必要はありません。もしうまくいかなかったとしても、「何が原因だったのか」「自分に何ができたのか」と深く内省することが、本当の成長に繋がると私は信じています。私自身も、社員に一方的に指示を出すのではなく、会社のビジョンや目標を日頃から共有し、対話を通じて社員が自ら考え、行動できるような組織文化を醸成するよう努めています。この専門性と協調性、そして主体性を兼ね備えた人材こそが、松阪まるよしが未来を託し、共に会社を成長させていきたいと願う若手像です。
取材担当者(高橋)の感想
亀田社長の20代へのアドバイスは、非常に実践的で心に響くものでした 。得意分野の深化と他部署連携による視野拡大のバランスは、現代のキャリア形成において非常に重要です 。特に、「自分で考えて動く」主体性や、失敗からの深い内省を求める姿勢は、Z世代である私たちが意識すべき行動指針だと痛感しました [37, 38, 前回の出力より]。社員が自律的に成長できるような対話型の教育方針は、理想的な職場環境を求める学生にとって大きな魅力となるでしょう 。










