有限会社こじまは、長崎を拠点に「角煮家こじま」で角煮製品を、「割烹こじま」で日本料理を提供する企業です。直営工場を長崎市田中町に持ち商品製造をすることで、地域に根差し、働きやすい環境づくりと社会貢献を目指しています。今回は、長崎の地で角煮製品と日本料理の両軸を展開し、地域に根ざしたものづくりと雇用創出に取り組む有限会社こじまの歩み、そしてこれからの展望について、代表の廣井 聡文様にじっくりとお話を伺いました。
<聞き手=石嵜(学生団体GOAT編集部)>
【廣井様の今までの経緯・背景】
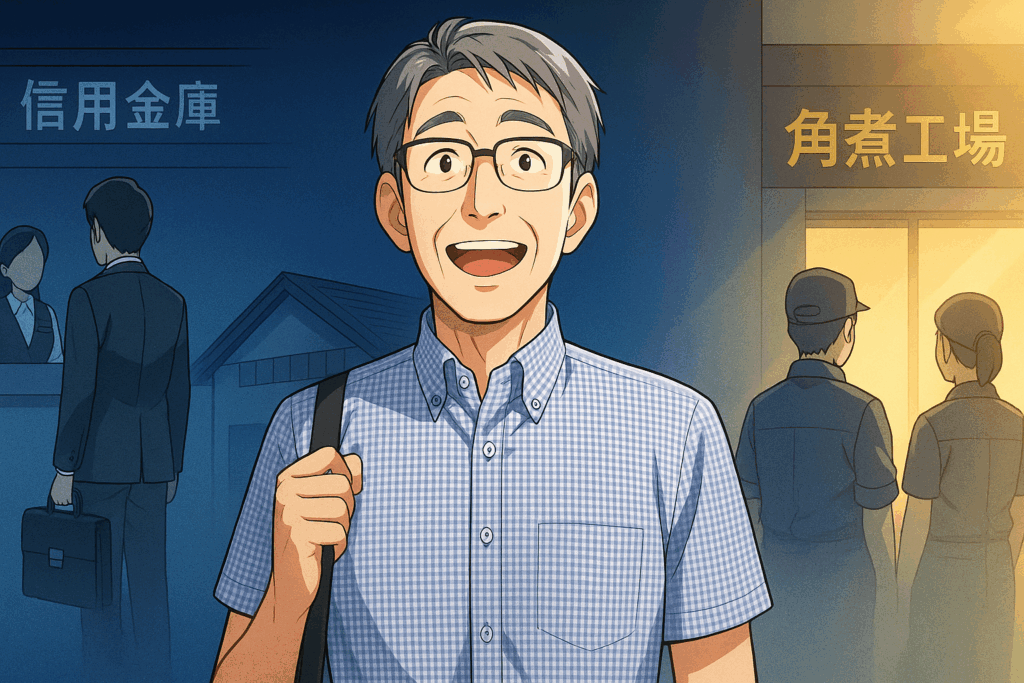
私は大学を卒業後、長崎信用金庫に10年間勤務しました。金融機関の合併を機に退職し、その後は豆腐製造業で10年間勤めました。職を探していた福島震災の頃、有限会社こじまが角煮まんじゅうを販売していることを知り、営業として入社しました。以来、営業畑を歩み、昨年10月頃まで営業を担当しました。そして、昨年4月、ミタニ建設工業の社長から突然の連絡があり、有限会社こじまの社長に就任することになりました。
大学では地質学を専攻しており、経営者になることは全く想像していませんでした。しかし、従業員の働く姿を見て、厳しい労働環境を何とか改善したいという思いは常に抱いていました。その環境改善が私の最大の目標で、皆の協力のおかげで、今は非常に働きやすい環境が実現できたと感じています。この環境改善に報いるためにも、今後は業績向上に注力するつもりです。経営者になってからは、家庭とのバランスも取れるようになり、妻からも「ちゃんと休めるようになってよかったね」と言われます。家庭の安定が仕事の基盤だと強く信じています。
取材担当者(石嵜)の感想
川中様のこれまでの多様なキャリアパスに感銘を受けました。特に、ご自身の経験から労働環境の改善を強く願われ、それが実現したというお話は、今後のキャリアを考える学生にとって、どのような環境で働くか、そしてどのような価値観を持つ企業を選ぶかという点で重要な示唆を与えてくれると感じました。従業員目線で物事を見てきたからこそ、社長として真に従業員を大切にする姿勢は、私たち若者が求める理想のリーダー像だと感じました。

【有限会社こじま事業・業界について】
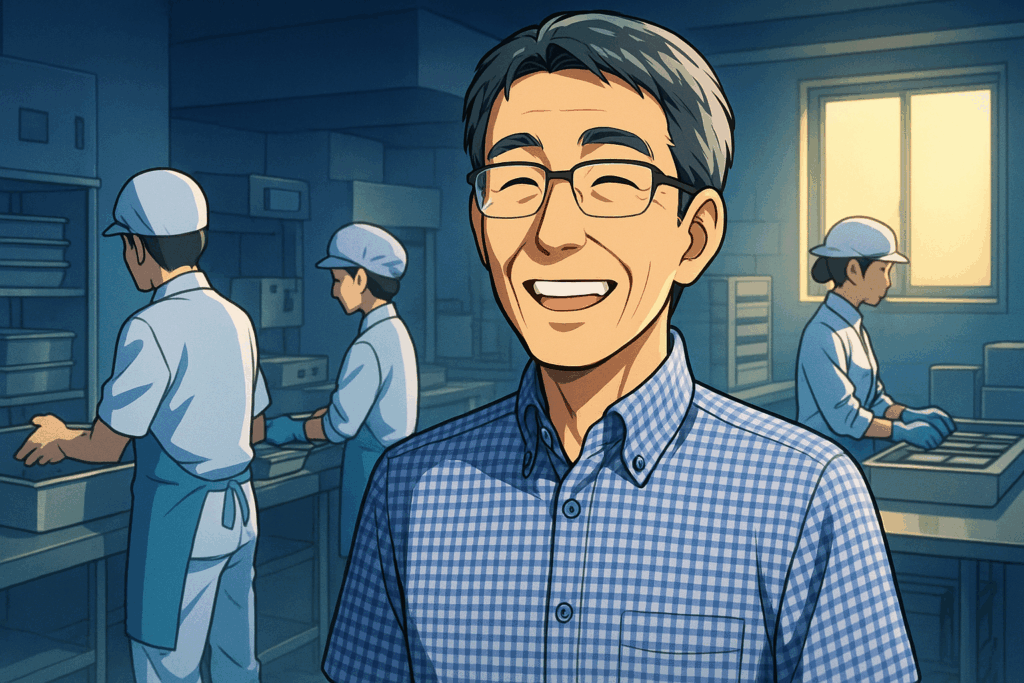
現在の経営者としての最優先事項は、会社の業績立て直しです。職場の環境や待遇はまだ発展途上ではありますが、最低限やるべきことはやり遂げたと思っています。これからは業績を伸ばすことに集中します。従業員も業績が給与に直結することを理解してくれており、皆で会社を盛り上げていきたいと考えています。この目標が達成できれば、いつでも役割を譲っても良いと考えているほどです。
当社は「角煮家こじま」や日本料理の「割烹こじま」を展開し、角煮製造工場も有しています。特に「割烹こじま」では長崎のフグ料理を前面に出しており、「長崎のフグといえばこじま」と認知されることを目指しています。夜の部に関しては、お客様に落ち着いた環境でゆっくりと料理を味わっていただくため、基本的に予約制を導入しています。行列を強いるような形での営業は、サービスの質を維持する上で避けています。これは、スタッフの休憩時間を確保し、安定したサービスを提供するためにも大切な方針です。
しかし、飲食・製造業界は人手不足が深刻です。和食の料理人確保は特に困難を伴います。昔ながらの「技は盗むもの」という職人気質が、現代の若者とのギャップを生み、離職に繋がる側面もあると感じています。工場では20歳前後の若手社員も勤務していますが、新たに求人募集をかけても応募が少ないのが現状です。これは、人手不足に加え、工場での仕事よりもAIやコンピューター関連など、より清潔な職場を志向する若者が増えている可能性もあると考えています。
ハローワークや求人サイトの利用に加え、タイミーのような短期人材サービスも活用が増えています。しかし、私は正社員の採用はきちんとした形で行うべきだと考えています。従業員との密なコミュニケーションを大切にした結果、離職率は以前より大幅に減少しました。SNSを活用した情報発信も重要だと認識しており、私は主に閲覧する立場ですが、20代の若手社員が積極的にコンテンツ制作や発信を担ってくれています。彼らの視点が、新たな顧客層へのアプローチに繋がると期待しています。
取材担当(石嵜)の感想
川中様が経営者として、環境整備の次に業績向上を掲げる明確な目標設定に感銘を受けました。従業員の理解を得ながら一体となって目標に向かう姿勢は、強い組織作りの本質だと感じます。
また、和食業界が抱える人手不足という具体的な課題、そして伝統的な職人文化と現代の若者の価値観のギャップは、学生が業界研究をする上で非常に示唆に富むものでした。コミュニケーションの重要性やSNS活用への理解も、現代の企業経営において不可欠な視点であり、学びが多かったです。

【有限会社こじまの今後の展望】
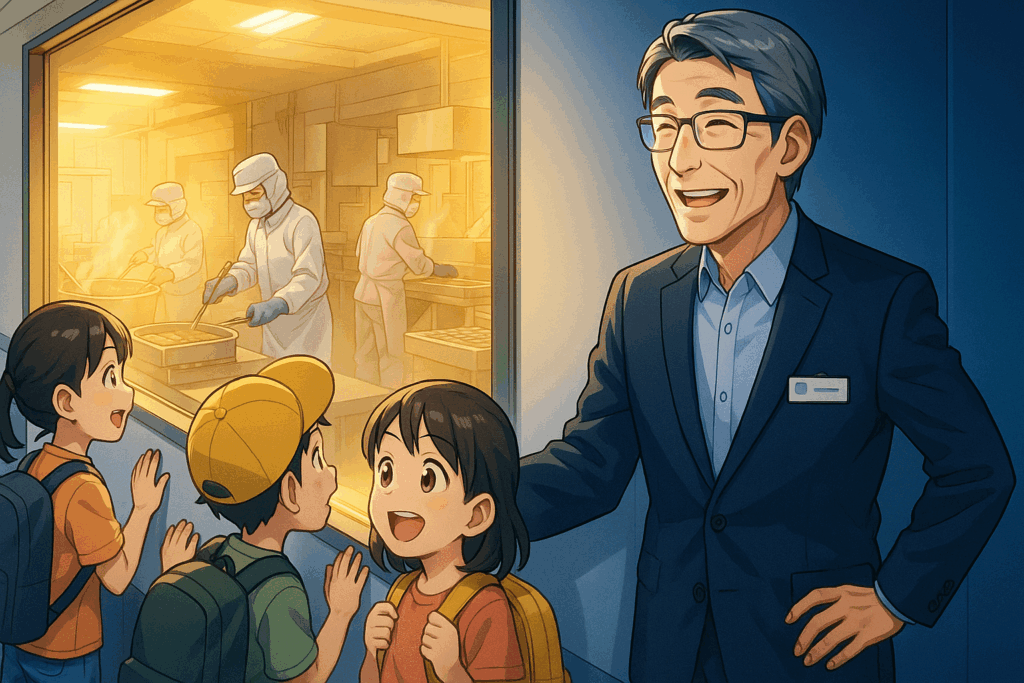
有限会社こじまの今後のビジョンは、まず「長崎に貢献したい」という思いが核にあります。将来的には、福岡にも匹敵するような県になり、長崎の象徴となる企業を目指しています。そして、長崎の子供たちが将来「こじまで働きたい」と思える企業にすることです。私が幼い頃に工場見学で感じたワクワクするような特別な場所という印象を、当社の工場見学などを通じて長崎の子供たちに与えたいと考えています。ヤクルト工場やカマボコ工場見学での自身の経験や息子の反応から、そうした体験の重要性を感じています。
最終的には「長崎といったらこじま、こじまといったら長崎」と、県民の皆さんに深く浸透するような企業を目指します。地元長崎に密着し、地域に根付いた企業であり続けること。そして、一人でも多くの長崎の子供たちが「こじまで働きたい」と当社を選んでくれることが、私の最大の目標です。
最近では、有限会社こじまのバンズを使ったバーガーショップ「Buns LABO」というポップアップ企画も進行中です。これは、長崎の多様な食材をバンズに挟む新しい試みであり、地域活性化の一環として大きな期待を寄せています。これからも地域と共に成長し、長崎の文化と魅力を発信し続ける企業でありたいと考えています。
取材担当(石嵜)の感想
川中様が語られた「長崎への貢献」と「長崎の子供たちが働きたいと思える企業になる」というビジョンは、非常に明確で心に響きました。単なる利益追求ではなく、地域社会との共生や次世代への投資を重視する姿勢は、学生が企業選びで重視するポイントと合致しています。
地域に深く根差し、その一部として成長していく有限会社こじまの未来に、私も一ファンとして大きな期待を抱きました。新たな挑戦である「Buns LABO」も、その地域貢献の意思を体現するものであり、今後の展開が楽しみです。

【廣井様から学生へのメッセージ】
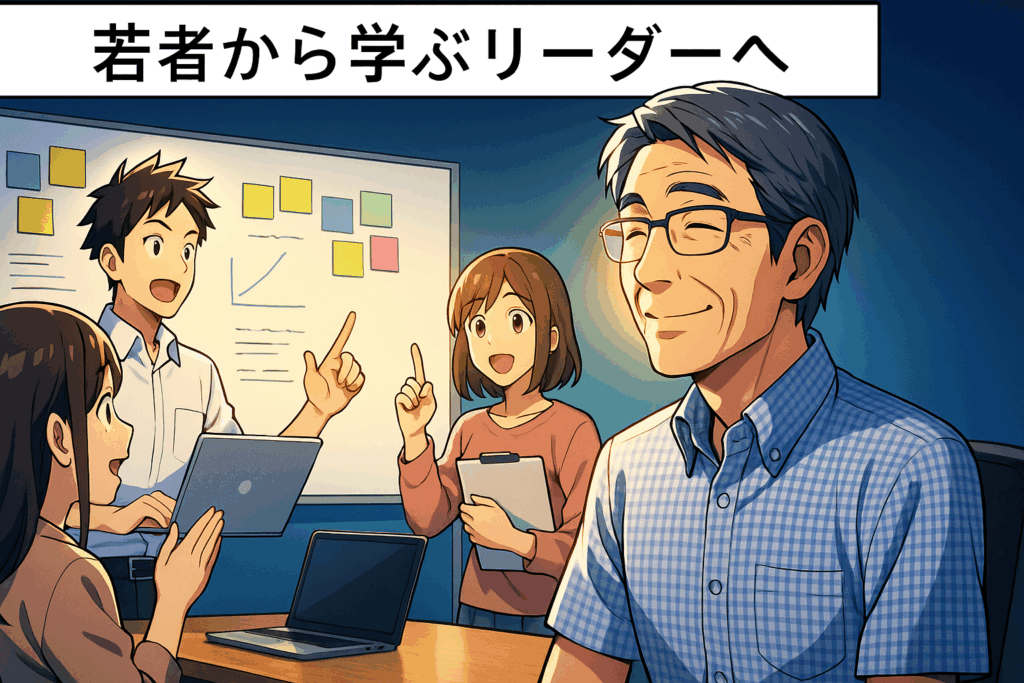
今の若い人たちへ、私から特別なアドバイスは必要ないと思っています。かつては「ゆとり世代」を心配した時期もありましたが、今は「すごい」とシンプルに感心しています。現代の教育では、タスク管理やプレゼン、プログラミングなど、企業で役立つスキルが小学生の頃から当たり前のように教えられていると感じます。彼らにとってそれは自然なことなのでしょう。
だからこそ、私たちは若い人たちから学ぶことが多いと考えています。私個人としては、若い人の意見には従う方が間違いがないとさえ感じているほどです。彼らの意見を頭ごなしに否定せず、「こうしたい」という思いがあれば、なるべくそれを実現できるようにサポートしたいと願っています。最初から「それはできない」と言うのではなく、まずは挑戦させてあげたいという気持ちが常にあります。
失敗を恐れず、どんどん挑戦してほしいと思います。私にとって失敗は「学び」であると考えています。だからこそ、若い皆さんには、「あれをしたい、これをしたい、これが目標だ」という思いをどんどん伝えてきてほしいと願っています。学生のうちに様々な場所へ飛び込み、行動すること。そして、何事にも興味を持つこと。興味があれば自ら学び、行動できるはずです。この二つが、社会に出てからも皆さんの大きな力になるでしょう。
取材担当(石嵜)の感想
川中様の若者に対する視点は、私にとって非常に励みになりました。特に「今の若い人たちには学ぶことばかり」という言葉は、私たち世代への大きな期待と信頼を感じさせます。
失敗を恐れず挑戦することの重要性を改めて教えていただき、学生のうちにどれだけ多くの経験を積めるかの価値を再認識しました。川中様のようなリーダーシップのもとで働くことは、自身の成長に繋がり、安心してチャレンジできる環境があるのだと強く感じました。










