男山株式会社は、北海道旭川の名水で地酒『男山』を醸す酒蔵です。1977年に日本酒として世界で初めてモンドセレクション金賞を受賞して以来、40年以上にわたり受賞を継続しています。国内外の酒類コンクールや全国新酒鑑評会でも数多くの金賞を受賞しており、北の大地に根差した酒蔵です。四季を生かした伝統の醸造技術を現代へと紡ぎ、変わりゆく時代とともに新たな挑戦を続け、現在では約40種類の商品を生み出しています。また、『男山』350年の歴史とともに、日本の伝統産業である酒造り文化を伝える「酒造り資料舘」を無料で公開しており、2024年9月13日からOTOKOYAMASAKE PARK内で営業しています。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【伝統を継ぐ者のキャリアパスと修行の経験】
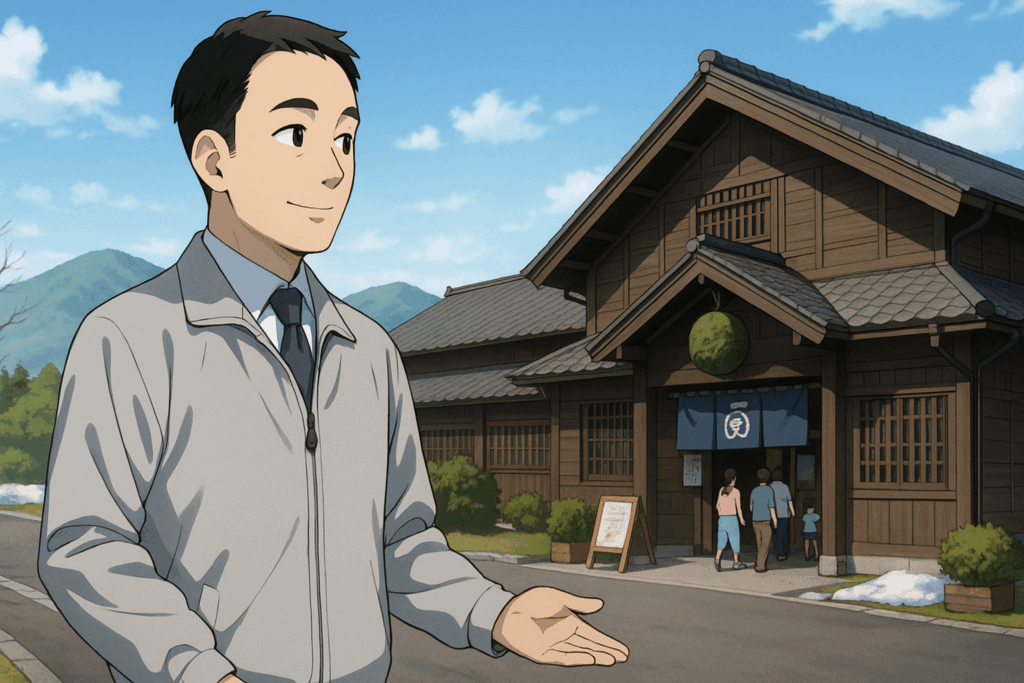
私は蔵元の5代目です。将来、現社長である父の後を継ぐ予定であるため、2014年に取締役に就任しました。男山に戻るまでの5年間は、総合商社の丸紅で勤務していました。大学卒業後、商社のビジネスモデルやより規模の大きな仕事に魅力を感じていたため、商社への就職を選びました。いずれ家業に戻るとしても、旭川でのスモールビジネスのような形になると考えていたため、まずは大きい仕事を経験したいと考え、商社に入社しました。
丸紅での経験は非常に大きく、今もなお、魅力的な同期・先輩・後輩との関係が続いていることが、キャリアにとって大きな財産となっています。商社での事業の広がりやスケール感を経験できたことは、その後の経営判断にも生かされていると感じています。
男山に戻ったのは2013年で、翌2014年に取締役となりましたが、当時の私はお酒の作り方についてまったく知りませんでした。そのため、父から「作り方を勉強してこい」と言われ、大分県の酒蔵で約7カ月、製造に関する勉強を行いました。この大分の酒蔵は、うちの社長と先方の社長が仲が良かったという縁もあり、行かせていただきました。
その酒蔵は小さな町にある酒蔵でしたが、地元に愛されている酒蔵のあり方や立ち位置について深く感じることができました。地域に根差した酒蔵の姿から学ぶところは多く、自分の役割を果たすために必要な知識と経験を、異分野での大きな仕事や他社での修行を通じて能動的に積む姿勢が、私にとって重要な糧となりました。
取材担当者(高橋)の感想
家業を継ぐという明確な将来の役割がある中で、あえて商社という異分野の大きなビジネスモデルを経験し、さらに酒造りの知識習得のために他社で修行をするという、広範な視野を持つ行動力に感銘を受けました。キャリアにおいて、自分の役割を果たすために必要な知識と経験を能動的に積む姿勢は、就職活動を行う学生にとって、目の前の企業選びだけでなく、自身の人生をどう生きるのかという問いに対する大きな学びとなります。

【品質への徹底したこだわりと早期からの輸出戦略】
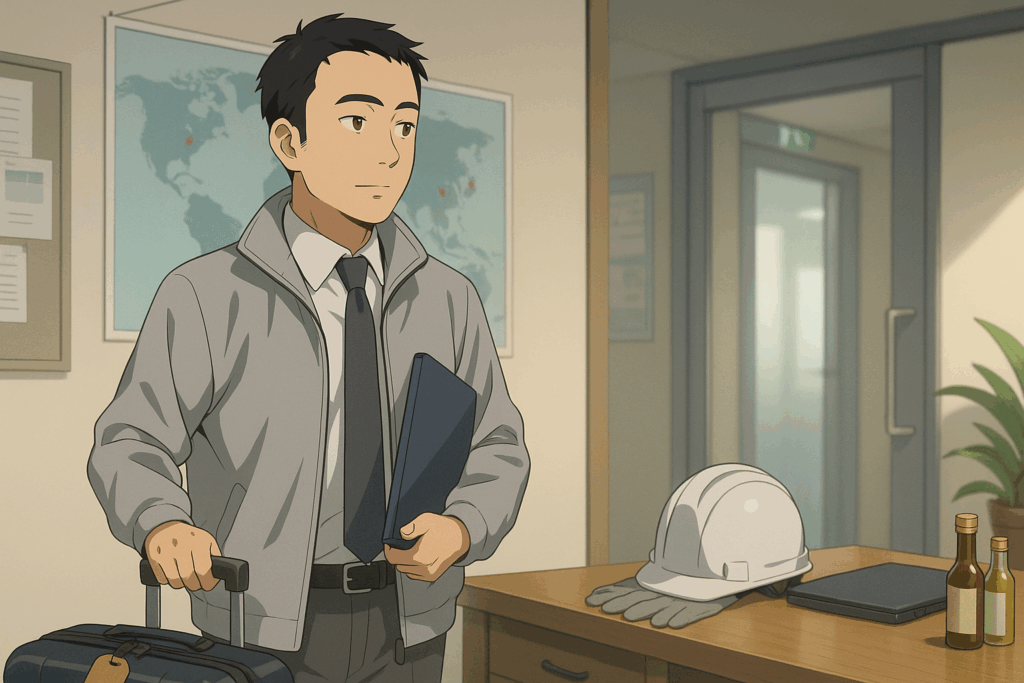
男山が持つ他社にはないこだわりの一つは、第一に「品質に妥協しないこと」です。弊社は品質管理を徹底するため、FSSC 22000という食品安全マネジメントシステムの認証を外部機関から取得しています。これはHACCP(ハサップ)を含む、安心・安全な製造のための国際的な管理規格です。例えば清掃手順の標準化など、安心・安全なものを作るための管理体制が整備されているかを外部機関がチェックし、認証を受けています。酒蔵でこの認証を取得している蔵は多くありません。
現在、男山の売上において輸出が占める割合は、売上構成比で約25%です。国内市場が縮小しているため、輸出の比率は自然と伸びています。弊社は、他の多くの酒蔵が輸出を本格化するよりはるかに早い1980年代に輸出を開始しました。輸出先は最も多いのが米国で、現在20カ国以上と取引しており、ほかに韓国や台湾などにも輸出しています。日本酒は日本食とセットで広がるため、日系人が多い米国では日本食に馴染みがあるエリアが多く、日本酒の市場も大きいと考えています。
早期から海外市場をターゲットにした背景には、当時の北海道の米と日本酒に対する市場の評価が関係していました。当時、北海道産の米は「評価が低い」ことで知られていました。そのため、「良い米が作れないのだから、お酒も美味しくないだろう」というイメージが広がり、「そもそも北海道で日本酒を作っているのか」というほど認知度が低かったのです。東京など大都市圏で売ろうとしても相手にされない状況でした。そこで、「東京で相手にされないなら、海外で先に知名度を上げていけば、自ずと東京で売れるようになるのではないか」と考え、海外で売るという戦略的な選択をしました。
取材担当者(高橋)の感想
国内で売れないという逆境を、「海外で先に認知度を上げる」という戦略で乗り越えられた点に、経営者としての強い意志と洞察力を感じました。また、国際市場で求められる高い水準――とりわけFSSC 22000認証に象徴される安心・安全の徹底――を満たしていることは、伝統産業の現代における競争力を高めるうえで極めて重要だと感じます。

【日本酒市場の縮小とイノベーションによる挑戦】
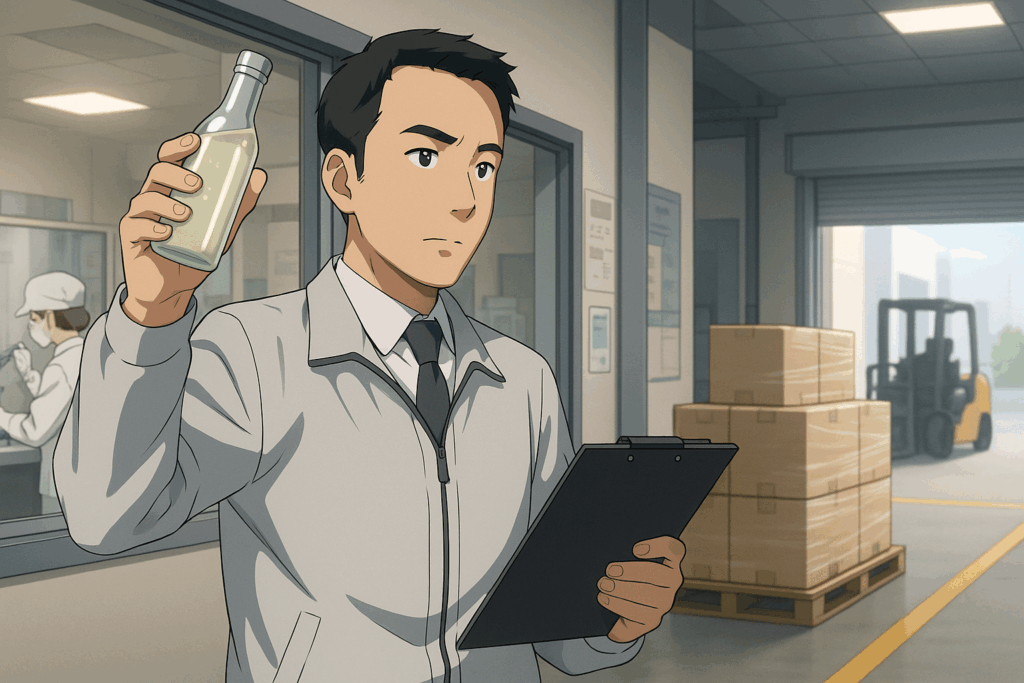
国内の日本酒市場は大きく落ち込んでいます。今の市場規模は、全盛期の4分の1以下になっているのではないでしょうか。日本酒はマーケットがどんどん縮小しており、海外では増えていると言っても、国内で落ちている分を賄いきれていないため、世界全体で見てもトータルでは下がっている市場です。輸出は増えていますが、それ以上に国内が減っています。縮小する市場で戦う選択もありますが、同じ労力をかけるなら伸びる可能性のある海外の方が伸ばしやすいと考えています。
うちの会社としては、将来的に国内と輸出の比率を半々(50%ずつ)にしていきたいという目標があります。しかし、日本酒は日本食と一緒に飲むものだと考えているため、日本の食文化が日本にある限り、国内市場がゼロになることはありません。地元の居酒屋や家庭で飲まれるような国内市場も、引き続き重要視しています。
若年層のアルコール消費の傾向を見ると、日本酒の消費は減っていますが、低アルコールのサワーやハイボールなどは市場が伸びています。若い世代にただ「日本酒を飲んでくれ」と訴えるだけでは、飲むきっかけにはなりにくいでしょう。既存の高年齢層だけでは市場は維持できないため、若い人に飲んでもらう工夫が不可欠です。
そこで、私たちは今、日本酒を起点とした新しい製品開発に挑戦しています。具体的には、日本酒由来のレモンサワーやジンを開発しています。米から日本酒を作る会社なので、発酵を通じてアルコールと糖分を生み出せる点を応用しています。アルコールの部分をジンに、糖の部分をレモンサワーに活用しています。
特にジンは、一般的な製品が輸入穀物などを原料とするのに対し、私たちは北海道産の米を原料として使っています。一般的なジンではアルコールの原材料の産地が分からなかったり、トレーサビリティが確保されていなかったりすることが多いですが、私たちは米から作っているため、原料の追跡が可能です。この安心・安全――原料が見える――という点を強みとして訴求しています。価格は高くなりますが、その価値に共感いただける方に選んでいただいています。
取材担当者(高橋)の感想
伝統的な日本酒の技術を応用し、米からジンやレモンサワーを開発するというイノベーションには大変驚きました。既存の強みを活かしつつ、伸長する低アルコール市場や、若年層が求める安心・安全な原料へのニーズに応える柔軟性は、縮小市場に対する強い危機感と挑戦心の表れだと感じます。

採用哲学と未来の若者へのメッセージ
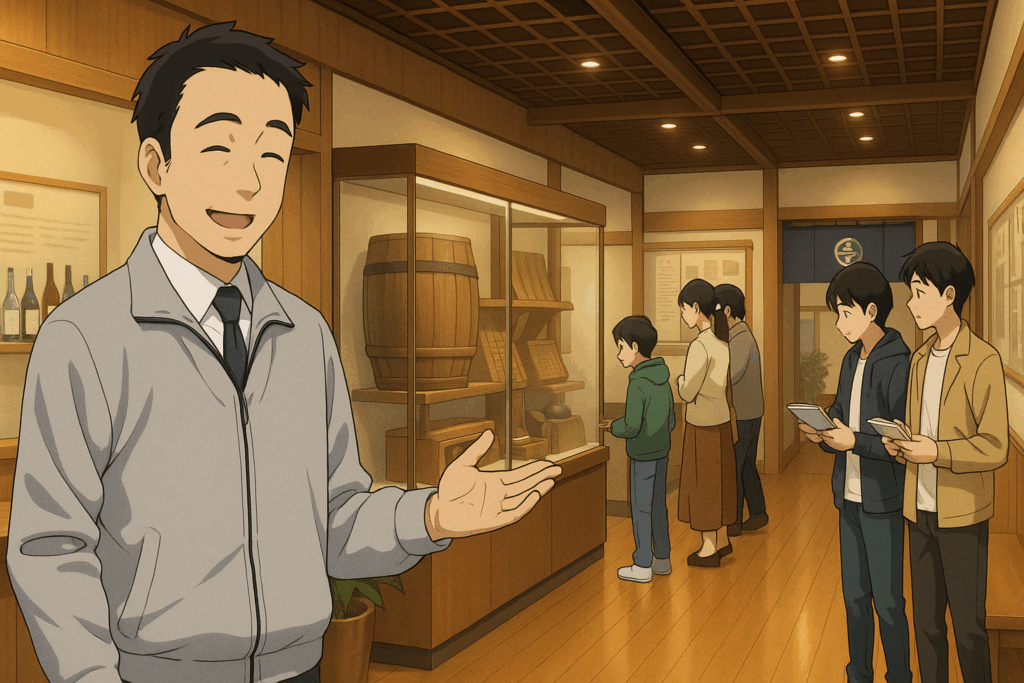
採用については、高校生や正社員の募集に対して応募が集まっており、実は大きくは困っていません。その理由として、募集方法の工夫よりも、会社としての価値を高めることが就職採用につながるという哲学があるからです。うちが良い会社であることを理解してもらえれば良いと考えています。
幅広い層に魅力を感じてもらうために、旭川にある旭山動物園の観光客も訪れるような、酒好きではない人も楽しめる「男山酒パーク」の運営にも力を入れています。入館料無料の「酒造り資料舘」もあり、日本酒好きではない人たちがたくさん来るため、少しでも日本酒に対してポジティブになってもらえる環境づくりに努めています。お酒の会社として見てもらうのと同時に、旭川を代表する会社だと感じてもらえるよう取り組んでいます。
酒造業界を目指す学生に対しては、日本酒が「日本ならではの伝統的なもの」であるため、それを作ることに楽しさや誇りを持てる人が向いていると思います。しかし、伝統産業であっても、日本酒だけでは生き残りが難しい時代になっているため、伝統を守ることに加えて、日本酒を起点とした新しい挑戦をする意欲も非常に大切だと考えます。
酒造りに限らず、常に世の中の動きに敏感であってほしいと思います。酒蔵と言ってもメーカーですので、お菓子や飲料などの嗜好品を含めて、どんなものが流行っているのかを把握しておくことが重要です。新商品が出たら試す、リニューアルされたら試すなど、試す習慣をつけることが大事です。ただ食べるだけでなく、人に語れるほど好きな商品を持つと、その商品が「なぜ売れているのか」「なぜ面白いのか」を深く考える癖がつくと思います
取材担当者(高橋)の感想
採用に困らないのは、会社としての価値向上を優先しているという明確な哲学があるからだと理解しました。また、世の中のトレンドに敏感になり、なぜその商品が売れているのか、面白さの核は何かを深く考える「考える癖」を学生のうちに身につけるべし、という助言は、起業を志す学生が多い私たちの世代にとって、夢を現実に近づける具体的なヒントだと感じました。伝統産業を守りつつも、時代に合わせて新しい挑戦(米由来のジンやサワーなど)を続ける姿勢は、未来のリーダーに必要な視点だと感じます。










