元気グループは、「共に生きる」を共通理念に、医療・介護福祉・教育を中心とした複数事業を展開するコングロマリットです。創業は1974年。現会長・神成 裕氏が埼玉臨床検査研究所を立ち上げたことを起点に、半世紀にわたり事業領域を広げてきました。
2024年にはグループ創業50周年を迎え、仲間は7,300名超の「大家族」へと成長。家族主義を掲げ、医療・介護・教育・各種専門領域で“感動と笑顔”を届ける基盤をさらに強化しています。
現在は、理事長・神成 裕介氏のもと、少子高齢社会とDXの進展を見据えた「変革」と「創造」を推進。医療・介護福祉・教育のアセットを組み合わせ、地域からアジアへと価値創造のシナジーを広げています。今回は、「家族主義」と「共に生きる」の思想を軸に、元気グループが描く次の50年について、グループの歩みと現在の挑戦を深掘りして伺いました。
<聞き手=石嵜渉(学生団体GOAT編集部)>
【神成様の今までの経緯・背景】
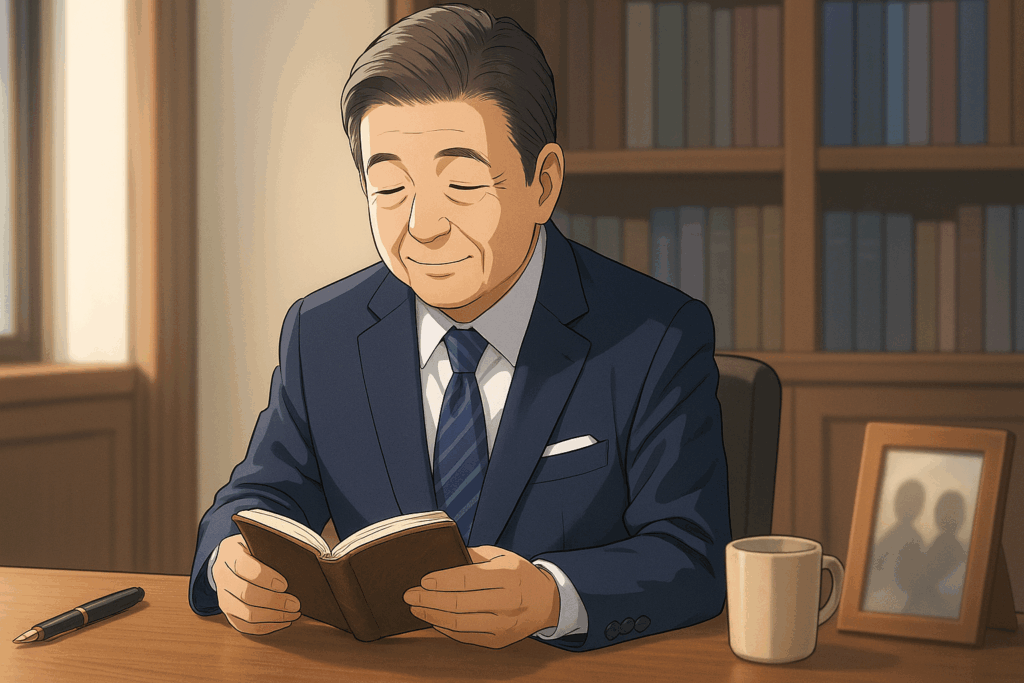
私が事業を立ち上げたきっかけは、非常に単純な動機から始まりました。中学校3年生の卒業時に「私は社長になるぞ」と決めていたのです。当時の社長というイメージは、お金持ちであり、貧乏だった私にとって、お金持ちになることでお袋(母)に贅沢をさせ、幸せにしたかった、というのが最初のきっかけでした。一生懸命頑張って社長になればお金持ちになれる、社長になってお袋を幸せにする、という非常に単純で分かりやすい目標を中学時代に決定しました。
そして、創業から50年間経った今も、この根本の価値観は何も変わっていません。きっかけは、目の前に優しいお袋がいたこと、その優しいお袋を幸せにしたかったという思いです。この50年間で、会社の仲間や、縁あってお付き合いできた人が非常に多く増えました。私は、そういう人たちにも幸せになってほしいと心から願っています。私と付き合ってみんな不幸になって泣いている人間がいたら、それは良いことではありません。縁があってお付き合いしてくれた人には、「あの人に出会えて良かったな」とか、「あいつは良いやつだと応援してやろう」と思ってもらえれば、それで良いと考えています。
事業は、23歳で臨床検査の仕事(埼玉臨床検査研究所)から始めました。その後、39歳くらいの時に株式の店頭登録を果たし(上場し)、富を得ました。当時、日本は若者の社会で人口が増え、消費が増えていましたが、バブルが弾けようとしていた頃に上場を果たしたのです。この富を得た根底にも、やはり人を幸せにしたいという思いがありました。この初期の動機が、現在医療、介護、教育といった社会インフラに欠かせない事業展開へと繋がっています。
取材担当者(石嵜)の感想
23歳という若さで事業を立ち上げ、39歳で臨床検査業界初の上場を果たした会長の行動力に圧倒されました。創業の動機が「お母様を幸せにしたい」という純粋な気持ちであり、その根幹の価値観が半世紀を経ても「縁ある人を幸せにしたい」という形でブレていない点は、リーダーシップと経営の継続性の鍵だと感じました。人を思いやる気持ち(EQ)こそが、長期的な成功と尊敬につながる本質的な価値であるという学びを得ました。

【日本元気グループの事業・業界について】
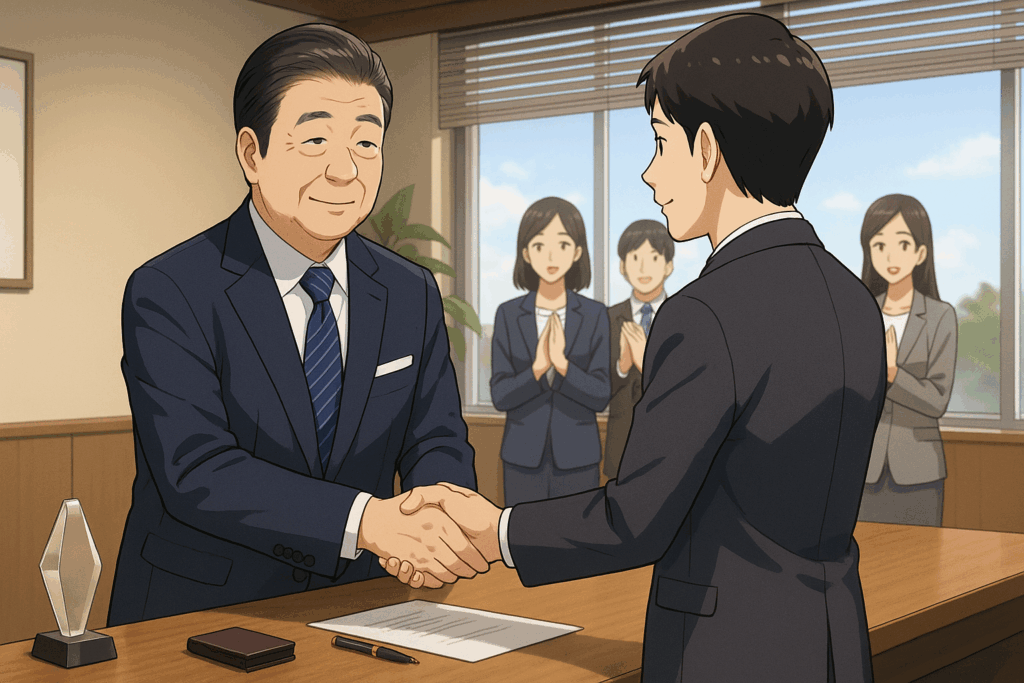
私たちが介護・医療・教育といった事業を拡大した背景には、日本の人口構造の大きな変化があります。かつて日本は若者の社会でしたが、高齢化率が14%を超え高齢者社会となり、現在では21%を超えウルトラ社会となり、さらに3割に近づきつつあります。この人口動態の変化によって、若者は減り、消費は伸び悩み、全てのものが下がり続ける状況になりました。また、当時の日本の強い経済力を危惧したアメリカが為替操作を行い、円高になっていったことも、日本が30年間成長しなくなった背景として存在します。
このような社会状況において、人手不足はどんな業界でも出るのは当たり前の事態です。特に介護や医療といった分野では深刻です。この問題に対し、私たちは、AIやロボットによる代替も一つの方法であると認識しつつも、元気グループとしては、アジアの国々(カンボジア、ミャンマー、ネパールなど)の人材に投資するという方法を選択しています。ロボットにお金をかけるよりは、アジアの人たちにお金をかけてやるという考え方です。
私たちは、彼らが日本に来て介護や医療の勉強をし、日本で働くことで親に孝行したり、自分の夢も達成できるように支援したいと考えています。カンボジアやミャンマーに日本語学校を設立し、現地で人材を育成するなど、日本でしっかりと勉強できるように準備しています。人手不足という社会課題に対し、「共に生きる」という理念に基づき、海外の人材に投資することで、日本と彼らの母国の両方に貢献することを目指しています。
また、経営における借金についても、私たちの考え方があります。私たちが医療や介護、教育といった社会インフラに必要な事業を行っていますが、これにかかる費用を、元気グループや個人の借金だとは思っていません。これは社会のための投資だと捉えています。社会が必要としているサービスを提供するための費用であり、社会の投資です。お金はあくまで幸せになるための手段であり、人のために使わなければ意味がありません。お金を中心にして考えると争いや差別が生まれるため、お金を中心に考える必要はないのですが、人を幸せにするために必要なものは当然必要であると考えています。
取材担当者(石嵜)の感想
日本の社会構造が若者主導から高齢者主導へと劇的に変化した背景を歴史的な流れと絡めて解説していただき、業界の現状が深く理解できました。人手不足への対応として、AI化だけでなく、アジアの人材育成に注力する姿勢は、まさに「共に生きる」という理念の体現だと感じました。また、借金を社会への投資と見なす会長の哲学からは、ビジネスの数字の裏にある社会的意義を強く学ぶことができました。

【神成様から学生へのメッセージ】
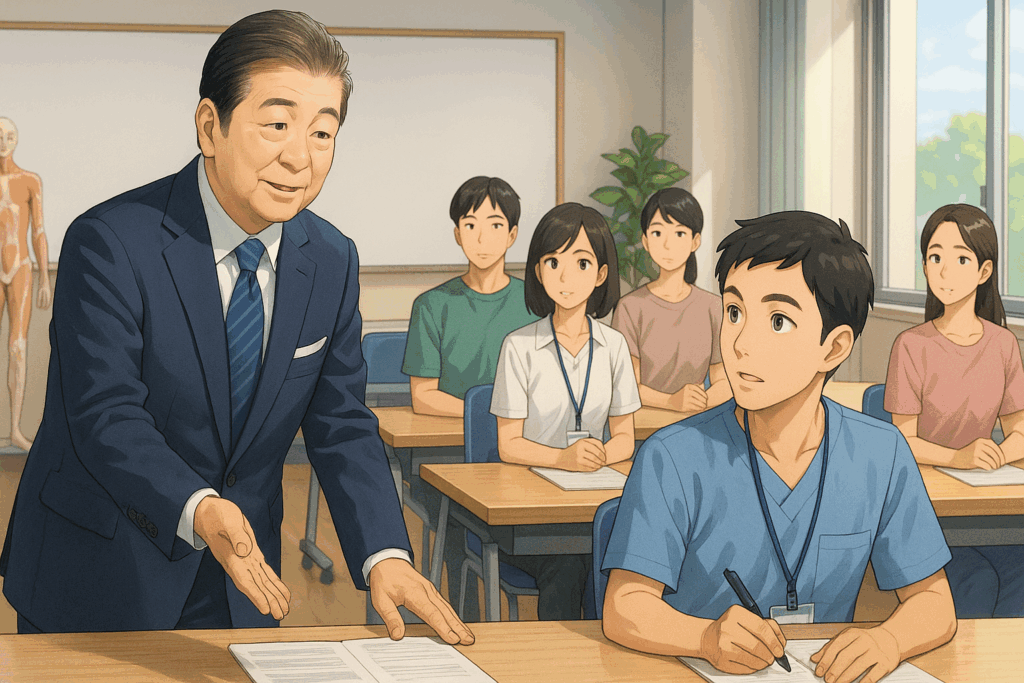
学生の皆さんには、まず「あなたは何のために生まれたのか」ということを考えてほしいです。それは、人のため、人の幸せのため、そして社会の人たちが喜んでくれるために生まれた、ということだと私は考えています。人間には目的がなければ生きてはいけないので、人が喜んでくれることが、結果的に自分自身の喜びであり、自分のための幸せにつながるのです。
誰かのために生きることが大切です。単純にお父さんお母さんのためでも良いし、あるいは飼っている猫や犬のためでも良いでしょう。最近の若い世代は「自分のため」にベクトルが行きがちだと言われますが、私が幸せになるということは、人が喜んでくれること、例えば「神成さんが頑張っているから私も頑張れる」とか、「あなたに助けてもらったよ」と言ってもらうことが、やはり自分にとって嬉しいことなのです。人が喜んでくれることは、まさに自分のためであると考えるのです。
私は自分自身を「頭が悪い」と決めているため、IQ(知能指数)が低いと思っています。もしIQが足りないと思ったら、人の2倍、3倍努力し、時間をかけて勉強する必要があります。時間をかけて覚えたり、分からないことは現場へ行って聞けば良い。IQの高い人には絶対に敵わないかもしれません。しかし、EQ(心の指数)だけは負けないと思っています。人の良さ、優しさ、思いやりといったEQは、人間そのものの価値であると私は思っているのです。IQが高いからといって人生成功するわけでもないし、尊敬されるわけでもありません。人から尊敬されるのは、やはり人柄(EQ)の部分であると結論づけています。
さらに、これからのリーダーを目指す者には、リベラルアーツ(社会的教養)を身につけることが不可欠です。スポーツ、芸能、社会の政治や経済といった、本当に様々な事柄について関心を持ち、自分の目で見て感じ、それを判断の基準に使うべきです。今、世界は大きく揺れ、混沌としています。若い世代だからこそ、既存の規制概念がなく、新しい価値観を追求し、歴史を変えるチャンスがあるのです。お金はあくまで幸せになるための手段であり、ベンチャービジネスを起こすにしても、「人のために」というきっかけがなければ、成功はあり得ないと考えています。
取材担当者(石嵜)の感想
「人のために生まれてきた」という言葉は、私たち日々の行動の指針になると感じました。また、多くの人が気にしがちなIQよりも、優しさや思いやりといったEQが真の人間的価値であるというお話は、学生である私にとって心に響きました。今こそ世界や政治、経済に対して目を向け、教養を身につけることが重要だというメッセージを受け、これからの学生生活で視野を広げていきたいと強く思いました。

【日本元気グループの今後の展望】
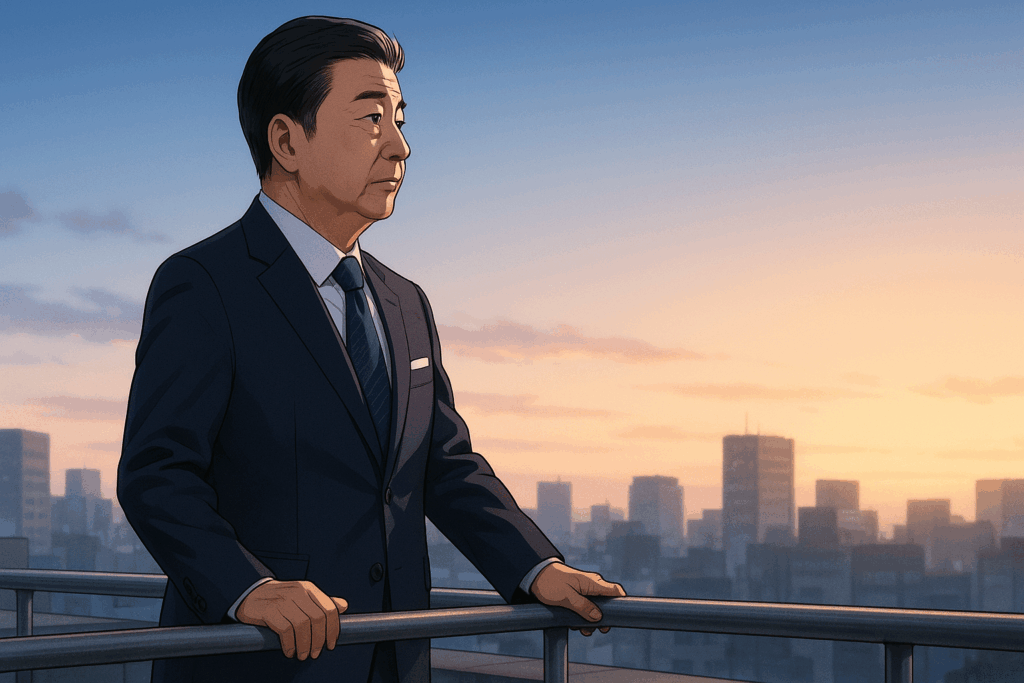
私は、よく言われる「持続可能な社会・会社」という概念に対して、疑問を投げかけています。仏教の「諸行無常(全ては変化する)」の教えを引用すれば、会社を何のために持続させなければならないのか、という問いが生まれます。命には必ず終わりが来るように、会社もいずれはなくなるものです。
しかし、会社を運営する上で唯一変わらない大前提は、「すべてのものが人のためにある」ということです。元気グループが人のためにならず、人の役に立たなくなり、世の中の変化についていけなくなったなら、それは持続しなくていいと考えています。会社自体がどうであるかよりも、そこで働く人たち一人ひとりが、自分の人生を「人のため」に生き、その組織に属しているうちは人のためになることを大前提とする。その個々の努力と貢献の連鎖こそが、結果として元気グループを繋いでいくことになると考えています。会社は極端な話、どうでも良いのです。
これから社会に出ていく皆さんには、「寝ないで目をあけている習慣」をつけた方が良いと伝えたいです。寝不足で死んだ人はいません。目をあけていると自然と考えるからです。それを人のために目をあけていた方が良いという気がします。私はこれまで、働き続けてきたというよりも、目を閉じることなく考え続けてきました。死んだら目をつぶって寝ていられますから、生きているうちは目を閉じることなく、人のために考え続けるべきなのです。
取材担当者(石嵜)の感想
企業のトップの方が「持続可能性」という現代のキーワードを批判的に捉え、「諸行無常」という概念を経営に持ち込んでいることに驚きました。会社は目的ではなく、人の役に立つための手段であり、その会社の存在意義は、そこで働く一人ひとりがどれだけ「人のため」に生きるかにかかっているという考えは、働くことの意味を深く考えさせられました。人生はいつか終わるからこそ、生きている今この瞬間も努力し、人のために生きるべきだというアドバイスは、私たちにとって非常に力強い言葉でした。










