本記事でご紹介するのは、新潟・長岡で80年の歴史を持つ老舗料亭の4代目社長を務める長谷川様です。伝統的な「趣き」と地域の良さを守りながら、IT導入や新しい営業戦略を推進し、老舗の変革を進めてきました。通信会社出身という異色の経歴を持つ長谷川様が、どのようにして伝統企業を現代に適合させ、組織を改革したのか、その軌跡と若者へのメッセージを語ります。今回は、老舗料亭の伝統と革新を両立させるために挑戦を続ける4代目・長谷川様に、地域に根ざした経営哲学と、未来を見据えたビジョンについてじっくりとお話を伺いました。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【巨大企業からの転身:異業種での経験が変革の礎となる】
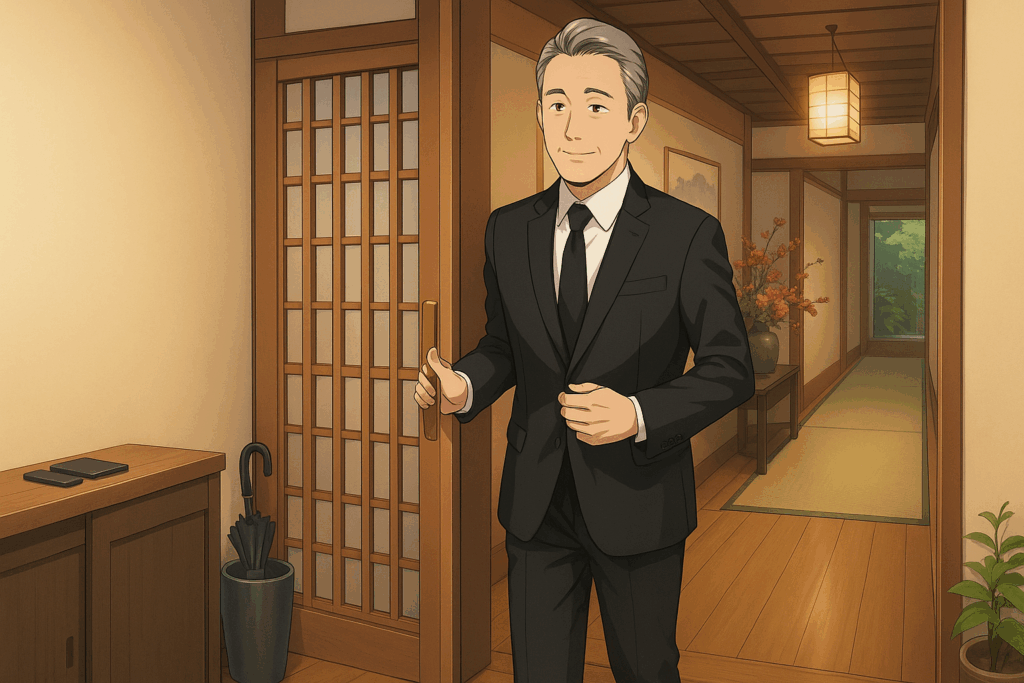
私は元々新潟の人間ではありません。18歳までは長野県におりました。その後東京へ出て、6年間過ごしました。最初の2年間は大学浪人という名の下の「無職」で、その後大学生を4年間やりました。私がしっかり働き始めたのは25歳で、就職した会社が東京の大手通信会社でした。転勤で新潟の長岡に来ました。6年間営業として仕事をしていました。その間に、当時の3代目社長の長女と知り合い、結婚しました。
結婚が決まった頃に、会社(料亭)に入ってくれと誘われましたが、一度断りました。通信会社とは畑違いの料理業界で、全く分からなかったからです。その後、転勤の話などもあり、長岡は良いところだと感じていたため、前職を辞めて今の会社に入社しました。
前職では、営業の「イロハ」をゼロから教えていただきました。その結果、信越地域ではトップクラスの営業成績を修めることができました。私が前職を辞めたのは、「もうちょっと違う世界を見たい」という思いがあったためです。元々、誰もやっていない領域や、よく分からないところに飛び込むことに楽しみを見出す性格なので、新しい挑戦へ進む動機になりました。
取材担当者(高橋)の感想
長谷川様が、巨大企業での安定したキャリアを離れ、伝統的な料亭の世界へ飛び込んだ決断は、長谷川様の「誰もやっていない領域に飛び込む」というチャレンジ精神の表れだと感じました。前職時代に培った通信やシステムに関する知識 が、創業80年の老舗のIT化に貢献したという事実は、一見無関係に見える過去の経験が将来のキャリアに大きく役立つという、就活生にとって貴重な学びになると思いました。

【デジタル化の推進と社員の意識改革:お客様を「外から持ってくる」】
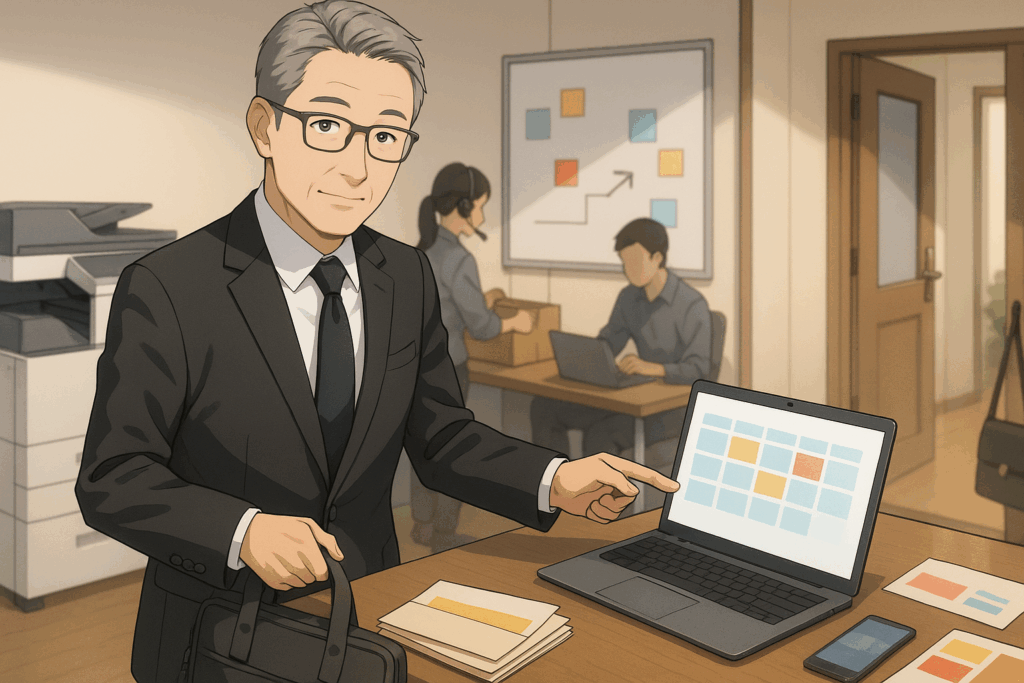
入社してから社長に就任するまでは17年ほどかかりました。当時の社長(妻の父親)は私と24歳も違いましたが、私のやり方を応援してくれていて、あまり口を出されたことは無かったです。また妻の祖母(当時大女将)、妻の母(当時女将)、妻(現在の女将)も一緒になって、会社の未来のための新しいやり方を模索していたように思います。入社からの17年間で、私は積極的に社内の仕組みを変えることを提案し実行していました。当時、予約は電話とFAXが中心でした。通信会社にいた経験を活かし、メールアドレスを取得し、インターネットでの予約導入に早い段階で着手しました。
また、社内の業務効率化も進めました。当時手書きが多かった請求書の発行を、パソコン導入とシステム化によって自動印刷できるように整備しました。社会が変わるように会社も変わっていかざるを得なかったのです。前職での経験が役に立ち、ホームページの構築やシステム化も含めた提案は、会社が変わっても実行できました。社長就任後、最も注力した改革は社員の意識改革でした。料理屋は飲食だけでは非常に厳しい時代に入っています。
弊社は現在、お弁当の配達やネットを介しての物販に力を入れております。大都市と違い、毎日違うお客さんが入れ替わり立ち替わり来ることはなく、リピーターの方が多いからです。飲食店は通常、予約を「待つ」営業ですが、私は前職で営業をしていた経験から、外に出て営業する、つまりお客様を「外から持ってくる」やり方を導入しました。ホームページでのPRを強化したり、リピーターの方に季節ごとにチラシ(DM)を送る営業を地道に行いました。現在、ネット予約(ホットペッパーや自社HP)は全体の3分の1を占める重要な予約経路になっています。
長い間飲食業界にいる方には、自分をPRすることが苦手な「奥ゆかしい」気質がありました。昔は「言わなくてもお客様が分かってくれる」時代でしたが、競争が激しい現代では、自分から「うちはすごいですよ」とPRしなければ埋もれてしまいます。意識を変えるために、私が率先して外に出てお客さんと話し、新しい客層を呼んできました。それにより、今までに来られたことがないお客様も来るようになり、社員は「会社が変わってきている」という実感を持ち、意識の変化が促されたと思います。
取材担当者(高橋)の感想
伝統的な事業の「待ち」の姿勢を、通信会社時代の経験に基づいた「攻め」の営業姿勢に変えられた点に、長谷川様の変革への強い意思を感じました。特に、奥ゆかしい職人気質の社員様たちの意識を変えるために、社長ご自身が率先して営業の行動で変化を示し、新しい客層を連れてくることで意識改革を促された点は、組織を率いる上で重要なリーダーシップのあり方だと感じました。オンライン予約の導入は、特に電話予約に緊張感を覚える若い世代 や、格式を高く感じるお客様 にも利用しやすくし、顧客層を広げるのに成功していると考えられます。

【業界に「染まらない」若者の感性:真のホスピタリティを実現する】
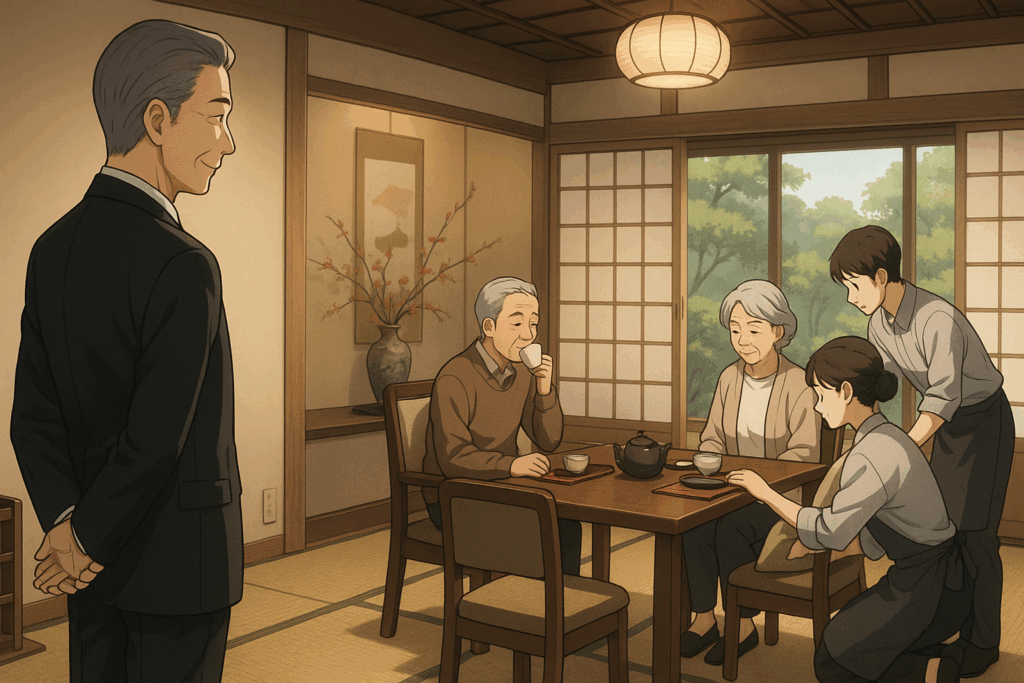
私が31歳で入社した時、私が社内で一番若い年齢で、当時の従業員は50代、60代、70代が中心でした。老舗の門構えのイメージがあり、若い子が働いていなかったのです。そこで、会社に新しい風を吹かせ、活性化させるために、できるだけ若い人材を採用しようという方針に転換しました。新卒や若い方々は元気ですし、感覚が違うのが非常に勉強になるというか、会社の雰囲気が変わるのです。
私は、業界に染まらない方がお客様のためになると考えています。業界に染まってしまうと、この業界の論理でやり始めますが、それってお客様のためにならないことがたくさんあります。当店ではお客様の会話や食べるスピードを見て、お料理を出すペースを調整しています。お客様のスピードが一番大切なんです。これは当たり前のことなのですが、その当たり前ができていない店舗が多くなっているように思います。
新卒の方が入ってくれると、そういう業界とは「違う感覚」が生まれます。料理に関してはセンスが違います。器や膳の作り方で色遣いが明るい感じになったりします。その道50年、60年の料理人だと、「この時はこの色」という習慣や癖ができてしまっていて、なかなか変えられません。新卒の方が入って、業界の常識に「染まってない」部分が良い影響を与え、私たちも勉強になります。新しい風を吹かせるという意味でも大切にしています。
また、人手不足の課題には、柔軟に対応しています。新卒や中途採用も続けていますが、単発バイトのマッチングサービス(新潟ではマッチボックス)にも登録して人を集めています。ただし、お願いする仕事は、サービススタッフ(接客)ではなく、片付け、掃除、製造工場の梱包といった裏方の仕事に限定しています。人に会うのを嫌がる方も多いからです。うちは予約商売なので、予約状況(平日夜の企業接待、土日の顔合わせ等)を見て、必要な時に必要なだけ労働力を確保しています。
取材担当者(高橋)の感想
業界の常識に「染まらない」若者の感性が、古い慣習を打ち破る力になっているというお話は、就活生が自身の「常識外の感覚」に自信を持つきっかけになると思います。お客様のペースに合わせて料理を調整するという徹底したホスピタリティ は、業界の論理を乗り越えた真のサービスだと感じました。さらに、人手不足への対応として、接客以外の裏方業務に短期バイトを限定的に活用し、接客の品質を維持しながら労働力を確保するという柔軟な戦略は、地方企業が抱える課題に対する具体的な解決策として非常に参考になりました。

【企業存続への挑戦と若者へ贈る「心の余裕」の重要性】
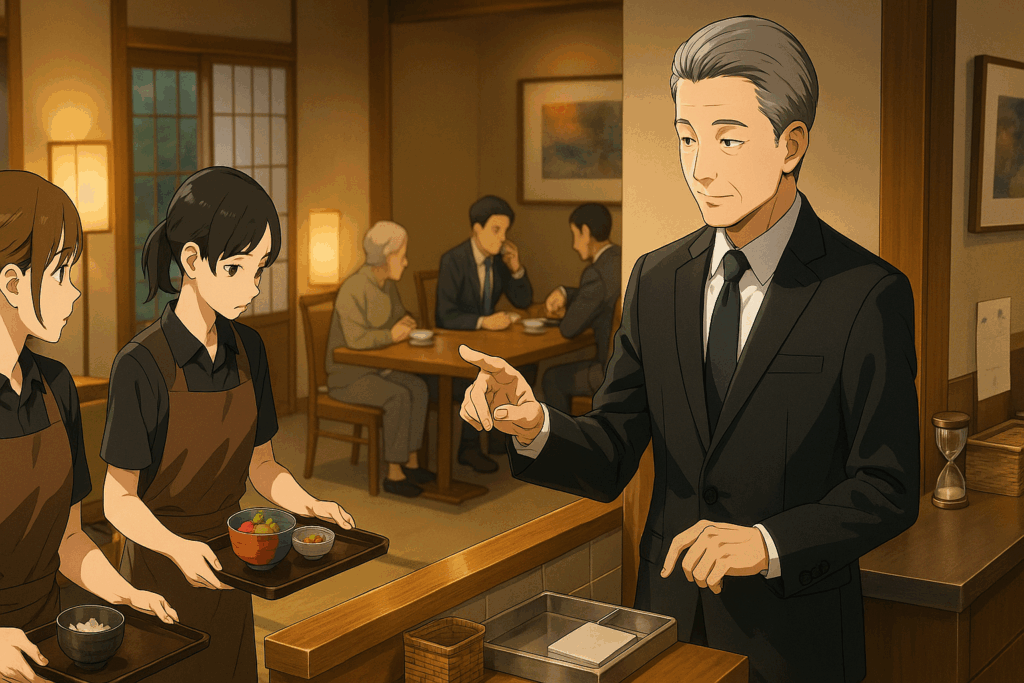
今後の目標は、企業が存続することが最も大切だと考えています。続けるということが大変ですが、今から10年後、20年後、30年後にもうちの料理屋が存在していることが目標です。そのためには、長岡らしさ、田舎らしさを出し続けることに注力しています。料理の質も、サービスタッフの質もそうです。
例えば、うちには接客マニュアルがありません。マニュアルがあると、みんな同じことを言うのでロボットみたいになってしまい、つまらないですよね。特に東京などから来られたお客様にとって、東京と同じだと多分つまらないだろうなと思うので。接客研修や指導はしますが、その人自身の雰囲気や話し方、地方の方言を使うといった、個性を大切にする温かいサービスを追求しています。田舎らしさを出すということです。
一方で、存続のためには時代の変化に合わせた物理的な変化も必要です。昔は畳の上に座布団で食事をしていましたが、高齢のお客様が増えて足が痛くなる問題がありました。そこで、日本的な雰囲気を失わないよう配慮しつつ、早い段階から畳の上に椅子とテーブルを導入しました。約99%のお客様が椅子席で食事をされています。雰囲気を味わいながらも、体が楽に食事できる環境を整えるなど、そういった変化は続けていかないとだめだと思っています。
20代の若者には、「たくさん遊んで様々な社会を見て、社会人になった方が人の心が分かる」ということを伝えたいです。飲食は、大きな意味で「遊び」の部分だと思っています。楽しさが重要です。今の学生さんは真面目すぎる方が多く、ちょっと遊びが少ないなと思うのです。真面目な人ほど、お客様からの批判や理不尽な意見を真に受けてしまい、心が疲弊しがちです。しかし、たくさん遊んで心に活力と余裕ができると、お客様の意図を察し、「いい意味でスルーできる」ようになるのです。私たちは、常にニコニコできる心の余裕を持った人材を求めています。そのぐらい心の余裕がないと、細やかで、心温たまるサービスを継続的に提供することは難しいでしょう。
取材担当者(高橋)の感想
企業が存続すること、そしてそのためには地方の個性をマニュアル化せず磨き続けるという視点は、地方創生を考える学生にとって学びになりました。また、「たくさん遊んで社会人になった方が人の心が分かる」というアドバイスは、真面目であることで消耗しやすい現代の若者にとって、仕事と自己防衛のバランスを取るための新しい指針になると感じました。お客様からの多様な意見を自分なりに解釈し、温かいサービスを継続的に提供するためには、心の余裕、すなわち「遊び心」が不可欠であるという長谷川様の示唆は、今後の社会人生活における大きな指針になると感じました。










