株式会社青葉は、1940年の創業以来、80余年にわたり札幌の地で地域に密着してきた老舗のマッサージ店「青葉マッサージ」を運営しています。事業内容は、マッサージ指圧と鍼の施術が中心です。リラクゼーション、鍼灸治療、美容鍼灸、カッピング、そして自宅やホテルでの出張・訪問施術など、多彩なメニューを提供しています。経験豊富な施術者が心身のバランスを整える施術を行い、各種保険の利用や相談にも対応しています(青葉社会保険労務士事務所も展開しています)。本記事では、株式会社青葉の社長が、いかにしてこの業界に参入し、数々の困難を乗り越えてきたのか、その経営哲学と学生へのメッセージをまとめます。今回は、創業から続く地域密着の歩みと、逆境を力に変えてきた経営哲学、そして未来を担う学生への思いについて、株式会社青葉の代表取締役社長にじっくりとお話を伺いました。
<聞き手=石嵜渉(学生団体GOAT編集部)>
【弁護士の夢と教育事業への強い目標】
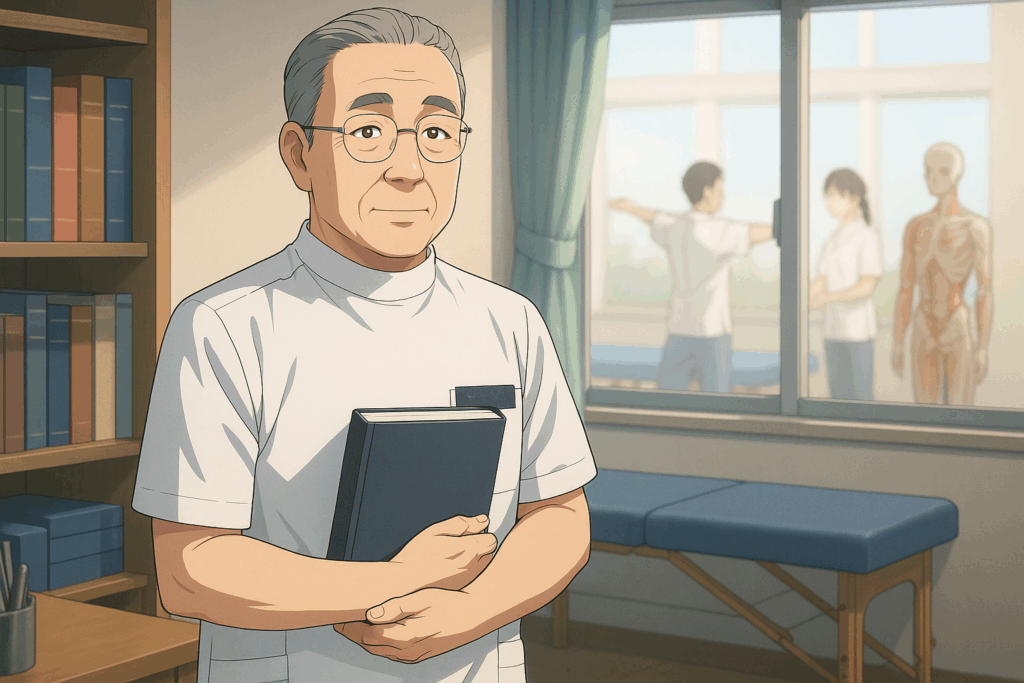
私は大学で法学部を卒業し、当初は弁護士になりたいと考えていました。卒業後、研究生として2年間学校に残って勉強を続けましたが、その努力では夢を達成することができませんでした。その頃、親(母親)が旭川での水商売を全て畳み、札幌に出てきていました。母は、水商売だけでは体を壊すことを懸念し、何か良い仕事を探していたところ、ちょうどM&Aでマッサージの事業が売りに出されており、それを母が買い取ったことが青葉との最初の接点です。私自身には事業を継ぐ意思は全くありませんでしたが、弁護士にもなれなかったので、株式会社青葉に入社することになりました。
この業界に入り、業界全体を見渡したときに、学校教育施設という教育関係が全く整っていないことに気づきました。私はこれを改善したい、「学校を作りたい」という強い目標を持ちました。この高い目標を達成するために、青年会議に入会するなど、手段を考えて実行に移しました。元々は北海道から出る必要はないと考えていた人間でしたが、青年会議の世界研修委員会などで日本中や世界中を回る中で、自分の殻を破ってもらうことができました。
学校設立は簡単な道のりではありませんでした。当時、マッサージや鍼の業界は、マッカーサーが「日雇いの刑だ」として潰そうとした歴史的背景がありました。昭和21年か22年に学校が作られて以来、長らく新しい学校は新設されておらず、盲人の保護のための規定が大きな障壁となっていたのです。しかし、私どもの友人が福岡で厚生労働省と裁判を行い、ハリと柔道整復については盲人保護政策の制限がかかっていないという主張で勝訴しました。その流れを受けて、私も札幌に札幌青葉鍼灸柔整専門学校を作ることができました。親の後継で事業を始めましたが、勉強一筋だった私が最終的に「学校を作りたい」という目標を叶え、今は業界の会長職も務めています。
法学部で弁護士を目指されていたにもかかわらず、全く異なるマッサージ業界に入り、さらに業界全体の教育水準を向上させるために学校設立という壮大な目標を持たれたことに驚きました。目標を叶えるために、青年会議に入り、日本や世界を回るという行動力は、私も見習うべきだと感じます。特に、困難な状況下で諦めずに目標達成のための道筋をつけられた経験は、私たち学生が自分の人生の目標を決める上で非常に勉強になると思いました。
取材担当者(石嵜)の感想
法学部で弁護士を目指されていたにもかかわらず、全く異なるマッサージ業界に入り、さらに業界全体の教育水準を向上させるために学校設立という壮大な目標を持たれたことに驚きました。目標を叶えるために、青年会議に入り、日本や世界を回るという行動力は、私も見習うべきだと感じます。特に、困難な状況下で諦めずに目標達成のための道筋をつけられた経験は、私たち学生が自分の人生の目標を決める上で非常に勉強になると思いました。

【激化する競争とコロナ禍でのサバイバル】
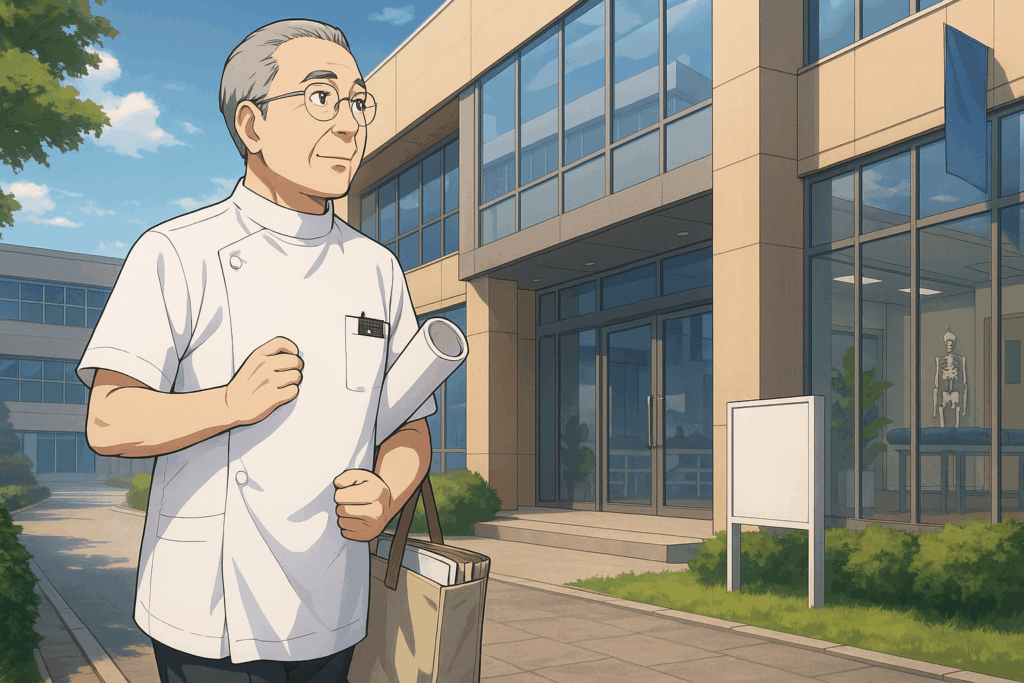
私どもの業界は、パーソナルトレーナーや介護など様々な業態と接点があり、優れている業者が多い一方で、競争が激しくなっています。大手でやっているところも潰れているのが現状です。また、経済産業省が「リラクゼーション業(手技によるもの)」を娯楽業の中のエステティックの下に入れてしまった影響で、身分法がなく、誰でもサービス提供ができる状態が存在しています。その結果、業界は企業化しにくい業となってきており、個人企業が増加しています。
事業環境として厳しいのは、単価の安さです。保険適用で施術を行う場合、めちゃくちゃ儲かるような業態ではなくなっています。しかし、希望がないわけではありません。本人が努力すれば、努力しただけ見返りがあり、マッサージ指圧・鍼だけで個人で1000万プレイヤーになっている人は少なくありません。これは、他の国家資格を持つ士業(社会保険労務士、行政書士など)が個人としての目標とするレベルと同じであり、努力次第でどの国家資格でも達成できると考えています。
近年経験した最大の苦難はコロナ禍でした。以前は従業員が110名おり、札幌のホテルのほとんどでサービスを提供していましたが、コロナにより夜ホテルに泊まる人がいないという状態になり、売上が全くなくなりました。会社を持続させるためには、会社を小さくするしかなかったのです。
私は、70名ほどを解雇するという苦渋の決断をせざるを得ませんでした。当時の日本経済新聞にも、雇用調整金を使っても支給が半年後になることが報じられており、社会保険料などの支払いに手元の資金が足りなくなるため、解雇の道を選ばざるを得なかったのです。あるお金で皆さんに1ヶ月分や2ヶ月分のお金を渡し、今は会社を小さくしてどうにか生き延びています。会社を小さくし、経費をどんどんサイズダウンする努力をして、今やっと利益が出るようになってきたところです。
どんな仕事にも苦難はやってきますが、目標を持って笑顔でいられるのは、学生時代に柔道で全国大会レベルの練習をする中で学んだ「なにくそ魂」が土台にあるからです。あの頃の柔道の練習よりは厳しくないと思えるため、乗り越えられます。
取材担当者(石嵜)の感想
社長が直面されたコロナ禍のダメージの大きさと、会社を存続させるための経営判断の厳しさが伝わってきました。特に、学生時代に柔道で培ったという「なにくそ魂」が、70名解雇という辛い経験を経ても、前向きに経営を続けられる精神力の源になっているという話は、非常に感銘を受けました。スポーツに限らず、学生時代に何か目標を持って熱中し、困難を乗り越えた経験を持つことが、社会人としての大きな財産になるのだと実感しました。

【「生きがい」を見つけ、計画的に一歩ずつ進む】
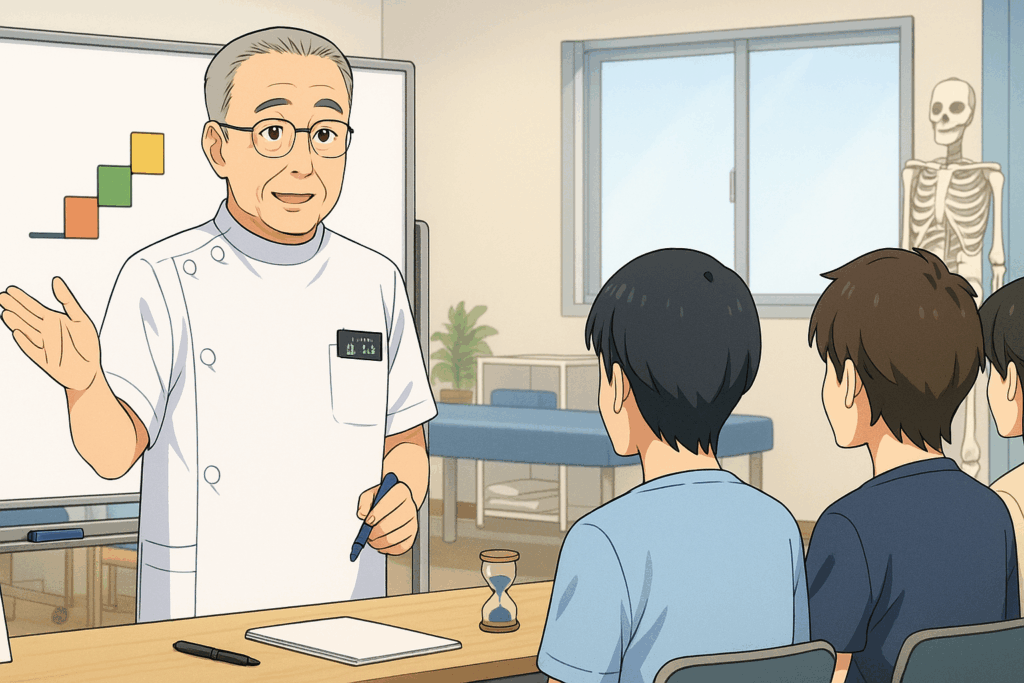
今の学生の皆さんに伝えたいのは、人生は「生きがいを見つけた者」の勝ちだということです。生きがいを見つけ、「これを頑張りたい」と思ったら、たとえ貧乏や辛いことがあっても、やりたいと思える何かがあればきっと達成できます。それを探し当てられるかどうかが重要です。社会に対して文句を言うのではなく、自分で努力して何か目標を見つけていかなければならないと感じています。
私自身、今65歳ですが、今の知識と経験を持ったまま大学生に戻れたら、人生は全く違っただろうと思うことがよくあります。学生の頃は、何が良いのか悪いのか分からず、行き当たりばったりでした。人生における計画の重要性を強調したいです。高い目標を持つことはもちろん大切ですが、その高い目標に到達するまでの最初の一歩、二歩をどうするのか、という計画を立てて、少しずつ上がっていくしかありません。いきなり富士山の頂上に登ることはできないからです。
目の前の就職や学校の授業といった課題はこなせるかもしれませんが、10年20年先の人生まで計画するのは難しいものです。だからこそ、今できることは「今を精一杯やるしかない」ということです。また、何事にもチャレンジしてみる姿勢も非常に大事です。人間は、「そこに危険なものがあるよ」と分かっていても、実際にぶつかって痛い目をみるまでなかなか理解できないものです。賢い人は先を予測してうまく回避できるかもしれませんが、それも経験しないと分からないことなのです。学生時代に何か一生懸命になれること、熱中できるものがあれば、それはきっと皆さんの人生を支える力となります。
取材担当者(石嵜)の感想
「生きがいを見つけた者の勝ち」という言葉が、自分の人生の目的を見つけようとしている私たち就活生にとって、非常に力強いメッセージだと感じました。また、「痛い目をみる経験も大事」という話は、失敗を恐れずにチャレンジすることの重要性を改めて教えてくれました。社長が過去を振り返り「今の知識があれば」とおっしゃるように、私たちも、将来の自分を後悔させないよう、今この時を精一杯、目標を持って行動し続けることが重要だと強く認識しました。

【人口減社会のサバイバルとAIの活用】
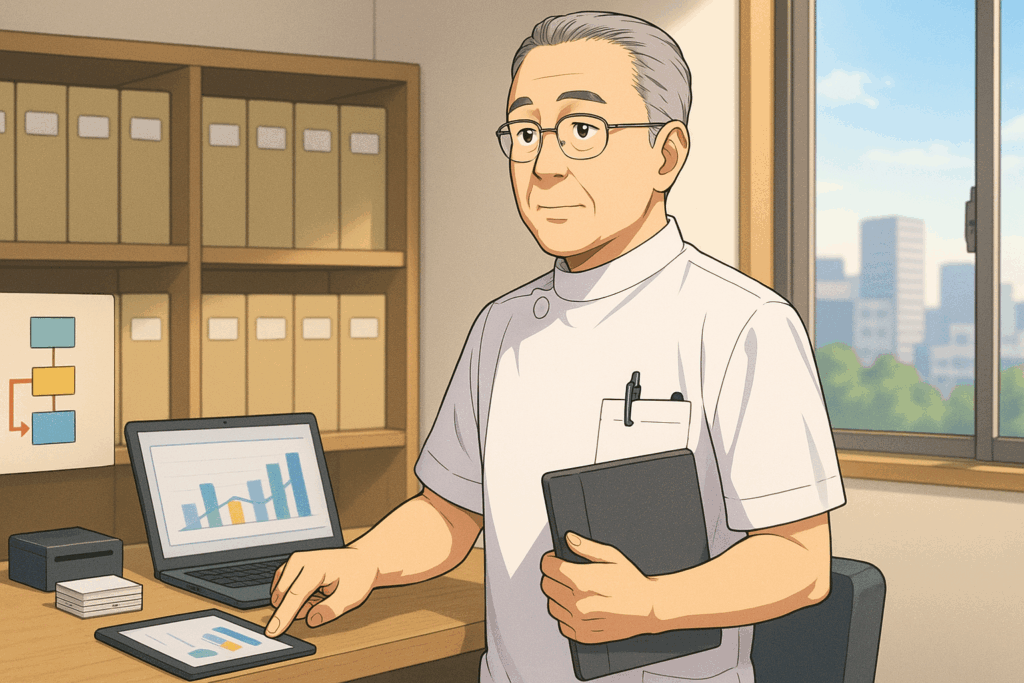
日本の人口はどんどん減っており、あと10年、20年は団塊の世代の人たちのおかげで食いつなげるかもしれませんが、その後、本当のサバイバルが始まるでしょう。出生数が恐ろしいほど減っている中、日本の胃袋は確実に小さくなります。コロナ禍で会社を小さくせざるを得ませんでしたが、これは逆に未来のサバイバルに備える上で理にかなった行動だったとも言えます。私は65歳ですが、「人生100年時代」と考え、今後は社会保険労務士、行政書士、そしてマッサージ指圧の知識を活かしながら、多角的に仕事をやっていきたいと思っています。
しかし、この士業の世界も、チャットGPTやAIには勝てない時代が来ています。例えば、雇用保険の手続きやPR文章の作成などは、AIが全て正確に出してくれます。私は実際に、銀行の懇親会で乾杯の挨拶をチャットGPTに全て書かせ、それを読んで好評を得た経験があります。チャットGPTは素晴らしいことを書いてくれるので、みんなが感動していました。
ですから、これからの時代、AIを使えるようにならないと、あっという間に時代に取り残されてしまうでしょう。みんながやっていて当たり前になってきています。私は、うちの会員に対し、有料版(課金)を利用すれば、自分の業態や仕事を分かってくれて、より質の高い答えを出してくれるようになる、と指導しています。
また、私たちの業界特有の課題として、医療の申請書(レセプト)を自動入力してくれるシステムを作りたいという案があります。患者さんの病名や施術回数、料金などを記した1枚の紙を作り上げるためのプログラムです。今すぐの問題ではないかもしれませんが、このような分野でもAIやIT技術を積極的に活用し、課題解決を図っていきたいと考えています。
取材担当者(石嵜)感想
65歳でいながらにして、未来の人口減社会やAI時代を見据え、チャットGPTを日常的に活用されている社長の柔軟性とポジティブさに圧倒されました。特に「士業もAIには勝てない」という言葉は、AIが私たちの未来のキャリアにどれほど大きな影響を与えるかを示唆しています。私たち若者が、このテクノロジーをいかに使いこなし、社会の課題解決や新しい価値創造に繋げていくかが、今後のサバイバルにおいて最も重要だと痛感しました。










