セノー株式会社は、1908年創業のスポーツ・健康器具メーカーです。体育館やアリーナの企画・設計・製造・施工から運営支援まで一貫対応し、学校・公共施設を中心に全国へ提供しています。ミズノグループの一員として、競技スポーツから健康・介護予防まで、器具提供に加え運動プログラムや施設運営の提案で、安心・安全で使いやすい環境づくりに貢献します。PPP・PFIを活用した施設整備や運営にも取り組み、地域のスタジアム・アリーナ活性化を支援。国内有数の実績と品質で信頼を築き、ユニバーサルデザインと安全基準に基づく製品開発を進めています。スポーツの力で人と地域の健康を支えます。環境配慮にも積極的です。今回は、体育施設の一貫対応で培ったものづくりと運営の知見、PPP・PFIによる地域アリーナ活性化の挑戦、そしてスポーツの力で健康を支える未来像まで、代表取締役社長にじっくりとお伺いしました。
<聞き手=石嵜渉(学生団体GOAT編集部)>
【今までの経緯・背景】
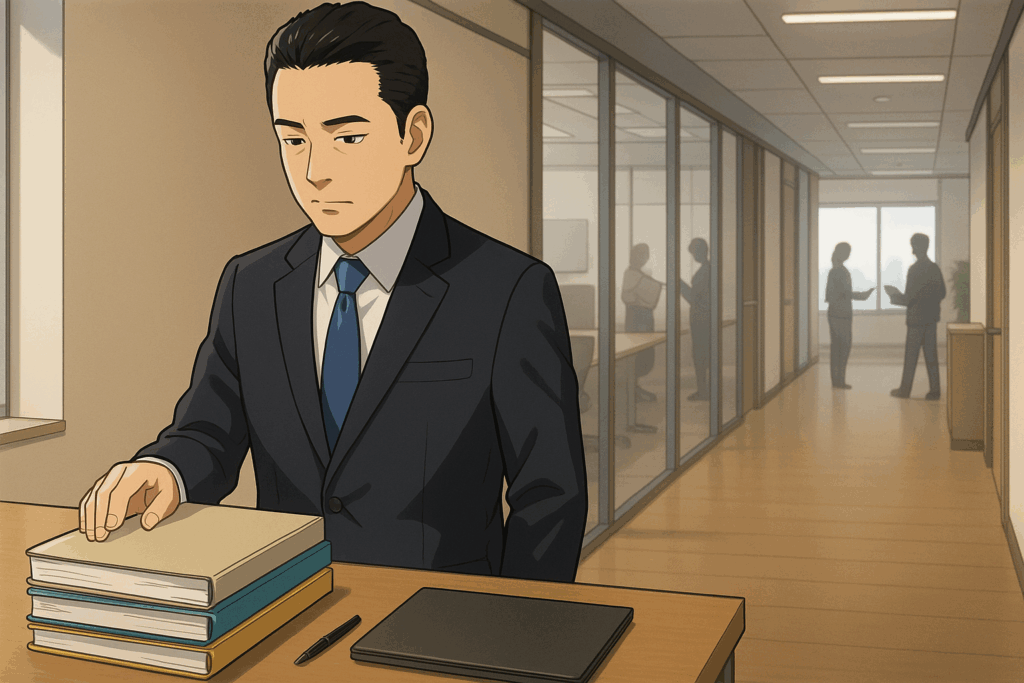
私は創業者ではなく、親会社であるミズノからの出向で、現在の社長を務めています。ミズノに入社した後、セノーに来たのは2024年1月、社長就任は2025年1月です。もともと会社経営や起業家を目指していたわけではありません。ミズノグループの会社として、セノーの業績を今後拡大し、グループ業績に貢献するという使命を受けています。
ミズノ本体の一部門に属していたときは、会社が大きいためセクションがきっちり分かれ、役割分担が徹底されていました。そのため、人材採用は人事総務部、お金に関する部分は経理部が担当するなどで、自分が担当しない業務も多くありました。しかし、セノーに来てからは一転して、人事総務から経理、お客様対応、売上に関わる部分から生産まで、すべてを見なければならない立場となりました。
この変化は、私にとって仕事上の大きな転機であり、「ほぼ新入社員と同様に、まったく別部署へ配属された」状態だと感じています。社長という立場は会社の大小に関わらず全体を見なければならず、これまで経験のない領域も含めて把握することが、現在の最大の課題です。
社員からは私がすべてを知っていると思われがちですが、知らないことは知らないと正直に伝えるようにしています。何もかも一人でできるわけではないからです。組織として大事なのは、各部門が役割を担い、それをいかにうまく機能させ、連携させるかです。陸上のリレーと同じで、いくら走力があっても、バトンをうまくつながなければ記録は出ません。
経営者の役割としては、「攻め」を前面に出すというより、まずは「守り」をしっかり固める意識が強いかもしれません。基本や重要事項を愚直にやっていくことが最も大事だと考えています。会社をつくるのは人です。新しい人材も必要ですが、いまいる人材をいかに成長させるかが要点です。
取材担当者(石嵜)の感想
大手企業から特化部門のトップへという経緯で、社長という立場になっても「ほぼ新入社員同様」と表現されるほど大きな変化があったというお話は、社長という立場の重さを感じました。以前は分業されていたすべての業務を担う中で、知らないことは知らないと言う正直な姿勢や、組織を「リレー」に例え、部門間の連携を重視されている点は、組織運営における基本の重要性を教えていただきました。技術やテクニックに走りがちですが、根本的な基本を大切にするというディフェンシブな姿勢が、結果的に組織全体の力になるのだと学びになりました。

【学生へのメッセージ】
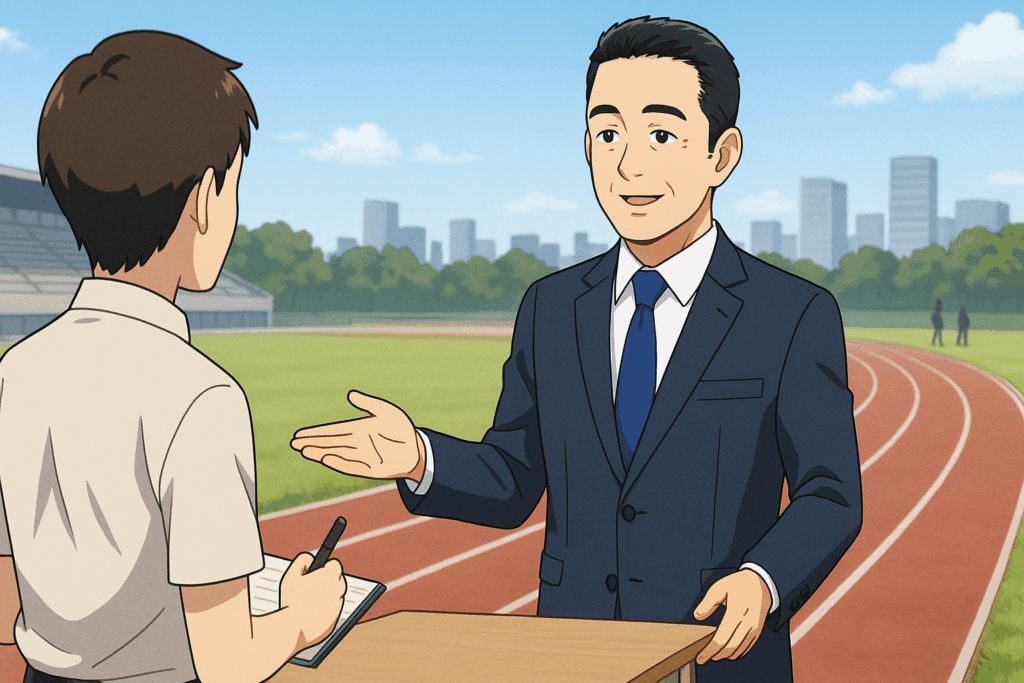
新入社員や学生には、「なるべく広い視野で、いろんな業界や仕事を実地で見てきてほしい」と常に伝えています。会社に入ると、どうしても仕事に関係のある部分だけを見てしまい、視野が狭まってしまうからです。そして、デジタル社会が進む今だからこそ、リアルの体験が極めて重要だと考えています。昔は現場に行かないと体験できないことがたくさんありましたが、今は行かなくても何でも見られたりします。それでも、「百聞は一見に如かず」という言葉の通り、現場に行ってリアルに触れる経験を、時間がある学生のうちに数多くしておくべきです。
例えば、世界陸上をテレビで見ていた人と、実際に現場で雰囲気を体験した人との間には、大きな差が生まれます。こうした現場でのリアルな経験の積み重ねこそが、将来、仕事上でさまざまな決断をするための礎(いしずえ)になるものです。私は、「大学の4年間は社会勉強の4年間だ」と考えています。
また、「知らない」と言える正直さが新入社員の特権です。社会に出て組織の中で活躍するために重要なのは、「正直であること」です。知らないことは知らない、分からないことは分からないと正直に伝えることが最も大事です。これは、学生や新入社員の「特権」でもあります。「教えてください」と言っても許される立場ですから、それをうまく活用するのが最も大事です。
私自身も、中学・高校時代はずっとスポーツをしており、その組織の中で動いていました。キャプテンを務めていた頃、やる気に温度差のあるメンバーが混在する組織をどう動かすかという経験をしたことが、後から振り返ると社会勉強になっていました。会社に行くと、同じ組織の中で違う意見を持った人が出てくるのは当たり前のことです。そのときに、どうやってバランスを取りながら、会社としてやるべき一つの方向に決めていくかが重要です。
取材担当者(石嵜)の感想
「大学の4年間は社会勉強の4年間」という言葉は、現在、社会勉強をするべく取材活動を行っている私自身に強く響きました。デジタル社会だからこそ、あえてリアルな体験を重視すべきだというアドバイスは、私たち若者が意識的に行動すべきことだと感じています。私も中学・高校時代にサッカーの副キャプテンを経験しており、やる気のある人とない人のバランスを取りながら組織をまとめる難しさを痛感した経験が、仕事につながるというお話には深く共感しました。また、「知らないことは知らないと言う」正直さが新入社員の特権であるという視点は、私たちがうまく活用すべき重要な学びでした。

【事業・業界について】
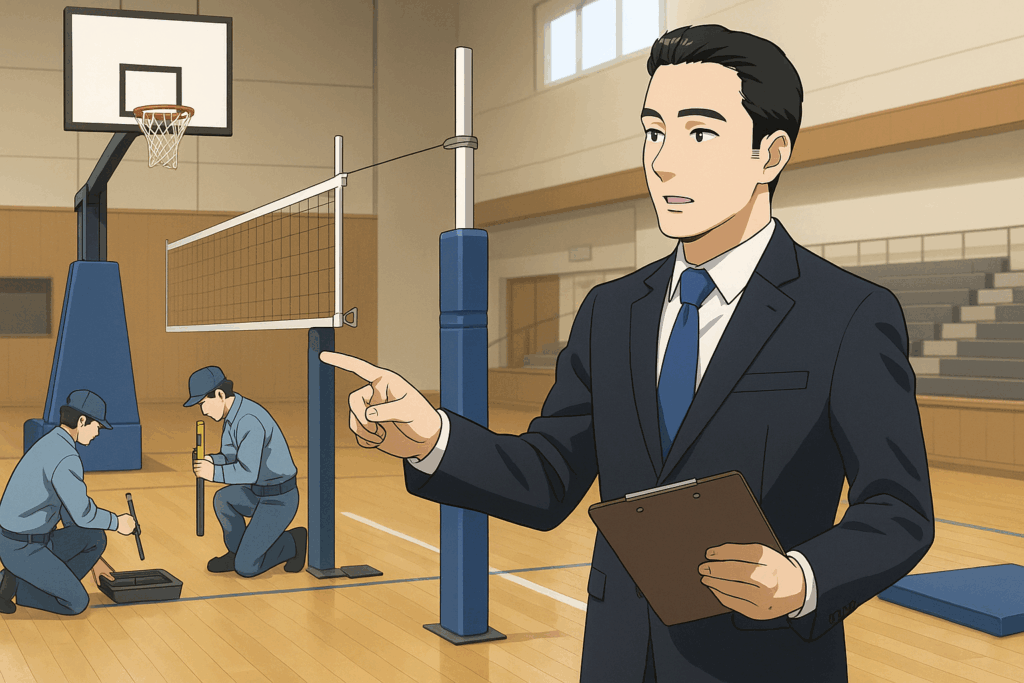
セノー株式会社のお客様は、BtoC(個人)ではなく、主にBtoB(企業や施設)です。体育館などの施設が購入主体であり、個人での購入がほぼないため、ミズノ本体と比べると一般の方への露出や認知度が低いのが現状です。
しかし、当社の製品は、バスケットボール、バレーボール、体操といった競技において、国際連盟から認定を受けています。この認定は、製品の優秀性が国際的な基準を満たしている証しです。私たちはメーカーですから、「確かな製品をつくる」ことが最重要のポイントであり、そこは疎かにしてはいけないと考えています。
認定を得るには厳格な基準を満たす必要があるため、品質へのこだわりがものづくりの根幹です。
取材担当者(石嵜)の感想
セノー株式会社が、特定の競技において国際連盟からの認定品を製造している、世界基準の「ものづくり」の会社であることに、製造メーカーとしての揺るぎないプライドと高い技術力を感じました。BtoBのビジネスモデルだからこそ、一般向けの認知拡大の難しさがあるという業界特有の事情も理解できました。しかし、世界的に製品の優秀性が担保されているという事実は、会社の確固たる強みだと感じています。

【今後の展望】
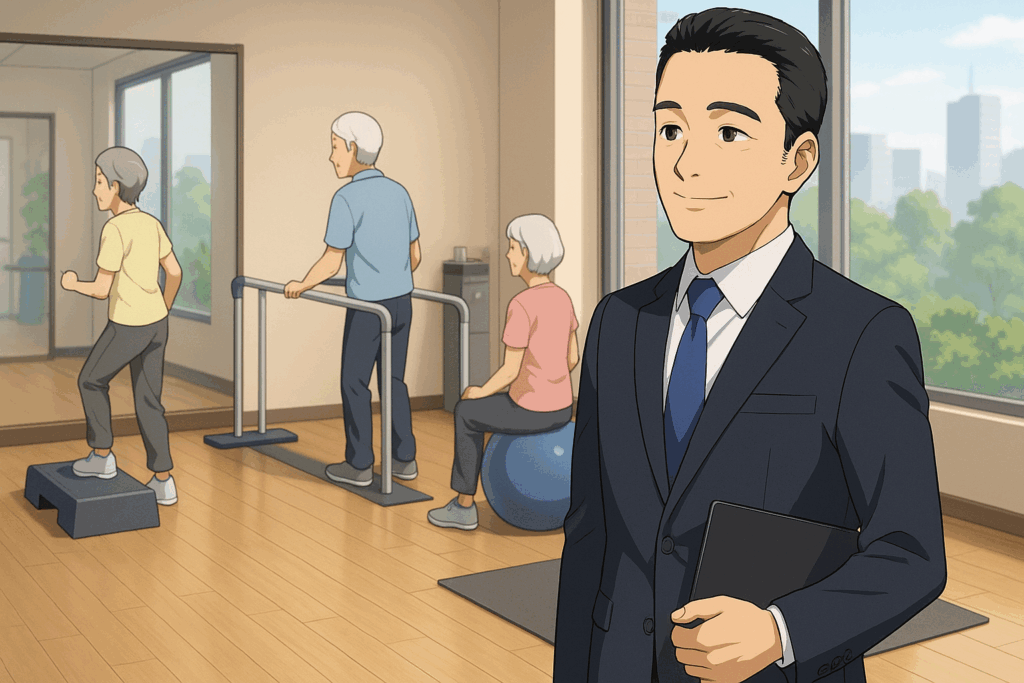
当社のビジョンは、ホームページにも掲げている通り、「スポーツと健康の未来を作る」です。これは、日本の高齢化社会における「健康」というテーマと、それをスポーツにどうつなげていくかという、社会貢献に直結するテーマです。
私が目指しているのは、「ビジネスの結果として社会貢献する」のではなく、「社会貢献の志がビジネスにつながっていく」流れへ、会社全体を導くことです。
そのために、スポーツ環境の整備――すなわち、競技スポーツだけでなく、健康のために体を動かす「運動」を支える環境や設備を、これまで以上に安全かつ簡便に実現できる製品づくりを、愚直に進めていくことが重要だと考えています。特に、高齢化社会に対応するため、日本人の身体特性や生活習慣に即した健康づくりに役立つ新製品を、しっかりと生み出していく。これが大きなポイントです。
事業の展開は日本国内に留まりません。欧米は競合が多く厳しい面もありますが、アジア諸国は今後、人口増と高齢化の進行により「健康」の重要性が一層高まると見込んでいます。現在、国際認定を受けている競技製品は海外でも販売されていますが、今後は健康領域においても、海外で評価される良質な製品を着実に開発し、日本発の製品がそのまま海外でも通用することを目指します。スポーツは世界共通であり、事業規模も世界規模へと拡大していくと考えています。
取材担当者(石嵜)の感想
「社会貢献をしようということがビジネスにつながる」という香山社長のビジョンは、非常に魅力的だと感じました。日本の高齢化という社会課題を解決しつつ、アジア圏を含めた世界規模で「スポーツと健康の未来を作る」という壮大な目標に、私自身もワクワクしました。製造メーカーとして愚直に「ものづくり」を追求する姿勢が、社会貢献とビジネスという両輪を力強く回していくのだと感じています。










