北海道ハピネス株式会社は、北海道で誕生した提案型人材企業です。私たちの原動力は、お客様からの信頼とスタッフへの感謝です。労働者派遣事業、有料職業紹介事業、そして登録支援機関として事業を展開しています。私たちは、ただ人材を派遣するのではなく、お客様の目的や目標を共有し、ベクトルの合った「人財」を配属させることが使命だと考えています。お客様とスタッフが共に考え、汗を流し、達成の喜びを味わう真の人材企業を目指しています。常に変化し続ける多様化時代に対応し、お客様とスタッフの幸せのための独自の提案や仕組みの開発を、私たちは本業の原点としています。北海道発の提案型人材企業として築いた「信頼と感謝」の基盤と、目的共有で“ベクトルの合った人財”を配属する仕組み、そしてお客様とスタッフの幸せを広げる今後の構想まで、経営トップにじっくりとお伺いしました。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【建設技術者から人材ビジネスへ:キャリアチェンジと創業の決断】
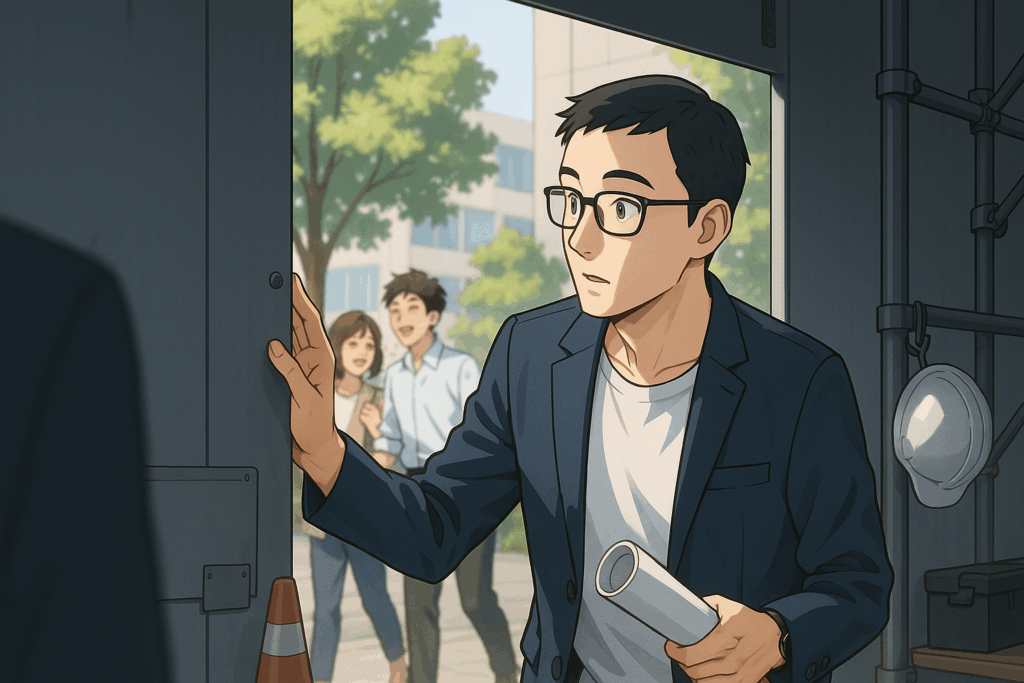
私は工業大学の建築学科を卒業し、ゼネコン(建設業)に就職しました。ビル建設における図面作成、業者への指示、計画立案を担う技術者として勤務しました。卒業後は大阪、東京、名古屋などで働きました。現場監督として工事現場で働いていた頃は、鉄板の塀の中で一日のほとんどを過ごすことが常態化していました。特に東京の現場で、一人で図面を描いている際、塀の外から楽しそうな笑い声が聞こえ、塀の外は楽しいのだろうと思ったことを覚えています。当時まだ25歳ほどでしたが、塀の外から聞こえる笑い声が羨ましかったです。
約6年働いた後、地元・北海道への転勤で戻ってきました。そのとき、図面を描く仕事とは違うことにも挑戦したいと考えました。先輩に「図面以外の仕事」を尋ねたところ「営業」という答えが返り、より楽しそうだと感じて営業職への転職を決めました。転職先として応募した会社がたまたま人材派遣会社で、そこから派遣の道へ進むことになりました。人材派遣会社で営業として働き始めると、それまでの建設系の人としか話さなかった生活から一転し、さまざまな業界の人と話せるようになり、とても楽しいと感じました。
業績も順調に上がり、入社2年後には会社の営業売上が5倍超となりました。その後、所長なども務め、派遣スタッフ数は入社時の88人から、最多で約1,100人超まで拡大しました。これは小泉内閣期の派遣法改正により、派遣禁止業種が一気に解禁された時代の波に乗った結果でもありました。しかし2009年のリーマン・ショックで仕事が一斉に止まりました。製造派遣は世界経済の悪化で消費が冷え、工場も止まるため、まず派遣スタッフが不要になります。その際、派遣スタッフや社員に辞めてもらうという辛い決断を経験しました。
そのとき、お客様から「藤川さん、自分でやろうよ。応援するから」と背中を押していただきました。今が底であればこれ以上世界経済も悪化しないだろうという逆転の発想で、「一番悪い時に作れば、あとは上がるだけだ」と考え、2009年に賛同した仲間と共に北海道ハピネスを立ち上げました。現在、創業から16年が経過しています。
取材担当者(高橋)の感想
長時間労働の中で「塀の外」の楽しそうな声に心を動かされ、全く異なる業界である営業職へ果敢にキャリアチェンジされた行動力に驚きました。逆境の中でも新しい仕事に楽しさを見出し、結果を出された姿勢は、私たち学生が社会に出るうえで大きな学びです。また、リーマン・ショックという最悪の経済状況を逆手に取り、お客様の声に応える形で起業された点から、ピンチをチャンスに変える経営者の熱量を感じました。

【少子高齢化に挑む:海外人材活用の背景と日本経済の課題】
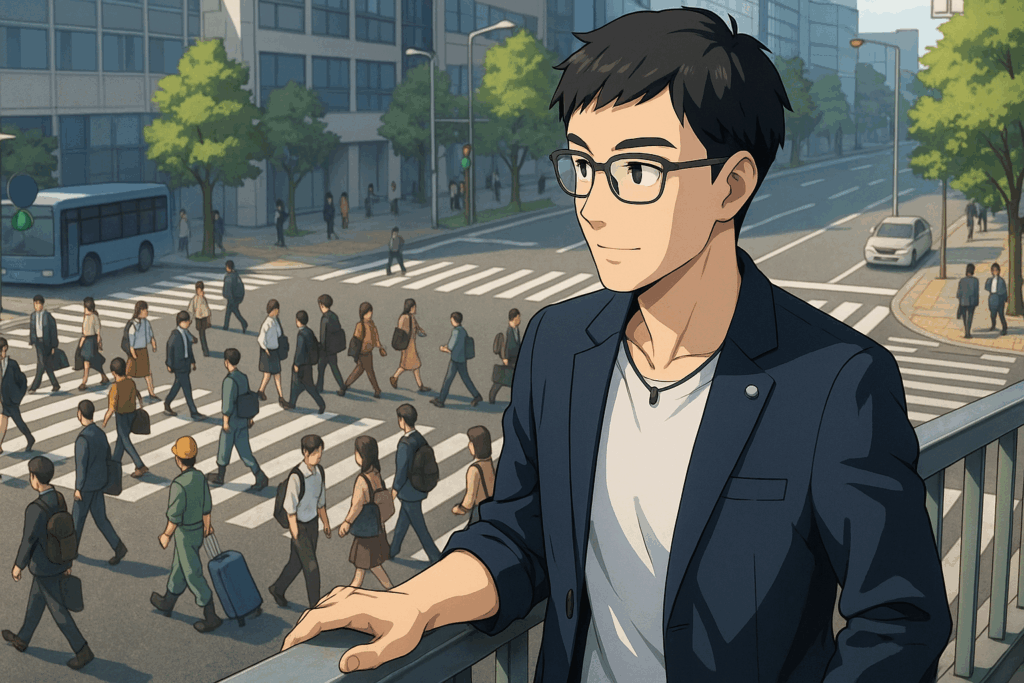
この世の中には、人が動かなければお金は動かないという原則があります。しかし、今の日本は少子高齢化により、経済を回す「動く人」が減っています。高齢化が進むと、経済を動かす人が減り、動かない人が増えるため、経済は構造的に弱含みます。この課題に対し、私たちは海外人材の受け入れを進めています。海外から来る若者は概して若く、働いて税金を納め、給与の約7割を母国へ仕送りします。残りは日本での生活費となりますが、生活があれば支出が生じます。働いて収入を得て、生活で支出する人を増やすことが、人手不足の緩和と経済活性化の双方に資します。
ベトナムやミャンマーなどでは、日本に来る若者の多くが「親に仕送りするために働く」という教育と強い使命感を持っています。家族内は親を頂点とするピラミッド構造で、「この家に生まれた以上、稼いで家に入れる」という価値観が根付いています。自分の欲しいものへの関心は薄く、より多く稼げばその分を家に送ります。親に褒められる――そうした世界観です。
これはかつての日本にもありました。戦後直後(現在の70~80代が若者だった時代)に近い状況が、いま東南アジアで起きています。当時の日本は、子が親を支える文化があったからこそ若者が多かったのだと思います。一方、いまの日本では子が働いても親が仕送りする逆転現象も見られます。これでは出生は細る一方であり、少子化対策には教育や文化の設計から見直す必要があると私たちは考えています。
取材担当者(高橋)の感想
「人が動かないと経済は回らない」という原則に基づく海外人材の導入は、複雑な課題に対する実践的な解だと感じました。特に「親への仕送り」を軸に働く価値観は、現代日本のそれと大きく異なり、強い示唆を与えます。日本の経済や文化を考えるうえで、この視点は重要だと思います。

【競争が激化する人材業界で「楽しさ」を追求する文化】
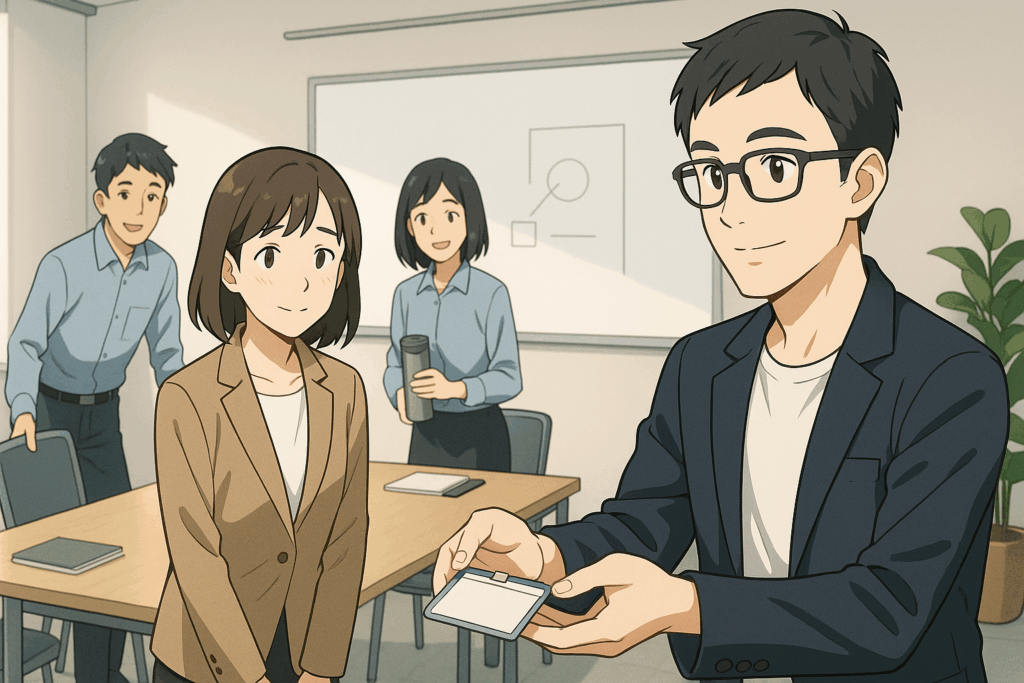
人材派遣業界では、人を集めるために時給を無理に上げて募集し、最終的に自社の利益を削るケースが散見されます。たとえば製造現場では、製品価格を急に値上げすることは難しいのが実情です。派遣価格が据え置きのまま時給だけが上がれば、派遣会社の利益は圧迫されます。一度上げた時給は下げにくく、収益構造が厳しくなるのが業界課題です。
こうした環境下で、私たちは創業時から「仕事をどう楽しくやるか」を重視してきました。派遣会社では、いくら優秀な営業でもお客様ばかりを見ていてはうまくいきません。最優先は、当社から派遣されて働く人が『北海道ハピネスに採用してもらって良かった』と実感できる状態をどう作るかです。
働く側が「北海道ハピネスで働けて良かった」と言えるよう、日々取り組みを検討しています。お客様は、嫌々働く人の派遣会社より、楽しそうに働く人の派遣会社を選ぶのが自然です。結果として、働く人からの紹介で新たな人材が集まる好循環も生まれます。最終的には、働く人が楽しく安心して働ける職場をつくることが、今もこれからも変わらない目標です。
さらに本社社員に対しても「明日も来たくなる会社」づくりを目指しています。日曜日の『サザエさん』のエンディングを聞きながら「明日から会社だ」とワクワクできる会社とは何かを、社員全員で形にしていきます。私自身、営業に転じた際「これは楽しい」と感じていました。楽しくできる仕事は業績が必ず伸び、辛い仕事は続きません。社会では仕事を選べない場面もあるからこそ、与えられた仕事や環境の中で楽しみを見出す視点転換が必要です。
取材担当者(高橋)の感想
業界の構造的な難しさの中で「働く人の幸せ」を第一に掲げる哲学は、顧客第一主義に偏りがちな企業と一線を画します。「サザエさんのエンディング」の喩えは、日常の瞬間にワクワクを宿す職場の意義を端的に示しており、就職活動で重視すべき文化の要点だと感じました。与えられた仕事の中に楽しみを見出すという姿勢は、社会人に必須の視点です。

【「ワクワク」を追求するための具体的取り組みと海外人材スキーム】
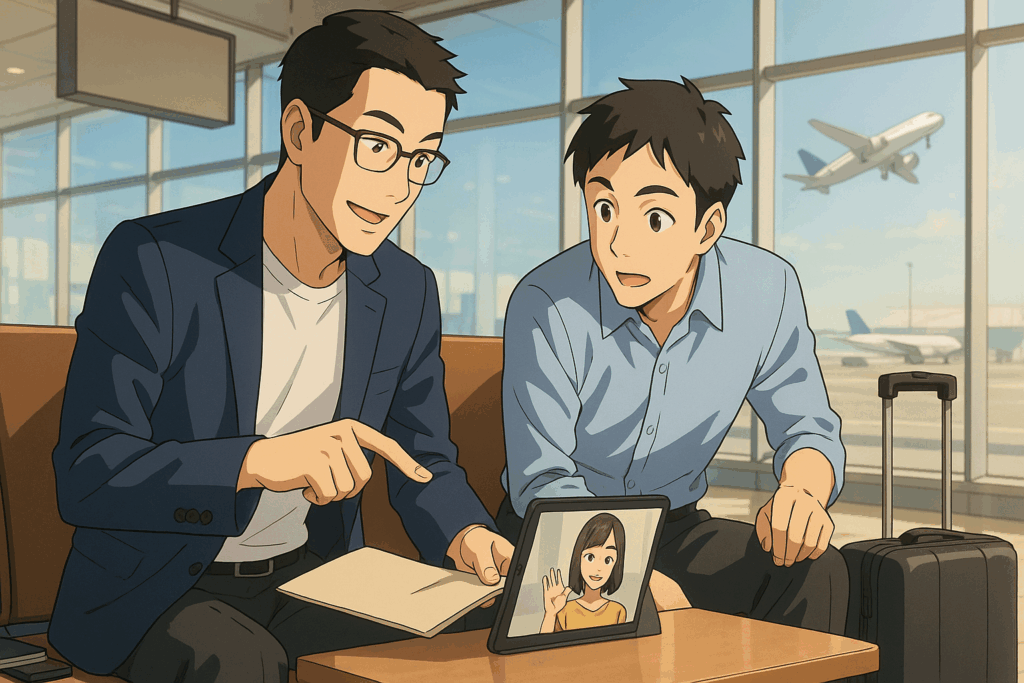
私たちは社員のモチベーションとワクワク感を高める具体策を実行しています。第一に、海外とのつながりを生かします。若手社員を順次、私と共に海外出張へ同行させ、現地の生活や日本で働きたいという熱意を直接見せます。これにより、社員は「君たちはそんなに日本が好きなのか」と衝撃を受け、日本人としての誇りを新たにします。結果として「自分の仕事が日本をプラスにする」という認識が芽生え、仕事への意欲が高まります。また社内では、チームごとに業務の改善策を研究し、発表会を行うなど、社員自ら工夫を凝らしています。自分の仕事を自分で改善し続けることは、楽しい職場づくりに直結します。
海外人材の導入は、コロナ禍を経て2023年途中から本格再始動しました。海外関連の売上はまだ全体の約1%で、残り99%は日本人向け人材サービスです。海外人材は法令上、作業員としての派遣就労ができないため、私たちの主力は特定技能制度を用いた紹介・登録支援(管理)です。現地で試験に合格した人材が直接お客様の従業員となり、私たちは登録支援機関(登録番号:21登-006404)として、毎月の面談・生活支援・入管提出書類の支援などを実施し、管理料を受領します。派遣に比べ売上規模は小さい構造ですが、お客様と地域、そして日本を目指す若者の双方に資するため、積極的に提案を進めています。
受け入れは容易ではありません。受入企業は「所属機関」としての認定が必要で、収支が悪い、従事内容が定めと相違する等の場合は認定されません。協議会などの団体所属も求められ、簡単には受け入れられないのが現状です。私たちが登録支援機関の許可を持つのは、お客様と海外をつなぎ、採用・指導・支援を円滑化するためです。現在はお客様と共に海外で面接を行い、その後の在留資格認定などの手続きにおおむね4か月ほどを要します。今年度に入国する人材は増加傾向にあり、現時点で20数名が控えています。全スタッフ約500人のうち、当初は約5%(約25人)が外国人材となる見込みで、来年には10%を超えると見ています。海外人材が100人を超える段階では、派遣とは性質が異なるため、北海道ハピネス株式会社とは別会社を立ち上げ、楽しさやワクワクをさらに高め、社員の原動力にしたいと考えています。
取材担当者(高橋)の感想
自分の仕事が社会に貢献している実感をもたらす仕掛けとして、社員の海外同行は非常にユニークだと感じます。日々の業務の先に「日本をプラスにする」という目標を見出すことで、取り組みが変わります。法令・認定等の複雑な手順を越えて仕組み化を進める原動力は、まさに「ワクワク」に支えられているのだと思います。

【学生へ送る、社会で成功するためのアドバイス】
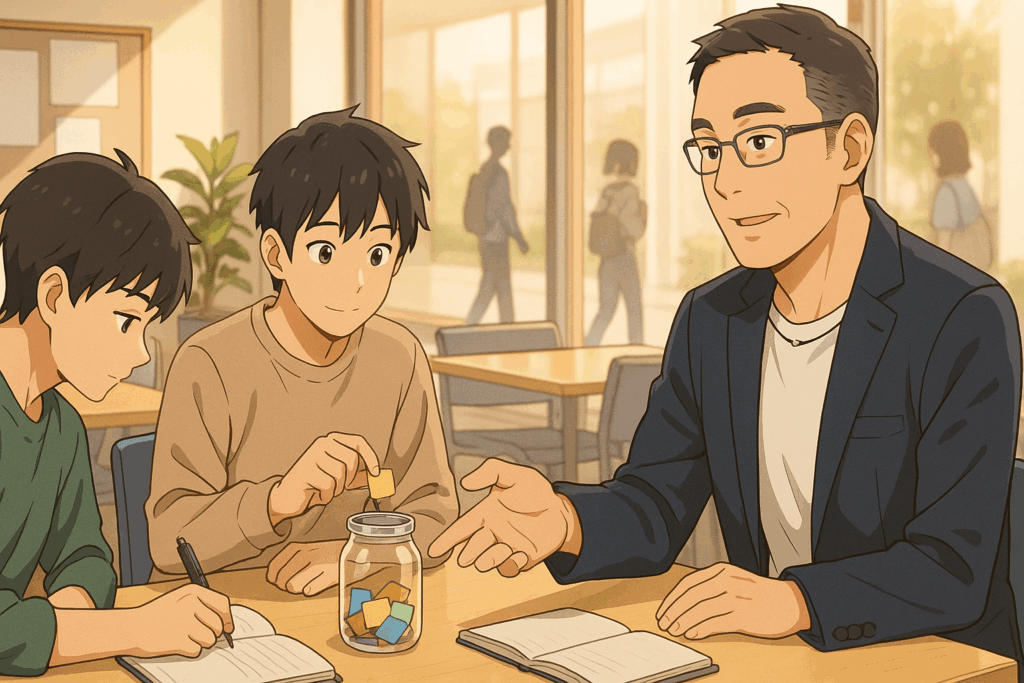
学生の皆さんにお伝えしたい最重要の原則は、「お金の流れは感謝で動く」ということです。仕事とは、「ありがとうございました」という感謝の連続がお金に変わっていく営みです。学生時代に、自分が何に「ありがとう」と強く感じたか、誰かに「ありがとう」と言った言われた経験を、些細なことでもよいので記録し「貯めておく」とよいです。いまだ商売になっていない「ありがとう」の種を見つけ、「これは自分がやる」と実行できれば、新しい事業につながります。
サークル等で多くの人と関わり、「ありがとう」の経験を積み重ねることは極めて重要です。成績が良くても、他者と関わらず「ありがとう」の経験が少ない人は、社会に出たとき「どこまでがありがとうか」が分からず苦労する可能性があります。社会人として成功するには、学生時代にどれだけ「ありがとう」を貯められるかが鍵になります。
取材担当者(高橋)の感想
仕事やお金を「感謝が価値へと転換されるプロセス」と捉える視点に強く共感しました。学生団体の運営において人との関わりから生まれる「ありがとう」の価値を意識してきましたが、それを新規事業の種として捉える発想は実践的です。今後も「ありがとう」を意図的に貯める経験を増やし、社会で通用する人間になる準備を進めたいと思います。










